
JMIA 認定登山インストラクター 栗山 祐哉 のブログページです。
山が好きで、人生山にかけちゃった、だいぶ山をこじらせちゃったタイプです。
そんな山好きが送る、登山技術や山道具、山のうんちく情報を満載にしてお送りする、かなりマニアックな記事を書いています。
山、こじらせちゃってる方にこそ、是非読んでいただきたい!!
カテゴリー
登山のロープの選び方|どのロープを何mもてば良いのだろう?
初めてロープを買う時って、どんなロープを買ったら良いか悩みますよね。
答えから言っちゃうと、結局は用途に合わせて何本かのロープが必要になるのですが、そうは言われても何をどう最初の一本として買えば良いか、なかなかその指標が掴めないのでないかなって思うんです。
まずそもそも、登山に使用するロープとして最低限どんな性能が求められるのか?
これまた使用用途にもよるのですが、原則として " ダイナミックロープ " である必要があります。
ダイナミックロープとは " 伸びることで衝撃を吸収するロープ " を言います。
細かいこと言うと、墜落に伴う落下エネルギーを、ロープの伸びにより時間軸に分散することによって最大墜落衝撃を緩和しているのですが。まぁ小難しい話はおいといて、要はバンジージャンプと同じで、びよーっっんって伸びるから衝撃吸収するのですよ。
これが伸びないロープだとマズくて、墜落衝撃がそのまま体に伝わっちゃいます。10m落ちたら10m分の衝撃がそのままダイレクトに体に伝わっちゃうんで、場合によってはロープが原因で死に至ります。
ロープは伸びなきゃダメなのです。
でもさ、あんまり伸びすぎると地面まで落ちちゃう可能性が高くなるし、良く伸びるロープほど細くなっていくから岩角で切れるリスクは高くなる。使用目的に合わせて、どのくらい伸びるロープを選ぶかが重要になるのです。
なので人間が怪我しない範囲のロープの伸び率に留めて作る必要があります。

.
クライマーに発生する墜落衝撃は折り返されたカラビナの摩擦抵抗により、0.7倍 の墜落衝撃がビレイヤーに伝わります。この時、折り返されているカラビナには、クライマーとビレイヤーのそれぞれに発生する墜落衝撃を合算した、クライマーに発生した墜落衝撃の 1.7倍 もの墜落衝撃が発生します。
人工的に整備されたクライミングジムやスポーツクライミングのゲレンデでは極めて丈夫に支点が作られていますが、アルパインクライミングではそうはいきません。
錆びたハーケン、細い灌木にスリングを巻いたもの、水っぽい溶けた氷に打ったアイススクリューなど、明らかにプアな支点にロープをセットしなければならない場合もあります。
このこともあり、アルパインクライミングで原則として " 落ちちゃダメ ” なのです。
" 万が一落ちた時に止まったら良いね " と言う感じでロープによる確保を行うので、低いところでロープが伸びて地面に激突しちゃうより、40m とか登ったところで落ちて、中間支点が破断して地面まで落ちちゃう方が遥かにヤバい!
中間支点保護の為には、しっかり伸びて衝撃吸収するロープが必要になるわけです。
この様に、使用目的によってロープの規格を分け、シチュエーションに合わせてより安全な選択ができる様になってます。
スポーツクライミングで使用するシングルロープに対し、アルパインクライミングではハーフロープ規格のロープを使用します。

なのでロープを2本使ってロープの屈折を減らし、本来あるべきロープの衝撃吸収を最大化するわけです。
ロープの伸び率が高いハーフロープは当然シングルロープに比べて細くなるわけで、岩角などで切断するリスクが高くなります。
ロープを2本使うことでそのリスクも分散できる、実に合理的なシステムなわけです。

そこでオススメなのが、シングル、ハーフ、ツイン、3つの規格全てが通ったロープを選択すること。
シングルロープの規格基準に収まる範囲のロープの伸び率や破断強度を有しながら、ツインロープの規格基準を満たす衝撃吸収性を持つロープを言います。(ツインロープとは、2本のロープを1つのカラビナに通すことでシングルロープと同じ役割を持つロープを指します。)
つまりあまり伸びず、丈夫なのに、衝撃だけはしっかり吸収してくれる良いとこ取りのロープってことです!
しかもシングルロープとしては最も細い部類のロープになります。なので当然軽い!!
この3規格のロープを30m用意するのが、最初の1本としてオススメです。
まぁ軽いとは言えシングルロープなので、例えばハーフとツインの2規格のロープに比べれば重くなるわけですが、最初の一本としてはオススメです。
と言うのも、たぶんこのブログをここまで読み進めている人の目的って、登山での使用が目的だと思うのですよ。例えばバリエーションルートで懸垂下降したいとか、沢登りやってみたいとか、岩稜登山で安全確保したいとか、主にはそう言った目的だと思います。
岩角や落石などでの破断リスクが比較的小さいシングルロープで、且つ衝撃吸収性も高いロープが理想的。長さとしてもこれらの使用目的であれば多くの場合30mあれば足りるケースが多いと思います。
最終的に本格的なアルパインクライミングを目標にする場合などにはクライミングジムでのトレーニングも欠かせませんが、これも多くの場合、30mあれば足りるケースがほとんどです。あまり長くないロープを使えば手返しが良くなり、練習回数ももっと増えるでしょう。
でも30mの3規格ロープって、実はあまり売ってないのですよ。
そこで Kuri Adventures では、60mのロープを仕入れて、半分に切って販売します!(現在準備中)
しかも外被にケブラー繊維を織り交ぜることで、岩角破断耐性まで高くなっているスペシャルなロープ。
個人的にも愛用していますが、とても安心感があって良いです♪

でもね、Kuri Adventures ではクライミング用品は講習参加者にしか販売しない事にしています。
と言うのも、知識なくして使用すると、むしろそれが原因で命に関わる事故に至る可能性があるわけですよ。
うちは商品販売で利益を上げて食ってるわけではなく、お教室を営んでいる訳です。なのでたくさんの人に商品を買ってもらいたい訳ではなく、ちゃんと学習してもらって、安全に登山を楽しんでもらいたいと考えています。
なので講習参加時に現場で商品をお渡しする形をとっており、店舗販売や通信販売は行っていません。
もちろん登山用品店で買ってもらっても良いと思うけど、いずれにせよちゃんと学習する機会は設けて欲しいなって思います。
ちゃんと学習して運用すれば、ロープってほんとすごく登山の幅を広げてくれるんですよ。
それも例えば山岳会の先輩に習うとか、大手ショップの講習会に参加するんでも良いんです。是非、学習機会を設けましょう!
(と言いつつ、そこは Kuri Adventures の講習をご利用頂ければ嬉しい限りではありますが ^^; )
エバニュー Ti400NH|世界最軽量のクッカー
永らくエバニューの Ti400FD と言う小さなクッカーを愛用して来ました。 カップメシに必要な300cc前後の湯をわかせるサイズで、もうこれ以上は無いと思われる50.1gの超軽量ボディ。大好きな山道具のひとつです。
しかし少し前にこのストイックな Ti400FD からさらにハンドルを取り払った、Ti400NH なるクッカーが販売されました。
火に掛けるナベがノーハンドだぜ?
バカじゃねぇの??
しかしこの鍋の重量が33.6gとマジで軽い!
ハンドルとそれに巻かれたシリコンチューブ、ハンドルの取り付け部分のプレート。これらの重量が16.5g。
実に1/3 の重さです。無視できません。


軽量化をする上で大切な事は、その事によるリスクの増加が最小限となるものである事。 例えば鍋からハンドルを取り払う事で生じるリスクで言えば、お湯をこぼすリスクなどが増しますが、お湯をかぶったりしない限りは直接的な危険はそこまで高くありません。 軽量化による安全性の向上と、危険性の増加を天秤にかけ、総合的な安全性が向上すると判断した場合にのみ変更を行います。
山岳遭難死亡事故の圧倒的要因第一位が転滑落。 荷物が軽ければバランスを崩す可能性を下げられるし、雪の上での滑落停止の成功率も大きく向上します。荷物がコンパクト化すれば風で煽られる力も小さくなるし、枝や岩に引っかかる回数も減らせます。 軽量化は、ちゃんと考えて行えれば山の安全に大きく貢献してくれます。
この辺りの軽量化の話をまとめて書籍化する事となりました!
まだ細かい打ち合わせはこれからなのですが、これまで蓄積したノウハウを全て詰め込んで、より多くの登山者の役に立てる一冊に出来ればと思います。 目指すは来春かなー?
グラナイトギア ヴァーガ2 のサイドポケット
最近、グラナイトギアのヴァーガ2を使いはじめました。
これまでは " 一泊二日なら冬でも30Lで幕営装備を組める " を信条にパッキングを行なってきましたが、正直なところ限界ギリギリなのも事実。









このグラナイトギアのヴァーガ2ですが、バックパックとしては超優秀です!
52Lの容量で540gと超軽量ながら、ダメージを受けやすい箇所にはかなり厚手の生地を使用していて丈夫です。これより軽いバックパックも確かに一部存在はしますが、ラフに使っても大丈夫そうな作りはやはり安心できます。
この手の軽量ザックにありがちなのがウェストベルトやショルダーハーネスの作りがチープなことによる疲労や手間などがあったりしますが、ショルダーに関してはかなり剛性感のある厚手のパッドが入っており、ウェスト周りにも最低限ながら腰骨をソフトに包んでくれるパッドが入っています。さらに正面とサイドには大きなポケットが有り、行動中に取り出しやすいものを収納しておくことができます。
フロントポケットにはグランドシートとタープ、サイドポケットにはトレッキングポール、カメラ機材、ガイラインコードとペグなど、すぐに取り出したいものを入れています。
この作りでありながら、抑えるべきところはしっかり抑えて540gに留めていることは優秀以外の何物でもありません!
『 雨蓋が無いのは不便ではないか? 』とたまに聞かれますが、案外そうでもないです。むしろ個人的には雨蓋の無い、ロールトップタイプのバックパックを好んで使います。
上の写真の状態で、100cm 程度のロールマットを筒にし、その中に30L程度の荷物が入っています。概ね35L前後と言ったところでしょうか?
つまり上にはまだかなりの余裕があります。
ハーネスやロープ、ヘルメット、脱いだジャケットなど、途中で増減する様な荷物を入れるスペースを十分に残しながら、それらが抜けた後にもきれいなシルエットを保ちやすいメリットがあります。雨蓋があるとどうしても上部が潰れ、不格好になりがちですからね(^_^;)
そういった意味で、ロールトップのモデルの方が使いやすいかなと感じています。
サイドポケットの問題は抱えるけどこれは好みの問題だし、気に入らないにしても簡単な裁縫で良い感じに仕上げられます。
グラナイトギアの定番バックパックであるヴァーガ2、良いバックパックですよ♪
【雪山登山のグローブ】続・防寒テムレスのカスタマイズ ~ インナーボア剥離作業編 ~

防寒テムレスって圧倒的な作業性が魅力なんだけど、それでも行動食食べたり、カップラーメン作ったりってレベルの作業になるとさすがに難しくなってきますよね。 その様な作業をするにはもっと薄手のインナーグローブで行うべきなんだけど、防寒テムレスと薄手のインナーグローブを組み合わせるとせっかくの作業性が損なわれてしまう。
かと言って、細かい作業のたびに素手になるのも嫌だし、付け替えるのもなかなかの手間・・・。
そこで防寒テムレスのインナーボアを引っ剥がして、1レイヤーのオーバーグローブとなるよう加工してみました♪
そんなんするなら防寒じゃないテムレス(ブラックテムレスなら " 03 " がそうですね)にすりゃ良いじゃんって思うかも知れませんが、実は手袋の形が違うのですよ。
インナーグローブをした状態で丁度良い太さ感のサイズになると、指先が余りすぎてやっぱり作業性が悪くなる。防寒テムレスの素手で適正のサイズから内ボアを引っ剥がすと、太い1レイヤーのテムレスができるのです。
これに薄手のウールのインナーグローブ(スマホも弄れます♪)を組み合わせることで、高い作業性のオーバーグローブとして使おうって魂胆。
これなら泊まり登山でもしっかりと乾かすことができるし、手汗で湿ってきてもインナーを交換できるし。なによりアウターを外してもそこにインナーがあるって状態は良いよね!
絶対的防水性と作業性を持つペラペラオーバーグローブの出来上がりです(*^^*)

グローブをひっくり返し、裁ちばさみでインナーボアに切れ目を入れます。

その穴からテムレス本体を引き剥がすよに捲り返し、インナーボアを分離させます。

手首の部分は縫い付けられているので、裁ちばさみで丁寧に切り取ります。本体を傷つけないように注意しましょう。

切りっぱなしの部分はほつれるので、ライターで炙って処理します。

インナーボアの代りに、薄手のインナーグローブを装着します。ウールのグローブを選択すると手が冷えにくくて吉です♪
ここではLサイズの防寒テムレスで作成していますが、LLサイズや3Lサイズから作れば、ラックナーのヒマラヤングラブの様な厚手のウールグローブとの併用も可能かと思います。防寒テムレスから作るペラペラオーバーグローブと未脱脂ウールグローブの組み合わせとか、保温性と操作性のバランスに優れたベストな選択の一つかもしれませんね。
低予算で簡単に作れるので、是非いろいろ試してみてください♪
カフ無しLサイズ
カフ無しLLサイズ
カフ付きLサイズ
カフ付きLLサイズ
薄手ウールグローブ
未脱脂ウールグローブ

雪山登山講習
雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。
雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。
しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
【 雪山登山技術 】ワカンの正しい装着方法

豪雪地やマイナーなルートでは、トレースが無い事も良くあります。一切の踏み跡がない雪面を歩き、自分自身でトレースを刻むこともまた雪山登山の醍醐味のひとつだと思います。しかし雪の深さが膝にも達すると、ラッセルはとても大変になってきます。そこで足が沈まないよう、カンジキを装着して歩くことになります。
スノーシューが有利か、ワカンが有利か。この議論は時折されますが、それは使用するシチュエーションにもよります。比較的なだらかな地形で、且つ豪雪地であればスノーシューが有利でしょうし、急峻な場所や倒木が多い場所などではワカンが有利でしょう。本来であれば行く場所によって選択を変えるべきですが、日本の山ではワカンの方が出番が多くなります。
日本の山は森林限界以下の山域から急峻な事が多く、急登のラッセルを強いられる事も多くあります。この様な場所では倒木や木々の枝が張り出していることも多く、これらを乗り越さなければなりません。取り回しの点からワカンの方が有利でしょう。
また一般的にはトレースのはっきりした人気のルートを歩く方が多いと思いますが、この様な場合にはカンジキの出番はありません。現実的には一日中持ち歩くだけになることの方が多いでしょう。
スノーシューは 1.5 ~ 2kg 程度の重量となりますが、ワカンは 750g ~ 1kg 程度と半分くらいの重さで済みます。ただでさえ重い雪山登山装備の構成の中で1kg前後の重量差はとても大きな差となります。
一定以上の積雪量がある山に赴く時は、原則として携行すべき装備であると考えています。特に宿泊を伴う場合、翌日に予想外のドカ雪が降る事もあり、自分たちが歩いたトレースさえも完全に消え去ることもあります。カンジキが無ければ行動時間は大幅に増え、大きなリスクとなることもあります。
そんな重要な道具であるワカンですが、意外なほど正しい装着方法が周知していない様に思います。ここではこのワカンの在るべき正しい装着方法についてお話しようと思います。
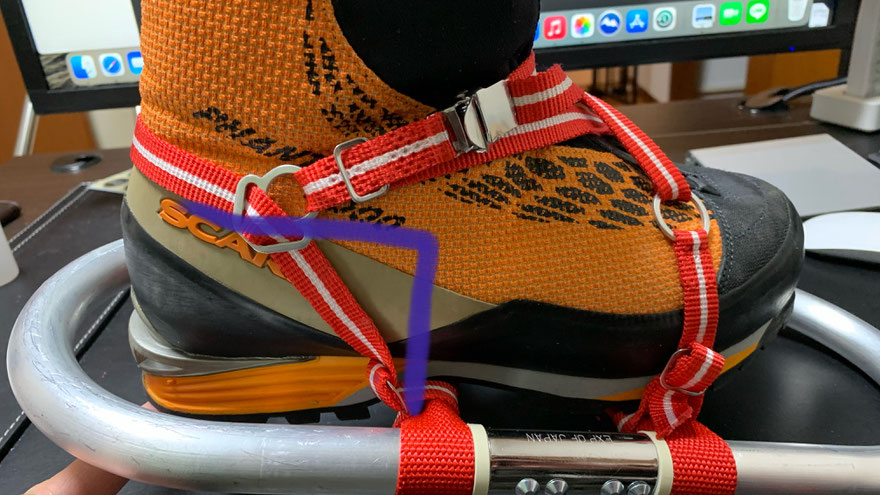
意識せずに装着するとこの写真の様に縦向きのバンドが斜め後ろ方向に傾斜した状態になりがちです。しかしこの状態では、後ろに傾斜した分と同じ長さだけつま先方向にズレる余地を残してしまうことになり、急斜面でのキックステップなどで足が前にズレてしまいます。
またこの位置で強く締め込んでも、縦のバンドが垂直付近になる頃には緩みが発生し、ワカンが左右にずれたり、時には歩行中に外れてしまうこともあります。

縦方向のバンドが垂直になる位置で締め込みます。この時、縦のバンドは短めにセットしておいた方がズレにくいです。あまり短くし過ぎると脱着しにくくなりますので注意しましょう。予め自宅でセットしておくことが大切です。

またバンドをリングに通す向きも実はとても大切!
リングの内側から外側に通してしまうと、ちょっとしたことで簡単に緩んでしまいます。外から内に通してしっかりとテンションを掛けることでテープがリングと靴の間に挟まり、摩擦が発生します。この事により手を離しても緩まない状態になります。
たったこれだけの事ですが、明らかにワカンが緩みにくくなるので意識しておきましょう。(逆に何度も脱着を繰り返すようなシチュエーションでは、リングの内から外に通す事で簡単に外せる様になります。但しズレやすいので注意しましょう。)

ワカンの携行方法って意外と悩ましいものなのですが、僕はバックパックのサイドにバンジーコードをセットし、4点で固定してワカンを装着しています。これならブラブラしないし、脱着もスムーズです!
ワカンは現在数社から販売されていますが、個人的にはエキスパート・オブ・ジャパン " ハイスペックスノーシューズ " のフラット形状のMサイズを愛用しています。
反り返りがあるタイプの方が歩行はしやすいのですが、キックステップの際にワカンが雪に刺さりにくい欠点があります。またフラットタイプのものであれば、ワカンをひっくり返してアイゼンと併用して使用する事もできます。クラストとラッセルが交互に現れる稜線歩きなどでは有利です。
重量がとても軽いこと、バンド止めの金具が優秀で、全く緩まないことなども大きなメリットです!(バンドの余分な長さをカットした状態で、両足実測で750gと全アルミワカンの中でも最軽量です。)
昔は中央のテープが切れやすい欠点がありましたが、プラスチックパーツで保護されることで耐久性を飛躍的に向上させました。

ちょっと重いけど、オクトスのワカンもオススメ!
スノーボードのビンディングの様にラチェットで締め込むタイプのワカンで、脱着が圧倒的に楽です。まず緩む事もありません。(縦バンドがワカンに垂直になる位置出しのセッティングは必要です。)
以前はしばらくこれを使っていましたが、片足150gの重量増を許容できるならこれもアリな選択だと思います。
ワカンを正しく装着することで新雪の歩行は格段に楽になります。
ちょっとした事なのですが、知ってると知らないでは快適さに大きな差が生まれますので、今回ちょっとご紹介させて頂きました♪
ご参考にして頂ければ幸いです。
栗山愛用の軽量わかん
ラチェット式わかん
浮力大きめ、フラット
浮力大きめ、ベンド
緩まないバンド
ラチェット化キット

雪山登山講習
雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。
雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。
しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
【雪山登山の手袋】防寒テムレスのカスタマイズ!

防寒テムレスは作業用ゴム手袋として開発されたもので、ゴム手袋ならではの絶対的防水性に加え、透湿性のある素材で作ることでゴム手袋の弱点である蒸れを解消した素晴らしい商品です。この特性により冬季登攀用手袋として10年ほど前からアルパインクライミングの世界で使われるようになり始めました。
作業用ゴム手袋特有の強烈な青い色が醸すダサさがありましたが、昨今では黒いカラーも登場し、さらには手首にカフまでつけた登山を意識した商品も登場。これにより一気に一般登山者の間でも普及しました。
防寒テムレスは保温力に欠ける点、ビレイや懸垂下降時にデバイスに手が巻き込まれる危険性があるなどのリスクがありますが、その圧倒的な作業性と防水性は他に代えがたいメリットがあります。僕は作業性を優先して防寒テムレスを直着用(インナーグローブは無し)し、ビレイや懸垂下降時、停滞時、強風の稜線歩行時などにはオーバーミトンを防寒テムレスの上から着用することで対応しています。
灌木に素早くスリングを巻き、アイススクリューに小さなカラビナを確実にクリップし、Vスレッドにロープを通すなど、細かい作業を手袋したまま行わなくてはならない冬季登攀では防寒テムレスが大いに役立ちます。一般的な雪山登山においても、アイゼンやワカンの脱着のしやすさ、ラッセルの際の防水性、テント泊でも翌朝凍らないなど多くのメリットがあるでしょう。
しかし登山専用に開発されたグローブと言うわけでは無いので、ちょっと使いにくい部分もあります。そこで防寒テムレスブラックのウィンター02をベースに、より使いやすい様にカスタマイズしてみました♪

グローブ同士をつなぐプラパーツは、僕は使ってないので切り取っちゃいました。

チャムスのプラスチックカラビナを通し、ハーネスやバックパックのショルダーにクリップして携行できるようにしています。

ちょっぴりダサいテムレスのロゴはアルコールを染み込ませたティッシュで拭き取って消しちゃいますw

手首にバンドを取り付けます。バンド中央部だけ縫い付け、接着剤で接着。針穴も接着剤で目止めしておきます。

バンドはロープを買った時についてたマジックテープを再利用しました。ほら、なんか高級感あるww

手首にはリーシュとなるバンジーコードを接続し、脱着の際に風でふっとばされない様にしました。

左手にはタッチペンを取り付け、グローブを外さなくてもスマートフォンをイジれる様にしています。これ便利♪
防寒テムレスはとても操作性に優れた手袋ですが、行動食を食べたり、カップラーメン作ったりなど、本当の意味での細かい作業はやっぱり難しい。極薄の手袋も別途ポケットに入れておいて、本当に細かい作業を行うときには素早く付け替えます。素手になる時間は作らないようにしましょう。
とても使いやすい防寒テムレスが、カスタマイズによってさらに使いやすくなりますよ!
カスタマイズに使用する部品類を下にまとめました。是非試してみて下さい♪

雪山登山講習
雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。
雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。
しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
最軽量プローブ ARVA RACE240

積雪期の山では、どこで雪崩に遭っても全く不思議ではありません。もちろん地形や気象条件、積雪量などによって雪崩の発生しやすさなどは異なりますが、一定以上の積雪があればどこでも雪崩の可能性はあります。一方で、明らかに " 雪崩が起きにくい条件 " があるのも事実で、リスクを避けて行う雪山登山であれば雪崩に遭遇する確率は極めて小さいとも言えます。
実際に令和元年の山岳遭難事故の統計を見ても、道迷い、滑落、転倒、病気、疲労の5項目で全体の86.7%を占めており、雪崩による遭難事故は0.3%に留まります。その半数はバックカントリースキーヤー・スノーボーダーに発生しており、登山者が雪崩に巻き込まれる可能性は遭難事故全体の0.15%と僅かなものでしょう。
しかしもし万が一雪崩に巻き込まれてしまえば、ビーコン、プローブ、ショベルが無ければ助けることはできません。雪崩の即死率は10%とされており、9割はまだ生きてるんです。装備と技術があれば高確率で助かる命を、それが無い為に失われる事があってはならないと思います。
そうは言っても、まず使う機会が無いであろう道具は可能な限り軽い方が良いと思います。そこで僕が個人的に愛用しているのが " ARVA RACE240 " と言うカーボン製のプローブ(ゾンデ棒)です。
プローブには大きく分けて2種類の長さがあり、凡そ360cmの長いタイプのもの、240cmの短いタイプのものがあります。また素材も丈夫なアルミのタイプと、軽量なカーボン製のものがあります。バックカントリーなど雪崩リスクの高いアクティビティを行う方であればアルミ製の長いプローブを用意すべきでしょう。しかし雪崩リスクはさほど高くない環境で行動するなら、カーボン製の短いプローブでも構わないのではないかと思います。
そんな240cmのカーボンプローブの平均的重量は200g程度となりますが、なんとこのプローブは120gと驚異的な軽さです!!

バンジーコードとトグルを追加してるので、実際には120gちょうどってところです。

サイズもコンパクトな製品で、バックパックに横向きに入れることもできます。
プローブは雪崩事故が発生しない限り、雪洞を作る際の積雪深を調べるのに使用したり、せいぜい幕営時のペグの一本として使う程度であり、登山中に使用することはほとんどありません。だからこそ欠かさず持ち歩くためにも、軽い道具である必要があると考えています。
ARVA RACE240 は、1gでも軽量化したいクライマーにとっては特に大きなメリットを生み出す道具であると感じます。
尚、当然の事ながら、道具だけ持っていれば良いってもんじゃありません。雪崩埋没した人を救助する技術も含め、安全に雪山登山を行う為には様々な技術を習得する必要があります。
それに関しては、是非 Kuri Adventures の雪山登山講習にご参加頂ければ幸いですw
皆様のご参加をお待ちしております♪

雪山登山講習
雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。
雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。
しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
グランドシートでハンモックのアンダーカバーを作ってみた!

ハンモックの寒さ対策にはアンダーキルトを使う訳だけど、大雨の時には地面からの跳ね水で汚れたり、風が強い時はアンダーキルトの温まった空気が対流してしまい、アンダーキルトをしてても寒さを感じてしまうもの。そのアンダーキルトを防水生地で覆ってしまえば、雨風によるトラブルを下げられるのではないかと考えました。
先日の記事では グランドシートを使って万が一ハンモックが破れてしまった際のバックアップのハンモックを作る方法を紹介したわけだけど、ここでもグランドシートを使ってアンダーカバーも担っていけないかと思うのです。
ハンモックの場合はできればグランドシートはあった方が便利だし、ってか、万が一に備えた予備のハンモックとしてどうせ持っていくんなら、これを活用しない手は無いなと思うわけです。
で、早速試してきてみました!


うーーーーん。この時点で案外悪くないのだけど、風にはバタつくよね。
これだけでも泥はね対策はほぼほぼ完璧だし、保温性にやや欠けるものの、風もだいぶ避けられるとは思う。だけどやたらスリングとカラビナを多用していろいろ工作しなきゃいけないのはちょっと手間だし、何よりもスマートでは無い。
アンダーキルトと同じ様に、各辺がクシュクシュっと絞れれば良いのだよなー。
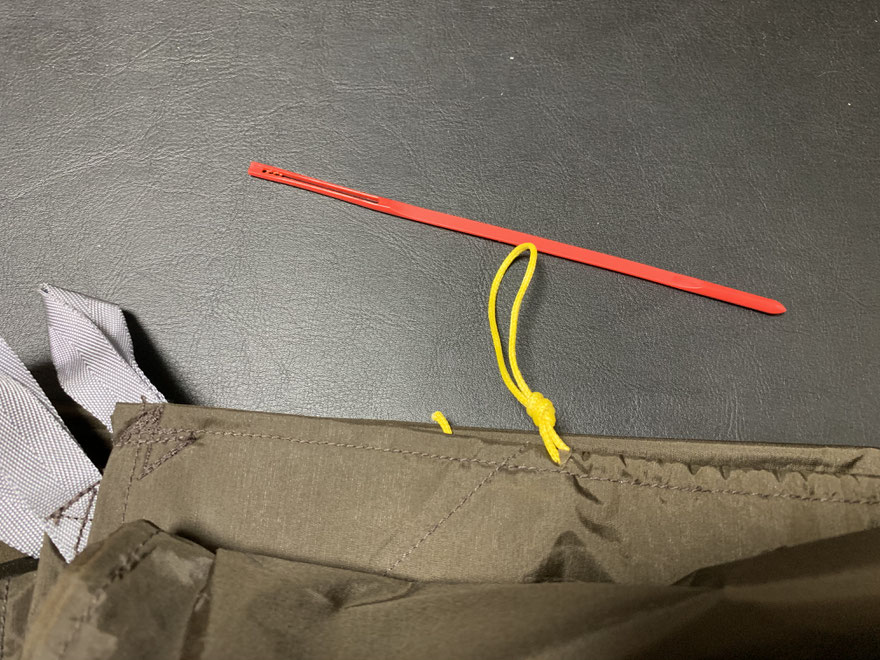

アライテントのアンダーシート2の場合、各角の補強の為に生地を当ててあり、それを縫い付けているステッチが入っています。それよりも内側に穴を開けないと紐が通せないので、この位置にハサミを入れます。強度を損ないすぎないように、切れ目はステッチに届かない範囲で!
すっぽ抜け防止にオーバーハンドノットで結びを作ります。コードロックを使っても良いのでけど、軽量化の為にあえて採用せず。スリップノットで止めることにしました。(不便だったら追加するかも?)
紐は保水しないように 2mm のダイニーマコードを使用。太さ的にはこれより太いと入らないし、これより細いとすっぽ抜けちゃう。使えるコードロックもほとんど存在しなくなります。2mm が無難かと。
さらに長辺側の中央部にポンチで穴を開けてハトメをカシメます。その穴にアクセサリーカラビナを設置し、ハンモックのサイドリフター用のループに接続することで中央部のバタつきを抑えます。

写真はバンジーコードですが、これはイマイチでした…。アクセサリーカラビナが吉!
これを直接アンダーキルト用のループにアクセサリーカラビナで接続します。(多くのハンモックにアンダーキルト接続用のループが縫い付けられています。個人的に愛用している KAMMOK Roo Single も、Cocoon Ultra Light hammock も、ほぼ同じ位置にループがります。他のメーカーは分かりませんが、この2つは同じアンダーカバーの作り方で使えるはずです!ただしセンターのサイドリフターループは KAMMOK Roo Single の方にしか付いてません。)
各辺のコードを引いて絞ってみると?


ほれみろバッチリ!!これ、めちゃくちゃ良くね?
アンダーキルトとアンダーカバーのクリアランスも程良く、実際に体重をかけるとクリアランスも小さくなります。でも密着はしないので、結露した水が内部に溜まったりしてもキルトを濡らさないし、キルトが圧迫されてロフトを潰すことによる保温力低下も防げます。ってか、僅かにクリアランスがあることで、確実に保温力も1ランク上がるかと!


さらについでにもういっちょ!
ちょっと強引だけど、ザックカバーとしても使えそうです。
各辺のコードを目一杯引いて絞り込み、片短辺側のループをセンターのカラビナに接続してショルダーハーネスと固定します。
ちょっとダボ付いて見えますが、たぶん泊まり登山装備なら割とちょうど良いくらいのサイズになると思う。
この時点で、
・グランドシート
・アンダーカバー
・レインカバー
と、4つもの役割を果たしている。
これが実測で僅か 216g なんだから優秀だと思いません?

裁縫が苦手な方でも、超簡単に作れます。自分でカスタマイズした道具って、それだけでなんか凄く嬉しいものだし、実際にハンモッカーにとってはかなり便利な道具となると思うのですよ。
ここで使っている商品を下にリンク貼っといたので、是非試してみて下さい(*´ω`*)
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
ハンモックの穴開き対策

先日 YouTube の動画撮影中に起きたハプニングで、ハンモックが引き裂かれて落ちる事件が起きました…。
専門店さんに相談してみたところ、どうやら小枝や石などを知らぬ間に乗せてしまい、そこに体重をかけてしまうことで小さなをきっかけに引き裂かれることがあるとのこと。エアーマットのパンクなどと同じで、滅多に起こらないが可能性を捨てきれないらしい。
暖かい季節ならいざしらず、寒い時期にこのトラブルを起こすと時に命に関わることもあるかも知れない。そうでなくても確実に辛く、虚しく、切ない思いをするのは間違えない。
エアーマットと違ってハンモックの場合、本当に軽いものでは 150g 前後の商品も数多く存在する。ぶっちゃけ2個持ったって大した重量ではないし、エアーマット1つ分の価格で2つ買えてしまうくらいリーズナブルなものでもある。
でもさ、全く使わない道具なのに、予備のためにもう一個持ち歩くのってなんか癪じゃない?
いや確かにヘッドライトなんかは万が一に備えて予備を持っていってるけど、幕営具の場合は何故かこれを許したくない…。
そこでちといろいろ実験してみました!
まずね、最初にやってみたのがタープポンチョをハンモックにしてみる作戦。
ハンモック泊をやるところって基本的には森林限界以下の山域なわけで、その範囲においてはポンチョを雨具として使用しても良いと個人的には思ってる。換気性が高いから案外蒸れないし、熱くない。バックパックも濡れないし、けっこう優秀なのですよ。
で、実際に乗ってみた!

これをハンモックとして使えれば大幅に軽量化!

素晴らしい!乗れたっ!! しかし、このあと悲劇が…。
おぉっ!?乗れたっ!!けっこうイケんじゃん!!?
ビリッ…ドスン………。
いやダメじゃん(;´Д`)
はい、ちーん。
さよなら諭吉パイセン。1万円終了ー。
再起不能なまでに終了ー。
15D の薄い生地に、頭を通す穴まで開いてるわけですよ。そりゃー無理ですよね ^^;
これができれば雨具の差し替えで、結果として重量増無しでバックアップを作れるんじゃないかとも思ったのですが、甘かった。
しかしこれで諦めませんよ!
次に考えたのが、グランドシートをバックアップのハンモックとして活用する方法。
タープポンチョですでに設営方法を研究済みなので、シートでハンモックを作るのはもはや余裕だぜ!!
ここで使用したのはアライテントのアンダーシート2。40D
とハンモック生地としてもウルトラライト系のハンモックとキャンプ系のハンモックの中間くらいな位置づけ。重量も 198g(実測) と許容範囲だ。

接続は60cmスリングをシートベンドにしてみました。これなら解くのも簡単♪

ちょっと小さめですが、バッチリハンモックとして機能します!
結論としてはまったく問題なし!!
タープポンチョの時にあった " ビヨーン " って伸びる不安感もなく、ビシッとしっかりした強度を感じられます。サイズこそ 140cm × 210cm と小さく、実際に乗ってみると足が少々はみ出ますが、バックアップとしては問題ないかと。
確かに装備重量増にはなるけど、みんなできればグランドシートは持っていきたいよなって思いません?
タープ張って、ハンモック設置してってやってる間、荷物置いとく場所って欲しいじゃないですか。でも登山に無駄な装備は可能な限り減り減らしたい中で、グランドシートはリストラ対象にされやすい存在。
でもハンモック破損時のバックアップとしても持っていけるならアリな気がしません??
他にも、大雨の日ってアンダーキルトが地面からの跳ね返りで汚れるのが気になるし、風が強い日はアンダーキルトをしててもちょっと寒かったりします。これをグランドシートハンモックで覆ってあげることで問題解決!
さらにハンモックの横に少し感覚を開けて設営すれば、荷物置き場を真隣に作ることも可能です。
ね!これ、超ナイスアイデアじゃね??

ハンモックはその性質上、破れて落ちるトラブルを完全に回避することはできません。いつでもその可能性は考えておかなくてはならないのです。そのひとつの対策案として、グランドシートを予備のハンモックとしても使う方法についてお伝えさせて頂きました。
尚この実験の際、手持ちの薄いグランドシートでも試してみましたが、やはりかなり不安な感じ。重量と強度の問題をいろいろ考えて、このグランドシートに辿り着きました。けっこう良さそうです!
あと手持ちのグランドシートに小さな穴が空いていたことも気になりました。この様な小さな穴をきっかけに、引き裂きトラブルは発生します。グランドシートという性質上、どうしても傷つきやすい存在。ハンモックが破けた時のバックアップとして用意していたグランドシートハンモックまで破けた日にゃ…。もはや目も当てられない…。
しっかりと定期チェックはしておきましょう^^;
この情報が、皆様のお役に立てれば幸いです♪
もしグランドシート買うなら、下のリンクからポチってね!!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
ハンモック最強説!

僕の登山は主に森林限界以下の森で行う登攀的山行となります。春から夏にかけては沢登り、秋の時期であれば藪岩登攀、冬に入るとアイスクライミングと、概ね森林限界以下の、それも極めて急峻な地形の中で活動しています。
国土の周りを全て海で覆われた我が国では、世界でも有数の降雨量を誇ります。雨により山の風化が進み、森林限界以下の山域から極めて急峻な地形が生み出されています。これは世界的にも稀な地形で、日本ならではの登山が楽しめます。
もちろん北アルプスなどの森林限界を超えた山域の展望の素晴らしさも認めますが、どこかヨーロッパに憧れを懐き、その背を追っている感を感じてしまうのは僕だけでしょうか?
日本の土地において、日本にしかないフィールドで、日本ならではの登山を楽しむ。そんなスタイルが僕は好きです。
山岳登攀を求めた山行を行うので、基本的には登山道から外れた急峻で不安定な地形の中で活動します。この様な山域において、平らな地面などほとんど存在しません。地面に眠ろうとすると、石でデコボコしていたり、斜めの地面しか無く快適に眠ることなど到底できません。
山の中で如何に幕営適地を見つけるかも登山の楽しみのひとつであり、僅かに見つけたその場所に、如何に眠るか。そこに登山者としての実力が試されると、本気でその様に考えていました。
ばーか言ってんじゃねぇw
もうね、過去の自分にそう言ってやりたいww
今年の春にハンモックに出会って以降、もう他の幕営具には戻りたくないくらい、僕はこれを気に入ってしまった。

いやさ、もう地面なんて関係ないのよ!
森林限界以下で活動している以上そこら中に木は生えているわけで、木さえあればどこでも幕営適地になるわけ。
そこがどんなにデコボコしてようと、どんなに急峻な斜面だろうと、どんな激ヤセ尾根だろうと、木さえあればいつでも超快適に眠れるのがハンモックの魅力なのです。
みんなさ、胸に手を当てて正直に話してみよ?
テント泊登山は確かに楽しいし、それこそ登山の在るべき姿だと思う。うん。それは僕もそう思う。
でもさ、実は眠りが浅くなったり、何度も夜中に目が覚めてしまったり、本当の意味で快適では無いよね?
てか、自宅のベットで眠るか、テントで眠るかって言われりゃ、そりゃ自宅のベットの方が快適なわけで、本音で言えばできればテントなんかで寝たくなんか無いわけ。
でもテント泊登山はとても楽しいから、だから仕方なく外で泊まるんだよね?
みんながそうかは分からないけど、正直なとこ僕はそう思ってきた。
それを根本から覆す良さが、ハンモックにはあったのだよ!
家で寝ててさ、ふと 「そろそろハンモックで眠りたいなー」 なんて思っちゃうわけですよ。
これって多分、自宅で眠るよりも快適だって感じてるんじゃないかな?
実際、ハンモックに切り替えてから夜中に目が覚めることは無くなったし、翌日の体力の回復度が明らかに変わった!
これは結果として登山の安全性にも繋がるんじゃないかと思うのです。
そして何より、眠ることそのものが楽しいって感じる。これこそハンモックの最大の魅力なんじゃないかな♪
もちろんただ快適だとか、楽しいだとかだけではない、登山で選択すべき合理性もある。
例えば山岳テントと比較した場合、圧倒的に軽くなる事。山岳テントで夏に泊まろうとした場合、だいたい1.5kg程度となると思うんだけど、これがハンモックと軽いタープなら、400g以下となる。これはだいたいツェルトと同じ重量だよね。軽い!
ツェルトで泊まっても重量的には変わらないわけだけど、ツェルトの場合には虫の侵入とか、大雨時の床下浸水の心配とかあるでしょ? でもハンモックなら常に宙に浮いてるし、蚊帳付きのものもあるし、そうでなくとも、マダニやムカデ、ヤマビルなど、地を這う虫は少なくともやってこない。当然雨の心配もない。
ハンモックは基本的にタープと組み合わせて使うので、まわりは常に開放されている。だから結露が発生せず、常に幕営具を乾いた状態に保てる。結果、連泊のリスクが下がるし、湿気で重量が増すこともない。これも大きな利点!
そして何より、どんな地形でも、木さえあれば安定して眠れるのは、他のシェルターじゃありえない。ハンモック最強!!

もちろん欠点もあって、森林限界を超える山域では基本的に使えないとか、風が特に強い場所だと寒いとか、破れてしまったら寝床を失うとか、厳冬期の保温、下からの水ハネ対策、荷物の置き場など、考えなきゃならないことがたくさんある。
でもそれって工夫次第でどうにかなることも多いし、与えられたパッケージをただ黙って使うんじゃなく、自分なりに考えて創意工夫してみる事ができるのもまた、遊びとして楽しめる要素だと僕は思う。
人によって登山のスタイルと合わない方もいるかも知れないけど、少なくとも僕の山行スタイルではベストマッチな幕営具だと思ってる。この素晴らしさを、是非より多くの方に知ってもらいたい。
いやさ、なにもこれに泊まらなくたって良いのよ。
ハンモックって握りこぶしくらい小さくなるし、軽いものだと150gちょっとのものもたくさんある。
これをバックパックの片隅に入れといて、小さな沢の脇にハンモックを張ってみて、そこでランチしてみてさ。いつもの登山にちょっとリラックスする時間を取り入れてみるとか。それだけでも楽しいじゃん?
で、興味が出たらキャンプ場とかでまずは試してみてもらいたい。そしたらきっと、ハンモックで泊まることが好きになると思うから(*´ω`*)
ね?興味出てきたでしょ♪
マジで良いからさ、一緒にユラユラしよーぜっ!
Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉
Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。
登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。
生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!
ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。
メトリウス ダイナミックPAS

これまで多くのランヤードはダイニーマなどの伸びない素材で作られてきました。衝撃をまったく吸収しない素材でランヤードを作ることに対する危険が認知され始めた昨今では、ダイナミックロープで作られたランヤードシステムが徐々に主流になりつつあります。
ペツルが先駆けて販売したコネクトアジャストが大変人気を集めましたが、やはりPASなどを代表するリング型デイジーチェーンのランヤードシステムより使い勝手が劣りました。
ところがついに出たのですよ!伸びるPAS!!もうこれしか選択肢無いでしょ!?

メトリウス ダイナミックPAS
国内で最も主流のランヤードシステムと言えば、メトリウスのPASだと思います。小さなリング状のスリングを繋ぎ合わせたデイジーチェーンで、長さ調整や懸垂下降のセットアップのしやすさから多くのクライマーに愛されています。
しかしPASを始めとした各社のリング型デイジーチェーンの多くはダイニーマで作られています。近年では衝撃を吸収しないランヤードを使用するリスクが指摘されており、高所作業の現場では法律で厳しく定められているほどです。当然クライマーにも高所作業員と同じか、それ以上のリスクがありますので、ランヤードの衝撃吸収性はとても大切です。まったく伸びないダイニーマで作られたランヤードシステムに対する危険が指摘され始めました。

.
各社を先駆けてクライミングに適した衝撃吸収型ランヤードシステムを作ったのが PETZL.。このあたりのスピード感は流石です!
PETZL のコネクトアジャストはダイナミックロープに長さ調整機構を持たしたシンプルなランヤードシステムで、この調整機構が4kNで滑り始める事で調整機構がない状態よりもさらに衝撃を吸収してくれる優れた構造をしています。
安全性がとても高い商品なのでしばらく愛用していましたが、利便性においてはリング型デイジーチェーンのタイプのものと比較すると些か劣るなと言う印象でした。それでも安全性が高い事は安心感に繋がるので、しばらく愛用していました。
しかしついに出たのですよ!伸びるPAS!!
その名も " ダイナミックPAS " !!!
メトリウスさん、もうちょいなんか無かったのかい?って聞きたくなるくらいにシンプルでダイナミックなネーミングですw
ダイナミックロープで作られた安全性の高いランヤードで、且つ利便性の高いリング型デイジーチェーンの登場です。

UIAA 109 規格をパスしており、落下係数2 / 落下重量 80kg の落下で、墜落衝撃を 10kN 以下に抑えられています。流石に 10kN
もの墜落衝撃を受けては命に関わる大怪我を負うリスクが高くなりますが、落下係数1くらいまでは許容できる範疇かと思います。
クライミングロープやその他のランヤードシステムからのデータから、落下係数1では6kN程度となるのではないかと想定されます。これはとても大きな衝撃ながら、生命を脅かすほどの怪我を負う衝撃ではないことを示しています。
旧来型の伸びないランヤードでは、凡そ120cmの墜落で10kN、240cmの墜落で20kNものダメージを負う計算となります。即ち、120cmのスリングをランヤードにしていた場合、落下係数1ですでに命の危険を伴うリスクがある事になります。気をつけていれば大丈夫とは言いますが、うっかりミスすることもあるし、致し方なくリスクを追わざるを得ない場合もあります。
やはり衝撃吸収するランヤードを選択した方が安全性は高いでしょう。
実際に衝撃吸収するランヤードをしばらく使ってみて、その安心感は絶大だなと感じます。特に最近メトリウスのダイナミックPASにしてからは、使い勝手の面でも向上し、とても満足しています。
しかしそれまでに使っていたペツルのコネクトアジャストや、CAMPのクライミングランヤードスイングなどの様な長さ調整機構が付いたものの方が、墜落時の衝撃吸収力がより高くて安全です。この辺りは利便性を優先するか、さらなる安全性を優先するかで考えて良いかと思います。
是非ご参考にして頂き、より安全なクライミングライフを楽しんで下さい♪
メトリウス ダイナミックPAS
このブログで紹介している商品です。
使い勝手が良く、おすすめ!
ペツル コネクトアジャスト
ダイナミックPASよりさらなる安全性を求めるならこれ!
CAMP クライミングランヤードスイング
操作性抜群!人と被りたくない方はこれもオススメ☆
YouTube でも紹介しています!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
スリングはこれがオススメ!! エーデルリッド テックウェブスリング

登山やクライミングに使用されるスリングには、主にナイロンかダイニーマが使われています。それぞれに利点と欠点が存在するため、使用箇所に併せて選択することが求められてきました。
ナイロンは比較的熱に強く、結びによる破断低下率の低い素材だが、耐切創性が低く、また水濡れや凍結による強度低下率が高い。
ダイニーマは高い耐切創性と破断強度、濡れによる強度低下が起こらない利点を持ちつつも、極めて熱に弱く、また結びによる破断低下率も大きい。
この2つの素材を組み合わせたナイスな商品が存在します!

エーデルリッド テックウェブスリング
クライミングに使用されるスリングは主に2種類。ナイロンとダイニーマのどちらかから選択される場合が多いと思います。
それぞれに相反する特性を持っており、使用状況に併せて選択することが求められます。
ナイロンであれば、結び目を作ることに対する破断強度低下率が小さいことや、そこそこ熱に強いことなどが利点である一方で、耐切創性(刃物に対する切断耐性を指し、クライミングでは岩角破断などに対する耐性が該当する)が極めて低く、また水濡れで25%、凍結では最大で50%もの強度低下が起こるとされています。
一方でダイニーマは、ナイロンに比べて遥かに高い耐切創性を持ち、さらに一切水を含まない素材で濡れや凍結による強度低下が起こらないなどの利点があります。しかし耐熱性が極めて低く、それに伴いナイロンよりも結びによる強度低下率が大きくなると言った欠点も持ち合わせます。
これらの特性を加味して素材を選択することが求められます。例えばロープとの摩擦が考えられる箇所においてはナイロンが有利だし、スリングに結びを作るならやはりナイロンが有利。沢登りやアイスクライミングなどの濡れが予想される山行ではダイニーマが有利だし、岩角接触する箇所にもダイニーマの方が良いでしょう。支点構築にはナイロンの方が安心だし、中間支点ならダイニーマが安心ですかね。この様に、使用箇所、状況などを判断し、道具の選択が求められます。

しかしそうは言っても、その両方の特性が欲しい事も多々あります。ちょっと暖かい日のルートアイスでスリングが濡れてしまい、そのスリングを使って可動域制限付き流動分散支点の構築が求められるようなシーン。ガースヒッチで木にスリングを結び、岩角を跨いだ先でロープにクリップする様なシーン。これらの場合には選択を悩まされます。
ところが近年、この2つの特性を持ったスリングが登場してきました!
それを代表するのがエーデルリッド者のテックウェブスリングです。

.
テックウェブスリングは、コアにダイニーマを使い、外被に耐熱性の高いナイロン66を使用したとても賢い商品。
中心部はダイニーマでできているの濡れや凍結に対する破断強度低下を防ぎ、岩角での断裂に対する強度も保っています。ダイニーマだけでは耐熱性や結びによる破断強度低下が気になりますが、外被をナイロンで覆う事でこれらの欠点をカバーしています。
特に結びによる強度低下率は、ナイロンだけで作られたスリングと比較してもさらに強固で、結びによる強度低下がとても小さい事も大きな利点とされています。
最新の縫製技術が生み出した新しい技術で、今後各メーカーともこの手のスリングが増えていくのではないかと予想されます。実に優れたアイデアの素晴らしいスリングです!
実際に使用した感じでは、少し細めで厚手のナイロンスリングって感じの使用感。他のナイロンスリングより僅かに硬さを感じるものの、使いにくいほどではありません。結んだ状態でテンションが加わった時の解きやすさは、ナイロンとダイニーマの間くらい。現場で解けなくなることはなさそうです。
使用感にも問題はなく、安全性が極めて高い。お値段も一般的なダイニーマスリングと大きく変わらない程度なので、現状で考えうるスリングのあり方として最も理想的な選択では無いでしょうか?
あらゆるシーンにおいて、最もオールマイティーに使えると思います。
240cm
クワッドアンカーシステムの構築に適した長さです。
180cm
ツーバイトやラウンドターンでの中間支点設置に!
120cm
スタンダードな長さ。様々な用途に使えます。
但し石灰岩の山など、特定の状況ではケブラー(アラミド繊維)のスリングを選択すべき場合もあります。ケブラーは結びによる強度低下、濡れや凍結に対する強度低下が著しいと言う大きな欠点を持っていますが、耐切創性、耐熱性がずば抜けて高いと言う利点もあります。
岩角がとても切り立つ石灰岩などはもちろん、残置ハーケンへの直接的な接続、明らかに岩角に触れる箇所などではケブラーの選択が良いと思います。

テックウェブスリングの登場で多くの場合はその一択で問題ありませんが、やはり完璧ではありません。使用状況を事前に予測し、道具の選択をすると言うこと。その段階からすでにそのクライミングは始まっています。
それはスリングだけに留まらず、ロープ、カラビナ、デバイス類など、都度しっかりと考えて選択することが大切です。
そして、だからこそ山って楽しいと思うのですよ!
その選択の在り方のご参考のひとつにして頂ければ幸いです♪
120cm
オールマイティーに使える標準的な長さです。
60cm
アルパインヌンチャクなど、中間支点の延長に適しています。
5.5mm アラミドロープ60m
自由な長さに切って使用できます。懸垂下降時のバックアップロープとしても◎
YouTube でも紹介しています!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山と自転車

登山者と自転車の相性は良いと感じています。例えば登山に自転車を活用すれば、縦走登山の際に予め出口に自転車をデポして入口まで車で行けば、アクセス問題は解決します。また遠く離れた駐車場に車を停め、自転車でアクセスすることで駐車場混雑問題も解決するでしょう。電車で行って、駅から登山口を自転車で目指しても良いですね!
長い林道のアプローチも自転車があれば一気に時間短縮が可能です。
さらに日常のトレーニングとしてもとても有効で、生活の足として使用していくことで登山に適した体作りを行っていくことも可能です。

登山と自転車
登山者と自転車の組み合わせって、実は大変相性の良い組み合わせなんではないかと感じています。例えばお盆の時期の北アルプスに出かけようと考えた場合、アクセスに悩むことが多いと思います。
例えば車で行こうとした時、ハイシーズンの北アルプスの駐車場はどこも満車で、駐車場手前には連なる路上駐車。ますます交通の流れは悪くなるし、マナー的にも良くありません。また縦走を行おうと考えた場合、入山点に車を駐車してしまうと後々の回収に困ります。そうなるとバスの出ている駅近くに駐車する事になりますが、ここもまた満車だったりして困ります。
この様な時、自転車があると一気に問題解決!
遠くの駐車場に車を停め、そこから自転車でアクセスすることで駐車場問題の心配はなくなります。縦走する際も、下山する登山口に予め自転車を停め、入山する登山口まで車で移動すれば下山後の回収も可能です。
車に自転車を積むサイクルキャリアは、2~3台積めるものが一般的です。場合によっては下山する登山口に自転車を1台デポし、麓の駐車場に車を停め、そこからもう1台の自転車でアクセスするなどの作戦も可能となります。
長く続く林道のアプローチはつまらないものですが、これも自転車を活用することで一気に短縮が可能です。また沢登りなど、そもそも登山道のない登山を行うような場合には、それこそ駐車場が遠く離れていることも多々あり、入山点と下山点が異なることも多くあります。自転車を活用しない手はありません。
電車で山に行く方にとっても、駅から登山口までの移動を自転車にすることで、バスの時間やバス停位置に悩まされること無く登山を楽しめるようになります。
自転車をアクセスに取り入れることで、登山の可能性はさらに広がるでしょう!
どの様な自転車を選択すれば良いかと言えば、それは各自の好みで良いと思いますが、できれば電動アシストのついた自転車を利用する方が現実的だとは思います。
自転車の何が辛いって、そりゃとにかく登りが辛い。ある程度勾配のある坂道では、寧ろ歩いた方が早い場合もあるくらい失速します。体力的にも本当にハード。登山の前から疲れちゃうし、下山した後ならそれこそ車の回収に向かうモチベーションが上がりません…。
しかしこれを電動アシストにすると、かなりの急登でも全く辛くない!楽々進むことができます♪
車への積載を考えると折りたたみタイプが手軽ですが、できればスポーツタイプを推奨します。ロードバイクで時速30km、クロスバイクで時速25km、マウンテンバイクで時速20km程度で走る事ができます。これが折りたたみ自転車やママチャリタイプでは時速15km程度とかなりゆっくり。スポーツモデルの方が現実的なスピードで移動できます。
片道の移動距離30kmを超えるような場合にはロードバイクが楽です。八ヶ岳全縦走でも、表銀座縦走でも行えるでしょう。
林道のアプローチを伴う場合にはMTBが良いでしょう。かなりの悪路でも問題無く走れ、下山もサスペンションと強力なブレーキのおかげで安心です。
その中間をとったようなクロスバイクであれば、ある程度の距離もこなせるし、ある程度の荒れた道でも安全に走れます。中途半端といえば中途半端ですが、日常の足としても使うなら一番現実的な選択かもしれません。
これら全ての車種で電動アシストが存在します。この様な電動アシストタイプのスポーツバイクを E-BIKE と言い、現在ヨーロッパでは大変な人気だったりします。日本の法律では強烈にアシストしてくれるのは時速10kmまでで、それ以降は徐々にアシスト力が弱くなり、時速24kmで完全にアシストが切れます。
しかし自転車でシンドイのは出足の加速と登坂なので、そこをしっかりとアシストしてくれればすごく楽な乗り物になります。
それでも時速24kmを超えるとアシストは止まり、そこから先の走行は自転車のポテンシャル次第になります。仮に時速25kmで走ろうとした時、ママチャリとロードバイクのどちらが楽かは言うまでもありません。

E-BIKE
は高性能な自転車に電動アシストを組み合わせているので、大変高価である欠点があります。実際に乗り始めてみればその価格にも納得の圧倒的ポテンシャルを秘めているのですが、購入に至るまでにはきっと悩むと思います。
だって安いものでも20万円。高価なものでは60万円以上します。本格的に自転車の趣味の方から見るとむしろかなり頑張った値段設定らしいのですが、それでも自転車にその価格はなかなか萎えます。
個人的に愛用している YAMAHA の YPJ-XC も、プロパー価格で35万円とかなりの金額。購入に至るまで2年も悩み、購入する瞬間もかなりビビりました ^^;
しかし実際に手元に来て乗ってみると、もっと早く買っていれば良かったと後悔するほどに良い買い物でした。スクーター買うよりずっと良いかも?
普通の自転車の様な登坂の辛さはなく、言うならばどこでも平地感覚。急な登坂であればあるほどむしろ楽しく感じたりしますw
こうなると、日常の足としても大いに活躍してくれます。当たり前の話ですが、車で移動したり電車に乗ったりすることに比べれば圧倒的に経済的!
辛いと感じるほどの運動強度ではないので、半径15km程度までの距離であれば問題無く生活の足として活用できます。
この " 辛いと感じるほどの運動強度ではない " と言うのが大きなポイントで、登山のトレーニングとしてとても優れていると感じています。
登山では体の中でも特に大きな大腿四頭筋を使いながら行動するので、多くのカロリーを消費します。このカロリー消費は、可能な限り体脂肪から燃焼させないと血糖値が下がってエネルギーの枯渇が起きます。この為に登山では心拍数を130前後に抑えながら行動すべきですが、この時最大限体脂肪からエネルギー生産させるために日頃から脂質代謝型の体作りを行っておくことがとても大切です。
E-BIKE を日常の足として移動すると、息が切れないくらいのペースで走ることとなります。その時の心拍数を計測してみると、凡そ120~140と理想的な脂質代謝の運動強度。これを毎日続けていれば、最大で65%程度の消費エネルギーを体脂肪から生み出せるようになるとされています。
仮に10km程度の距離を往復すると、大体350kcal程度消費されており、この内170~230kcal程度は体脂肪から燃焼されるようになります。通勤などに使い、月に20日ほど続ければ、二ヶ月で1kg程度の体脂肪を減らせる計算となり、ダイエットにも適しています。6Mets程度と運動強度は低いので、毎日続ける事も問題なく可能です。
登山の際のアプローチにも使用でき、日常の足としても使用できる
E-BIKE。登山のトレーニングとしても優れ、さらにロードバイクやクロスバイクなら街中でのサイクリング、マウンテンバイクなら林道ツーリングなど、新たな遊びとしても活用できます。
もちろん電動アシストなんてなまっちょろいもんはいらんと言うストイックな方は、普通のスポーツバイクを買っても良いでしょうしね!(僕はこの10年ほどロード、MTBと乗り継ぎましたが、電動アシストに切り替えて考えが180°変わりましたよ!)
決して安い買い物ではありませんが、登山者と自転車の相性は良いと思うのです。
皆さんのより素晴らしいアウトドアライフのご参考にして頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
クライミングギアにプーリーを2つ

直接的に登攀に必要な装備ではないので、一般のクライマーで持っている人は案外少ないものですが、いざトラブルが起きた時にプーリーが無いととても困ります。
宙吊りになった人を引き上げる際にプーリーがないとほんと引き上げが困難だし、困難な壁の登攀の際に荷揚げを行うにも、プーリーがないとほんと重い。渡渉の際のチロリアンブリッジなんかにもあると便利ですね。
プーリーはたくさんあった方が効率的ですが、登攀に直接的に役立つ道具では無いのであまりたくさんは持ちたくないですよね(^_^;)
個人的には2つのプーリーを個人装備として持つのが良いかなと感じています。

クライミングギアにプーリーを2つ
登攀を伴う登山を行う際、クライミングギアにプーリーは含まれていますか?
セルフレスキューをしっかりと訓練されている方でも、プーリーを持っていない方もいらっしゃるのではないかと思います。直接的に登攀に必要となる道具ではないので、どうしても軽量化の対象にされてしまいがちだとは思います。
しかし実際の救助の際には、プーリーの有無でその効率は大きく変わります。
例えばカラビナで直接ロープを180°折り返した場合、プーリー効率は凡そ50%。抵抗が一切ない状態の半分までエネルーギーロスが発生することになり、例えば1/3の引き上げシステムを作っても計算上では175%の出力となります。この状態では70kgの人を引き上げるのに40kgもの力が必要になります。現実的には岩角接触などによりまず引き上げられません。(1/6システムなどにしてもその抵抗により効率は262.5%。複雑なシステムの割に二倍半程度の力しか出せません。)
ではプーリーを使った場合にはどうでしょう?
商品によってプーリー効率は大きく変わりますが、ボールベアリングが搭載されたプーリーであれば凡そ90%程度の効率になります。仮にこのシステムで全ての屈折箇所をプーリーにした場合、1/3システムで271%の出力。1/6システムであれば515%の出力になります。圧倒的なエネルギー効率の差です。

ではどのくらいの個数を用意すれば良いでしょう?
個人的には、各自が2つのプーリーを持つことが理想だと考えています。例えば2人でコンティニュアスビレイで行動中にパートナーが落ちて負傷したとします。自力で登り返しが行えない場合、レイジングシステム(倍力システム)を組んで引き上げを行う必要があります。
この場合、要救助者まで余ったロープを下ろせるのであれば1/6システム、ロープのあまりがない場合には1/3システムでの引き上げとなります。1/3システムの場合には最低2つ、1/6システムの場合には最低3つのプーリーが必要となります。
救助者、要救助者のそれぞれがプーリーを携行していれば、このどちらのシステムでの対応できます。

.
レイジングを組んでホーリングシステム(引き上げシステム)を構築する場合、システムの一部にセルフジャミングシステムが取り入れられる必要があります。
セルフジャミングシステムとは一方向にしかロープが流れないシステムのことを言います。これを組んでおかないと、せっかく引き上げても手を離した瞬間に落ちてしまいます。
セルフジャミングシステムを構築する上で一番手間が少ない方法がセルフジャミングプーリーを取り入れること。各社からアッセンダーを搭載したセルフジャミングプーリーが販売されており、アッセンダーとしても使用することができます。
クライミングを行う際にはアッセンダーも携行すべき装備なので、セルフジャミングプーリーは一石二鳥となる道具と言えるでしょう。2つ持つプーリーの内、ひとつはセルフジャミングプーリーにしておくと良いでしょう。
もちろんプーリーとフリクションコードの組み合わせでも問題はありません。セットに時間がかかったり、フリクションコードの抵抗分僅かに引き上げが不利になったり、コードのあまり分の戻りが発生する効率の悪さはありますが、万が一限界まで引ききってからのリリースが必要なミスを犯してしまっても、最悪の場合フリクションコードを切れば解除できます。
またコードの戻り分のリリースが起きるので、本当の意味でパツパツまで張り込んでしまうミスは起こりにくい特徴もあります。(セルフジャミングプーリーの場合、少しロープを引いてアッセンダーからテンションを抜かないとジャミングを解除できない。)
当然セルフジャミングプーリーを用意するよりもコストもかかりません。
プーリーとフリクションコードの組み合わせで持つのも一つの選択肢でしょう。

当たり前の話ですが、セルフレスキューは適切な指導を受けた上で充分なトレーニングを積み重ねる必要があります。
クライマーはもちろんロープを使った登山を行う以上必ず宙吊りのリスクが伴います。せっかくロープにより大滑落を防ぐことができても、引き上げることができなければ本当の意味での危機は脱せません。(事故脱出できることがまずは優先されます。)
アルパインクライミングやマルチピッチクライミング、バリエーションルート、雪山登山などを楽しむすべての人が身につけるべき技術です。
山岳会などの組織に属さない方の場合はどうしても身につける機会がなかなか無かったりしますが、しっかりと学習しないと危ない目に遭うかもですよ!
是非学習機会を設け、しっかりと練習を繰り返しておきましょう。
その上で、装備を整えておくこともやっぱり重要です。プーリーを装備に加えていない人はちょっと検討してみましょう。
皆様の安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪
おすすめの講習カリキュラム

セルフレスキュー技術講習
山岳遭難事故は万が一ではなく、もっとずっと高い確率で発生します。もし仲間が目の前で事故を起こした時、自分たちで助け出さなくてはならない場合もあります。
この講習ではセルフレスキューを行って良いかどうかの判断と、救助方法、実際に救助の流れを行うロールプレイングを通じて活きた技術を習得します。
料金:12,000円(税別) 対象:登山初心者~
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
セルフビレイはダイナミックロープで!

セルフビレイを行った状態で墜落すると、とても大きな落下係数が発生してしまう場合があります。例え墜落距離が短かったとしても、落下係数が大きいと墜落衝撃も大きなものとなります。もしセルフビレイをとっているランヤードが伸びない素材だった場合、腰に重篤なダメージを及ぼす危険性があります。
そこでダイナミックロープを採用したランヤードシステムを使うことで、ロープが墜落衝撃を大きく吸収してくれます。安全度はかなり高くなります。
ロープを切って自作しても構いませんが、専用の道具を使うことで利便性も高まります。ペツルのデュアルコネクトアジャスター、とても便利です!!
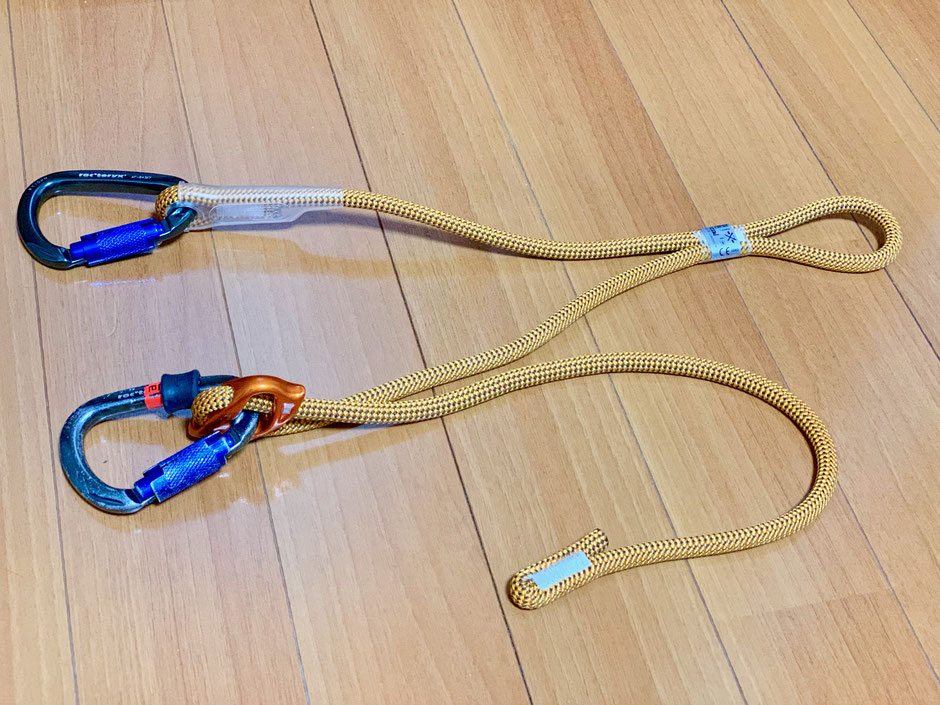
セルフビレイはダイナミックロープで!
セルフビレイをとるランヤードシステムに何を使っていますか?
登山の世界では、スリングやPASなど、伸びないウェビングテープを使用したランヤードシステムを使用している場合がほとんどだと思います。僕自信も最近までそうでした。
しかし高所作業の世界ではアブソーバー付きのランヤードシステムの採用が法律で義務付けられたりなど、安全に関する基準が厳しくなっています。この様な規制の裏には、必ず誰かの屍が転がっているものです。重篤な怪我や死亡を伴う事故がいくつも発生したからルールが変わったと考えるのが自然でしょう。
特殊高所技術協会さんのカラビナ破断実験動画では、スリングをランヤードにした状態で落下係数2 の墜落を発生させた時のカラビナ破断強度を紹介しています。この動画ではマイナーアクシスでの墜落を起こした際に7.7kNの衝撃荷重で破断したことが示されていますが、実際にカラビナが破断しなかった場合にはもっと遥かに大きな衝撃が発生していたものとも考えられます。
そもそもセルフビレイをとったまま登ってはいけませんが、その際に伸びないランヤードを使用しているととても危険であることが分かります。
伸びないロープやスリングでの墜落の場合、衝撃吸収を考える必要がないので計算式はシンプルになります。
体重 × 落下距離(m) × 9.8 ÷ 100 = 衝撃荷重
例えば 120cm のスリングで、上記実験と同じく80kg/落下係数2 だった場合 80kg × 2.4m × 9.8 ÷ 100 = 18.816kN となります。
お、恐ろしい…。確実に死ねます…。 ( ※ 凡そ6kNで腰に深刻な怪我を負い、凡そ12kNで人は即死するとされています。)
仮に落下係数1 でも9.4kN、落下係数0.8 でも7.5kN。骨盤骨折や内臓破裂などの怪我を負う可能性も高いでしょう。
ではこれをダイナミックロープで行っていた場合はどうでしょう?
ペツルのコネクトアジャストと言うダイナミックロープを使用した状態での、墜落実験データをペツルが公開しています。これによると、調整式アームを採用している側での落下係数2 の墜落で6.2kN、調整アームが無い側で8.9kNとされています。これは大きな怪我をする可能性があるが、即死するエネルギーでは無いことが示されています。
実際には落下係数1 程度までの墜落がほとんどでしょうから、4.5kN程度(アームは4kN以上滑らないことが規格で定められている)の衝撃荷重程度に留まります。決して小さな数字ではありませんが、怪我をする可能性は低いでしょう。
.
究極を言えば高所作業と同じ用にアブソーバーシステムを組み入れたランヤードにすべきでしょうが、クライミングではそこまで大きな落下係数が発生する状況は考えにくいものです。重量などを考慮すると、ダイナミックロープを使用したシステムが現実的でしょう。
個人的にはペツルのデュアルコネクトアジャストと言うランヤードシステムを採用しています。
セルフビレイの長さを自由に変えられたり、フィックスロープの架替え、バックアップを設けた懸垂下降のシステム構築などにも便利です。
クライミングや登山の世界では、伸びないランヤードシステムによるセルフビレイを行うことがまだまだ一般的です。
それで致命的な怪我を負った事例はあまり報告されていない事からも、実際にはそこまで大きな問題では無いのかも知れません。常識的に考えれば、セルフビレイをとっているその場所から自由落下が起こることが殆どないのでしょう。
しかし想像できる事故はいつか必ず起こるものです。特にクライミングで壁のど真ん中にいる状況で何かしらの作業を行うような場合や、足元が切り立った岩壁の鎖などに対しては自由落下も充分に考えられます。
必ずしも既製品である必要はないと思います。
例えばロープの両末端を2.5m程度切って、末端にダブルフィッシャーマンズノットで安全環付きカラビナを固定し、反対末端をエイトノットでハーネスに繋ぐ。これを2本用意すれば、鎖場での架替えなどでも役立つでしょう。
ロープを切って作った場合も、落下係数1 での衝撃荷重で4.5kN程度までに収まると考えられます。
安全を重視したい方は、是非ダイナミックロープによるランヤードシステムをご用意頂くことを推奨します。
ご参考にして頂ければ幸いです♪
おすすめの講習カリキュラム

単独行登山者安全確保技術講習
単独行登山者の死亡事故者・行方不明者が多い最大の理由は、滑落事故が起きたときに救助が遅れる事が最大の理由です。そもそも転滑落を起こさないことが大切です。
この講習では、単独行登山者が危険箇所で安全確保を行うための技術を指導しています。いつも先導するリーダーにも学習頂きたい内容です。
料金:12,000円(税別) 対象:登山初心者~
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
アルパインクライミングにグリグリ?

ペツルの誇るブレーキアシスト機能付きビレイデバイス、グリグリ。
スポーツクライミングの世界ではとてもメジャーな商品で、正しく使えば安全度が極めて高い確保を行えます。なんせブレーキアシスト機能付き。末端を握ってさえいれば、ぼーっとしてても確実に確保できます!
スポーツクライミング用に開発されているので、アルパインクライミングでは不向きと考えられていました。しかし、今、山岳ガイドや登山インストラクター、山岳救助隊員など、多くの職業登山者がフィールドに持ち出しています。
使いこなせれば、実は素晴らしく使いやすい道具だったりするんです。

アルパインクライミングにグリグリ?
ペツルが誇る銘ビレイデバイスのグリグリは、ボビン回転型の自動ブレーキアシスト機能が搭載された安全度の高いビレイデバイスです。末端さえ握っていればクライマーの墜落を感知して自動でブレーキが作動してくれるので、初心者ビレイヤーでも安心して任せられます。
スポーツクライミング用として開発されているのでロープを通す穴は1つ。使用ロープ径もシングルロープに合わせたサイズ設定で、アルパインクライミングには不向きと考えられてきました。
しかし近年、モデルチェンジにより風向きが変わってきました。最新のグリグリ3(2019年現行型で、国内販売名は"グリグリ")では、その重量も175gまで軽量化。230gあった初代ではちょっと重すぎるかなといった印象でしたが、現行型ではかなり現実的な重量となってきました。
また使用ロープ径も初代では10mm以上と限られていましたが、現行では8.5mm以上とかなり幅広くなりました。シングルロープであればほぼ全て対応可能ですし、太めのものであればハーフロープでも使用できます。(ロープは1本しか使えないので、フォロービレイ用としての使い方になります。)
これらの進化により、最近ではプロの職業登山者を中心にフィールドで活用する人も増えてきています。何故って何かと便利なんですよ♪

ロープのセット方向に注意!カラビナホール側にクライマー側のロープを通します。

ボビンが回転してロープが挟み込まれ、自動的にロープをロックします。
使うフィールドにもよりますが、日本のアルパインクライミングは樹木の多い森林限界以下で行われる事が多いと思います。この様な状況下では、ハーフロープシステムの利点が活かせません。現実的にはシングルロープでの登攀を行わざるを得ない場合も多いと思います。またこの様なシュチュエーションにおいては、丈夫な灌木にスリングで支点をとれる場合も多く、プロテクションに対する衝撃はある程度許容できるでしょう。
その一方でクライマーの動きをビレイヤーが視界に捉えにくかったり、ドラッグが起きている流れの悪いロープでのフォロービレイに苦労することが多くあります。
グリグリを使うと、仮に視界から外れた先で墜落が起きても安心だし、何よりもフォロービレイがかなり楽!
ほんとこれが大きい!ダイレクトビレイの動きがめちゃくちゃ軽くて、引きの労力がものすごく軽減されます!!

その他にも引き上げシステムの中にリリース機能を設ける際、グリグリを使用すると抵抗が比較的小さいという利点もあります。
例えばカラビナの効率は48%、ストップやリグで26%程度であると言うデータがあります。グリグリならこの効率が42%と、カラビナ折り返しより少し抵抗が大きい程度ですみます。
もちろん専用器具でもっと効率が良い道具も存在しますが、登山用に持っていく器具としては現実的でない重量となります。この点においてグリグリはかなり優秀です。

.
またブレーキアシスト機能により懸垂下降中の途中停止が簡単だったり、懸垂下降途中からの登り返しも実にスムーズに行える利点も大きな魅力です。
グリグリのすぐ上にアッセンダーを取り付け、そこにスリングでアブミを作ります。あとはアブミを上げたらそこに立ち上がりつつ、グリグリから出ている末端側のロープを引き上げるだけ。
スムーズなフォロービレイの動きがここでも活かされ、他の汎ゆるシステムの中でも群を抜いて楽に登り返せます。
このシステムの手返しの良さも魅力で、懸垂下降と登り返しを何度も繰り返すシーンでは本当に役立ちます。
クライミングルートのクリーニング、クライミングジムのルートセット、レスキューのサポート。一般的な登山者にとっての利点では無いかもしれませんが、プロが選択する理由はこのあたりにもあります。
もちろん利点ばかりではありません。ロープ1本しか使えないので、懸垂下降を行う時には少し面倒なシステムを構築する必要があります。
ロープの末端をエイトノットで結び、その環とロープをラッペルリングやマイロンリングなどで接続します。そのリングにロープ回収用の引き綱を接続し、懸垂下降終了後に回収する手間などがあります。
単発の懸垂下降などではあまり手間も変わりませんが、連続した懸垂下降などでは作業効率が悪くなります。
またロープ1本での懸垂下降となるのでロープの伸び率もより大きくなり、安定した懸垂下降が行いにくくなる欠点があります。
この辺りはグリグリを選択することの大きなマイナス要素の1つとなるでしょう。

.
また墜落衝撃の大きさもマイナス要素の1つです。墜落と同時にロックがかかるグリグリは、ブレーキアシストの無いビレイデバイスに比べてロープが流れません。これはすなわち墜落衝撃が一気に支点にかかると言う意味でもあります。
支点強度が充分なゲレンデやジムではむしろグランドフォールのリスクが少なくなり良いのですが、中間支点がプアな場所での確保には適しません。緩んだ氷、雪上での確保、ボロボロの岩の登攀など、少しでも墜落衝撃を小さくしたい時にグリグリを使用するのはリスクです。
これらの問題を一挙に解決する選択肢に、サブデバイスとしてエイト環を持参する手があります!

エイト環はATCなどのチューブ型デバイスに取って代わられた古い道具ではありますが、実は利点も多くあり、山岳救助の現場などでは未だに根強く使用されている道具でもあります。
そもそもエイト環からATCなどのチューブ型デバイスに取って代わられた最大の理由は制動力の低さにあるのですが、急に止められないということは支点に対する衝撃を緩和できるということでもあります。これはプアな支点しかとれない場所において大きな利点です。また懸垂下降の際にロープの太さが違っても、ロープ同士の摩擦によりロープが流れるスピードの差が生まれにくい事も良い点でしょう。グリグリのマイナス要素をカバーする意味でも、エイト環はとても有効です。

.
これに合わせてベアールのバックアップラインと言う、まさにシングルロープでの懸垂下降の為に作られたような軽量なロープがあります。5mmの太さで13.5kNの強度を持ち、懸垂下降の対としての役割はもちろん、とても長い支点構築用ロープとしても使えます。それでいて21g/mと軽量なので、携行に不便しません。
例えば沢登りやアイスクライミングなどでは、滝の中央付近にラインを取りたい場合もあると思います。その様な場合でも両岸の木からめちゃくちゃ長い固定分散支点を作ることで、滝のど真ん中にマスターポイントを作ることもできます。
これはめちゃくちゃ便利です!
懸垂下降の際にも、ロープの長さと同じ長さのバックアップラインを用意することで、シングルロープでもロープの長さ分の懸垂下降が行えることになります。
シングルロープでアルパインクライミングを行うと、ロープのドラッグ現象が問題となります。
そもそも木が生えた壁の登攀を行う場合には、屈折は避けられないのですが、木で屈折した場合にはカラビナで屈折した場合より遥かに大きな摩擦が発生し、墜落時にロープの伸びを有効に活用できないことが懸念されます。
また一般的なマルチピッチクライミングなどにおける屈折とは比較にならないほど大きな屈折が発生します。この様な場所にはカラビナで木の干渉を逃がすだけでは不十分な場合があります。
これはシングルロープでのアルパインクライミングに限った話ではありませんが、木の生えた壁の登攀を伴う場合にはプーリーカラビナと長いスリングも容易すべきでしょう。
それについて詳しくはスリングの選択と使い方をご覧下さい。

.
アルパインクライミングでグリグリを使用する際には様々な工夫が必要となりますが、実際に使ってみると便利な点が多いものです。入門者向けではありませんが、システムを充分に理解できる人であれば選択を視野に入れてみても良いでしょう。
多くのプロフェッショナルが現場で使う道具には、やはりそれなりに意味があります。
ひとつの選択肢として、検討してみては如何でしょうか?
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
スリングの選択と使い方

クライミングや登山に使うスリングについて考えてみたことはありますか?
様々な太さや長さのスリングがありますが、実は素材も違います。そしてその素材別に特性も変わってきます。
水に濡れると弱くなる素材、僅かな熱で溶けてしまう素材、結ぶと強度が下がる素材など、素材別の弱点を知らなければ危険な場合もあります。また適したシーンで適した素材を選べば、安全度は最大限に高まります!
スリングはどれでも一緒ではありません。しっかりと考え、それぞれの状況にあった素材や長さの選択を行っていくことが大切です。

スリングの選択と使い方
スリングには様々な素材があり、その素材ごとの特性を充分に理解している必要があります。また長さも様々なものがあり、使用目的によって使いやすい長さもまた異なります。自分が行う山行スタイルを良く考え、適した選択を行いましょう。
まず素材ですが、主にナイロン、ダイニーマ、ケブラーの3種類が使用されます。(素材別の特性に関してはクライミングにおける支点と素材の科学に詳しく記載しています。)
素材特性として、例えばナイロンであれば結びによる強度低下率が他の素材より低く、また結びを作ることでショックアブソーバー(衝撃吸収)効果が期待できると言う、他の素材には無い大きな利点があります。
しかし一方で水を含んで重くなりやすい、岩角断裂耐性が著しく低いなどの欠点もあります。これらの特性から、支点構築に優れた素材である事が分かります。
ダイニーマの場合には、水をまったく含まない、素材の破断強度が高いので軽量コンパクトになる、ナイロンよりもずっと高い岩角断裂耐性があるなどの利点があります。
その反面、熱に極端に弱いという大きな欠点もあります。この為、フリクションヒッチでの使用は極めて危険です。たくさんスリングを持っていかなくてはならない中間支点用に使用するのが適しています。
ケブラーは圧倒的な耐熱性と岩角断裂耐性をもっていますが、結びによる強度低下率が著しいと言う弱点も持っています。
フリクションヒッチでの使用に適していたり、岩角接触箇所における中間支点設置や残置ハーケンに対する直かけでの中間支点設置、懸垂下降の捨て縄などに適しています。石灰岩などに直接スリングを使用する場合など、他に選択肢はないでしょう。
この様に、素材特性を良く考えた上で、低在適所使い分ける必要があります。
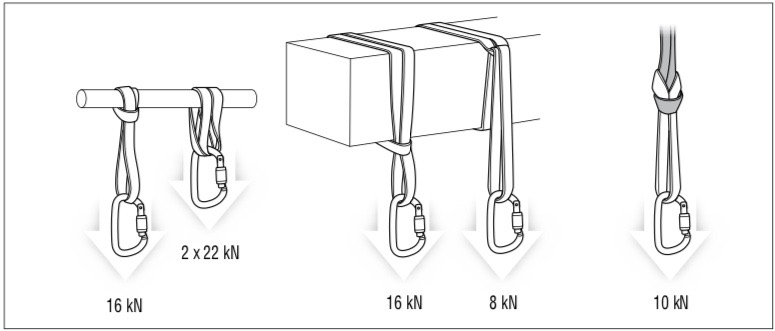
また結びによる強度低下率にも差があります。例えばスリングにオーバーハンドノットで結びを作った場合、ナイロンで凡そ13kN、ダイニーマで凡そ11kN、ケブラーでは凡そ7.5kNまで強度低下が考えられます。(上のイラストはナイロンにおける強度低下率です。)
これを考えると、ケブラースリングの途中に結び目を作ることはナンセンスだし、ダイニーマでもできれば避けたほうが無難であることが分かります。
またガースヒッチの折返し角度によっても、強度が2倍も変わることが分かります。イラスト中央左側の様な形になるよう、中間支点設置時には注意が必要です。また登り始め直後やランナウトする可能性が高い直前の支点には、可能な限りツーバイトかラウンドターンによる中間支点設置を行うべきでしょう。

.
写真の様にラウンドターンを行う場合には、長いスリングが必要です。この写真の木は凡そ脹脛くらいの太さで、使用しているスリングは240cmのスリングです。
240cmのスリングって一見長過ぎる様にも感じますが、このくらいの太さの木にラウンドターンした際のランニング距離は90cm程度。これでちょうど良いくらいです。
180cm~240cmくらいの長いスリングも何本かあると便利です。
ラウンドターンやツーバイトにする場合、カラビナのマイナーアクシスにも充分な注意が必要です。
カラビナ内部に3方から引かれる力が発生するので、マイナーアクシスにとてもなりやすい傾向になります。クローブヒッチで固定するなどして、カラビナの反転を防ぎましょう。
この為にも、やはり充分な長さが必要です。
ではガースヒッチによる中間支点設置が必ずしも悪かと言えば、状況によってはそうとも限りません。例えば親指程度の太さの灌木にしか支点を取れなかった場合、そもそもその木に10kNを超える支点強度などあるのでしょうか?
ガースヒッチでのスリング強度よりアンカーの強度が低い場合、ガースヒッチで結ぶこと事態に問題はありません。
また大きな墜落衝撃は落下係数が高い登攀直後にしか発生せず、中盤以降は支点にかかる衝撃は4~6kN程度に留まります。10kNも支点強度が出ていれば十分耐えられます。むしろドラッグ現象によりロープの衝撃緩和が十分に成されないことの方が問題なので、ランニングを充分に出せるガースヒッチの方がリスクが低くできる可能性だって考えられます。
ケブラースリングの考え方も同じで、確かに結びによる強度低下率は著しいものがありますが、リングにして使えば充分な破断強度が出せます。(オーバーハンドノットでの接続で15kN、ダブルフィッシャーマンズベンドでの接続で20kN)
岩角に直接接触する箇所や残置ハーケンに直接スリングを通さざるを得ない場合などにおいては、他の素材を使うより圧倒的有利です。
これから行う山行において、どんな素材のスリングを何に使うのか?
持っていく長さや本数はどの程度にするのか?
適切な知識を持ち、いくつかの種類のスリングを用意し、事前によく考えて持っていく道具を選び、その場その場での使用方法の最適解を考えて設置する。常に考え続けることが安全なクライミングへと繋がっていくでしょう。
ご参考にして頂ければ幸いです。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
ダウンミトンのすすめ

オーバーグローブの予備には、ダウンミトンがおすすめ!
万が一オーバーグローブが使えなくなった際の予備にももちろん、手先が冷える寒さの中で保温力を大幅に高めることができるのも魅力です。メイングローブとしては操作性にかけるダウンミトンも、使い方を考えればとても役立つ魅力的な道具となります。
さらに一つのアイデアとして、ダウンミトンを足に履き、テントシューズの代わりとして使うというものがあります。一つの道具を複数の目的に使う事で、山の装備はより軽くする事ができます。

.
.
2つ目の冬季手袋にはダウンミトンだ!
冬に登山を行う場合、手袋の換えは必須です。インナーグローブを2~3セット持っていくことは常識とされています。
オーバーグローブもまた、できれば予備を持つべきでしょう。風に飛ばされたり、ビショビショに水没することもあります。
先日別の記事 ( 雪山登山の手袋はこれがおすすめ!)
でもお伝えしていますが、冬季登山における手袋は未脱脂のウールインナーと中綿の入っていないペラペラインナーの組み合わせが結局一番使いやすく思います。
慣れればそこそこ細かい作業も手袋をしたままできるようになるし、保温力もそこそこ高い。そして多少濡れても冷たさを感じさせず、保温層であるウールインナーだけを懐で簡単に乾かすことができる優れた組み合わせです。

.
しかしこの組み合わせにおける保温力は特段に高いわけでなく、時に寒さを感じることも無いわけではありません。
爆風の稜線上を歩いている時や、アルパインクライミングやアイスクライミングにおける長時間のビレイ中には手が冷え切ってしまう事もあります。
動いている最中に寒さを感じる事はほぼありませんが、極端な寒さの中や動いていない時には手の冷たさを感じることもあります。
この様な場合に備え、予備のオーバーグローブにはダウンミトンを選択することを推奨しています。
愛用しているヘリテイジのエクスペディションダウンミトンは、収納時には軽く、小さくなってくれる手袋ですが、その保温力は絶大!
極寒状況下においてもまず寒さを感じる事はありません。
基本的にはウールインナーとペラペラオーバーグローブの組み合わせで行動し、殆ど全ての場所はこれだけでこなせます。
でも太陽の光が射していない日で且つ風が強い日の稜線などでは、体感気温は極端に下がります。動いている以上体幹部はさほど冷えませんが、四肢、特に手の指先はとても冷えやすく、凍傷リスクが高くなります。
この様な場合には、事前にペラペラオーバーグローブからダウンミトンに切り替えましょう。その際に、細かい作業が求められる靴紐の結び直しや行動食摂取などは全て済ませておきます。そうすれば、一般的な雪山縦走登山中に細かい作業が求められることはそれほど多くありません。とても快適にダウンミトンで行動できるでしょう。
アルパインクライミングやアイスクライミングのルートにおける長時間ビレイでは、動かない時間の長さからやはり手が冷えてしまいます。縦走登山と違い、クライミングではロープやギヤ類の細かな作業が求められますので、ずっとダウンミトンのみで行動するのは無理があります。何度もグローブを交換しながら登ります。
ダウンミトンへの切り替えが求められる環境というのは、かなり寒い日です。曇っていて太陽光が射さなかったり、風が強かったり、極端に気温が低い日であったり。その様な日は動かないでいるとすぐに体も冷えてきます。つまり、" ある程度は衣類の保温力を上げても無駄に汗をかかない状況 " でもあります。
この様な状況下では登りはじめる前の取り付きでダウンミトンを取り出し、ジャケットの内側に入れておきます。この事により、ピッチを切る際にすぐにオーバーグローブをダウンミトンに切り替えられる上、ダウンミトン装着時には体で暖められてホカホカになっています。この際に外したオーバーグローブを懐に入れておくことで、湿ったオーバーグローブを乾かすことにも役立ちます。
予備にオーバーグローブは、インナーグローブと違って本当に緊急用の万が一のために用意するものとなります。
であるならば、せっかく持っていくのであれば環境によって切り替えられるものを用意したほうが、様々な状況に応じて手の保温力や操作性を切り替えることができ、より快適な登山を行えるようになるものです。
そしてさらに、オーバーグローブの予備をダウンミトンにすることによって、とても快適な使い方もできます。

僕は常々感じていましたが、テントシューズってなんか無駄な重量な気がしませんか?
ただ快適性のためだけに持っていく道具で、しかも寝る時以外はまるで役に立たない。行動中は完全にただの錘です。
しかしある時思いつきました♪
そうだ!ダウンミトンをテントシューズにしちゃえば良いではないか!!
愛用しているヘリテイジのダウンミトンはウィンドストッパーを採用しており、さらに手首の部分は雪が入らないようにドローコードで締め込めるようにもなっています。インナースパッツ付きのハードシェルパンツなどと組み合わせれば、短時間だったらこのまま雪の上に出ることもできます。
寝るときも足全体をダウンが多ていることになるので、とても快適です♪
僕の場合、VBL ( 雪山登山の足冷えにVBLと言う考え方 )を行っているので、一日歩き終えた足に手袋を履いちゃうってのがなんとなくちょっとアレですが…。まぁそのへんは山なんで割り切って行こうかなと(^_^;)
これを行うためには、少し大きめのダウンミトンである必要があります。
でもお店で直接履いてみちゃうのも、ちょっとマズそうなので、一応参考までに。僕の足は実測で26.5cmで、ヘリテイジのエクスペディションダウンミトンを履いた場合に若干の余裕があるかなと言った感じです。たぶん27.5cm~28cmくらいの方までならいけるんじゃないかと?
各社からも同じ様な商品が出ていますが、ヘリテイジのエクスペディションオーバーグローブの方には手首の絞り込みのテープが付けられており、これが踵の絞り込みとしても使えて便利です。たぶん足サイズが小さめな方でも、この絞りである程度調整できるのではないかと思います。
登山において、軽量化はとてもとても重要な技術となります。
軽量化を行うためには、いくつかのポイントがあります。
僕は以下のように考えています。
・必要なものはすべて持ち、不要なものは何一つ持たない。
・一つ一つの道具の重量を把握し、より軽量なものを選択する。
・いくつかの道具を組み合わせて、一つの道具として機能させる。
・保温に関しては妥協しない。
などがあります。
その中の1つに、" 一つの道具をいくつもの要素のに使う " と言う考え方があります。
荷物を軽量化する事は、体力の消耗を防ぎ、自分の弱さをカバーします。それはすなわち、登山における安全性を向上させるということにも繋がります。
ダウンミトンのアイデアは、数ある装備の一つに過ぎませんが、この様なアイデアを積み重ねていくことによって、登山の装備はもっと軽く、小さくなっていきます。
ひとつのヒントとして、皆さんの安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
エネルギー代謝と心拍コントロール

登山を行うと凄まじい勢いでエネルギー消費していきます。
例えば体重65kgの男性が6時間のハイキングを行うと、基礎代謝を含めた一日あたりの消費カロリーは5000kcalを超えます。同じ方が日常生活を送った場合には大凡2500kcal程度、フルマラソンの消費カロリーが2500kcal程度。すなわち、日帰りハイキング程度の軽い登山でも、フルマラソンと同程度のカロリー消費が起きています。
体は無理したエネルギー捻出を行うので、肉体疲労も大きくなります。この事は山のリスクにも繋がります。
疲れにくい運動の在り方を学べば、山はもっと楽しく登れるはずです!

エネルギー代謝と心拍コントロール
登山はイメージよりずっとエネルギー消費の激しい運動となります。例えば体重65kgの男性が6時間のハイキングを行った場合、基礎代謝を含めた一日あたりの総消費カロリーは5000kcalを超えます。
この方が日常生活で消失するエネルギーは大凡2500kcal、フルマラソンで消費するエネルギーが2500kcal。すなわちハイキングに出かけるということは、フルマラソンに匹敵するエネルギー消費が成されていることになります。
しかし実際には、日帰り登山はフルマラソンほど肉体的な疲労感はありません。体に対するダメージは、日帰りハイキングの方がずっと小さなものになります。
何故同じだけのエネルギーを使いながらも、こんなに体が受ける影響が違うのか?
ここに " もっと楽に山登りを行うヒント " が隠されています。

.
まずフルマラソンとの大きな違いに、絶対的な心拍数の違いがあります。
フルマラソンでは有酸素運動レベルの心拍数を維持するのが効率が良く、心拍数は145~165程度で保たれるはずです。一方で登山は長時間運動であり、且つ酸素が薄くなる環境で運動を行わなくてはならないので、心拍数は上げるべきではありません。
心拍数が高いと早くエネルギーを供給しなくてはならないので、生産スピードの早いエネルギー代謝が求められます。
糖はすぐにエネルギーに変えることができるので、まずは糖を中心としたエネルギー生産を行います。
無酸素運動ほどではありませんが、70%程度は糖代謝からのエネルギー供給が成される事となります。
フルマラソンでは、これが効率の良い運動リズムとなります。
しかし登山の場合、とても長い時間行動するので糖を中心としたエネルギー代謝ではすぐに糖が枯渇してしまいます。
糖は血液中の血糖と、筋組織内、肝臓内に貯蔵するグリコーゲンを併せ、大凡2000~2500kcal程度のエネルギーが蓄えられています。しかし登山において、これでは足りません。糖だけでは足りないので、糖の替わりにアミノ酸分解からもエネルギー生産を行います。これにより体中の筋組織が痩せていきます。
登山の様なエネルギー消費量が多くて、且つ長時間の運動を行うような場合、糖代謝型のエネルギー生産は適しません。
そこで脂肪をエネルギーに変える脂質代謝を行います。
人間はATP(アデノシン三リン酸)と言う物質を分解することでエネルギーを生み出しています。糖1gあたりから生み出されるATP生産量は20~30個程度ですが、脂肪1gから作られるATP生産量は100を超えます。
体重65kg、体脂肪率20%だった場合、単純計算で13kgの脂肪が蓄えられています。人間の体に糖からのエネルギーは2000~2500kcalしか生産できませんが、脂質からは90000kcal以上生み出せる計算になります。
では何故フルマラソンではここを有効活用できないかと言うと、脂質代謝を中心としたエネルギー代謝はゆっくりとしか行えないからです。糖がATPに切り替わる行程よりも遥かに複雑な行程を踏まなくてはならないので、脂質をエネルギーとする場合にはゆっくりとした運動であることが求められます。
その点登山はそもそも低酸素な環境下で運動を求められるので、ゆっくりとした動きで心拍数を高めない行動が求められます。
心拍数120~145程度が最も脂質代謝効率が良いとされており、ここを目指した行動を行うと血糖値を下げたり筋組織破壊を起こさずに行動を行える様になります。
そもそも登山中に足を止めなければならない行動の仕方をしているということは、心拍数が上がりすぎている証拠。心拍数を乱さず、脂質代謝効率の良い歩行を行えば休憩なんていりません。仮にゆっくり歩いても、休憩回数が極端に少なくなるので結果として時間的ロスは殆どないことが多いです。
もし登山中に息が切れたりする様であれば、それはオーバーペースであると言えます。息を乱さずにおしゃべりできるくらいのペースと昔から言われていますが、まさにそのくらいゆっくり歩くのが良いでしょう。
経験則からそれを導き出した昔の人はすごい!

そうは言ってもなかなかそのペースを掴むのは難しいもの…。
そこでおすすめなのがハートレートモニター付きの腕時計。心拍数をいつもモニタリングしながら登山を行えるので、自分の歩行ペースト心拍数の関係が掴みやすくなります。
アップルウォッチなどで一気に有名になった機能で、今や安いものでは5000円程度で買えます。個人的にはエプソンのパルセンス PS-600
と言う時計を使っており、心拍ゾーンの移行をバイブレーションで教えてくれます。いちいち時計を見なくても、ペースオーバーが判断できるのはありがたいものです。
はじめは極端にゆっくりに感じるかも知れませんが、明らかに疲労感が減るはず。結果として休憩をとる回数は明らかに減り、到着時間もあまり変わらなくなるはずです。
ゆっくりした行動を行うことで、糖代謝と脂質代謝の割合は、5:5 ~ 3:7 くらいになります。
どんなにゆっくり行動しても糖代謝を無くすことはできないので、行動食は糖を中心に摂取しましょう!
脂質の方がたくさんのカロリーがありますが、脂質を経口投与してもすぐにエネルギーにはなりません。特にエネルギー変換速度が早いとされている中鎖脂肪酸ですら、エネルギーに切り替わりはじめるのは早くても1時間後からで、エネルギーのピークに達するのは4時間後となります。
エネルギー補給のために朝食や夕食に脂質をとることは良いと思いますが、行動中に摂るべきエネルギー供給は糖を中心とすべきでしょう。
ゆっくり歩くのにストレスを感じる方は、自分自身が長時間高心拍に耐えられる強い肉体を持つ必要があります。
週に2回程度のインターバルトレーニング、週に2回程度のランニング(心拍160以上の高負荷)、最低でも月に2回、できれば週に1回程度の登山。これを繰り返せば僅かに心拍限界を高めることができます。
それでも心拍の許容は年齢に応じてしっかり下がってきますし、アスリートでも無ければそこまでたくさんのトレーニングはいらないと思います。
楽に、疲れない登山を行うためには、心拍数コントロールを行うテクニックを身に着けましょう。
それが結果として強さとなり、山の安全につながるはずです。
皆さんの安全登山の山行になれば幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
雪山の足冷えに、VBL(ベイパーバリアラップ)と言う考え方

寒冷地では、汗を衣服の外に全て出すことが困難です。内外温度差が大きい環境ではどうしても一番外側の生地のすぐ内側で結露が発生し、衣服の内側は徐々に湿気を帯びていきます。
水は空気より20倍以上も熱伝導率が高いので、衣服の保温層が濡れてしまうと外気により保温層内の空気は一気に冷やされ、保温力を急激に低下してしまいます。
そこで極地冒険などでは、VBL(ベイパーバリアラップ)と言う技法が使われます。
湿気を外部に漏らさないことで熱伝導率の低下を防ぎ、衣服の性能を最大限に活かす技術を登山にも取り入れています。

.
.
VBL(ベイパーバリアラップ)ってなんだ?
雪山登山やアイスクライミングなど、寒冷地における活動ではどうしても衣服の内外温度差が大きくなってしまいます。
内外温度差が大きければ必ず衣服の一番外側の生地の内側に結露が発生し、そこより外には湿気が出て行きにくくなります。こうなると衣服の内側の保温層は徐々に湿気を帯び、デッドエアスペースの水分量が増えていきます。
水は空気の20倍以上もの熱伝導率となるので、保温層が湿気を帯びると保温層内の空気は外気の冷たい温度が伝わり、一気に保温力を失うこととなります。
そこで極地冒険などでは、保温層の内側に湿気を通さない膜を設けることで水分を膜の内側に留め、膜の外側から保温層、一番外部の生地までの間を乾いた状態に保つ技術が使われます。これをVBL(ベイパーバリアラップ)と言います。
BVLは湿気を通さない膜でなければならず、つまりは空気も滞留しにくい膜であると言うことにもなります。
熱伝導には伝達熱以外にも、気化熱、放射熱、対流があります。水を通さない膜を設ける事で外気との伝達熱による急速的な温度低下や気化熱による熱消失は防げますが、その一方で体温からの熱の対流は膜で防がれ、膜より外に熱が伝わりにくくなってしまう欠点もあります。また皮膚から放たれる放射熱の一部も膜で跳ね返されるので、膜より外の保温層は膜がない状態より暖まりにくい状態になってしまいます。
また当然ですが膜より内側はとても蒸れます。膜があまりに皮膚から近いと、かなりの不快感を感じるでしょう。
これらの問題を解決するためには、皮膚 → 第一保温層 → VBL → 第二保温層 → 外被 の順で構成される必要があり、このバランスがとれるとこれまでと同等の保温力を保ちつつ、保温力の低下を起こさずに長時間活動ができる様になります。
では登山においてはどの様にVBLを活用することができるでしょうか?
例えば手袋に使おうとすると、薄手のインナー → 薄手のゴム手袋 → 保温層 → オーバーグローブ と言う組み合わせになります。これってあまりに操作性が下がってしまうので全然現実的ではありません。
体全体で見ると、アンダーウェア → ビニールカッパ → 化繊中綿ジャケット → ハードシェル みたいな構成となります。いやこれ、暑いだろ…。
しかし足だけは有効に使えるのではないかと考えていたりします。

積雪期登山を考えると、足だけはどうにも冷えやすいと感じます。もちろん保温力を狙ってダブルブーツにすれば(ダブルブーツの場合、そもそもVBLの技術が活用されていますが…。)圧倒的に暖かくなりますが、足首が固くなって歩きにくくなったりします。
長時間のラッセル、爆風の稜線、高所登山、厳寒地など、足の冷たさが極端な状況では仕方ありませんが、決して歩きやすい靴ではありません。
特に日本の山は急峻で、太平洋側に至っては降雪そのものが少なく、夏道と変わらない大きな段差も多くあります。この様な状況ではやはり足首の柔らかいシングルブーツが適しているように感じます。
一方でシングルブーツではどうしても結露の影響を避けられず、冬靴の中綿は徐々に湿気を帯びてしまいます。これにより停滞して体からの発熱量が低下すると、すぐに外気が足に伝わり足が冷えてしまう現象がおきます。
シングルタイプの冬靴でこそ、このVBLと言う技術が大きく活かされるのではないかと考えています。
足で使う場合、ネオプレーンの薄手のソックスを使うとやりやすいです。モンベルから沢登り用の薄手のものが発売されていたり、探せば Amazon でもけっこういろいろあったりします。だいたい 0,5mm 厚くらいが使いやすいかな?
これを直接足に履いてしまうと絶対的な保温力が低下する様な印象なので、僕の場合は中厚手程度のウールの靴下の上にネオプレーンソックスを履いてVBLとしています。
足からの熱と湿気をウールソックス層で留め、靴の中綿と外被で外気を遮断する。薄手のネオプレーンソックスは縫い目があるのでそこからの湿気の漏れは防げませんが、僅かな湿気であれば靴のゴアテックスが抜いてくれるかなと期待しています。外被の内外温度差もVBLにより小さくなるので、結露による濡れ戻りは最小限に防げます。
これによりテント泊の際にも靴が凍ってしまうトラブルが起きにくくなりますし、夜寝る時にネオプレーンソックスを脱いで裏返し、懐に入れて寝ればウールソックス、ネオプレーンソックス共に朝までに乾かせます。
この方法であればシングルブーツでも足の冷えはだいぶ起きにくくなり、連日の山行でも靴が湿っぽくなりません!

ただ、世の中に完璧なんてものは存在する訳もなく…。
この技法、足が臭くなるのですよ…。
正直気化熱が起こらないのだから化繊のソックスでもそう変わらないと思うのですが、化繊だと臭くなるのですよ…。
うーん。やはりグローブにしろ、ソックスにしろ、肌に触れる部分はウールが正義ですな(^_^;)
そんな感じでこの駄文を締めたいと思います。
ご参考にして頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
雪山登山の手袋はこれがおすすめ!

冬のグローブ選びは本当に迷走しました。
一番最初に先輩から " 冬はウールにペラペラオーバーグローブが最適らしい " と教えられ、それを使っていました。しかしそれは使い古されたカビの生えた技術だろうと、最先端マテリアルを使った様々なグローブをいろいろ試してみていました。
15年以上の歳月彷徨い続けた結果、ついにこの数年間は1つの答えに辿り着いたのです。
その答えは!? 結局ウールにオーバーグローブw
先輩の言うことは聞いといた方が良いのですなー。
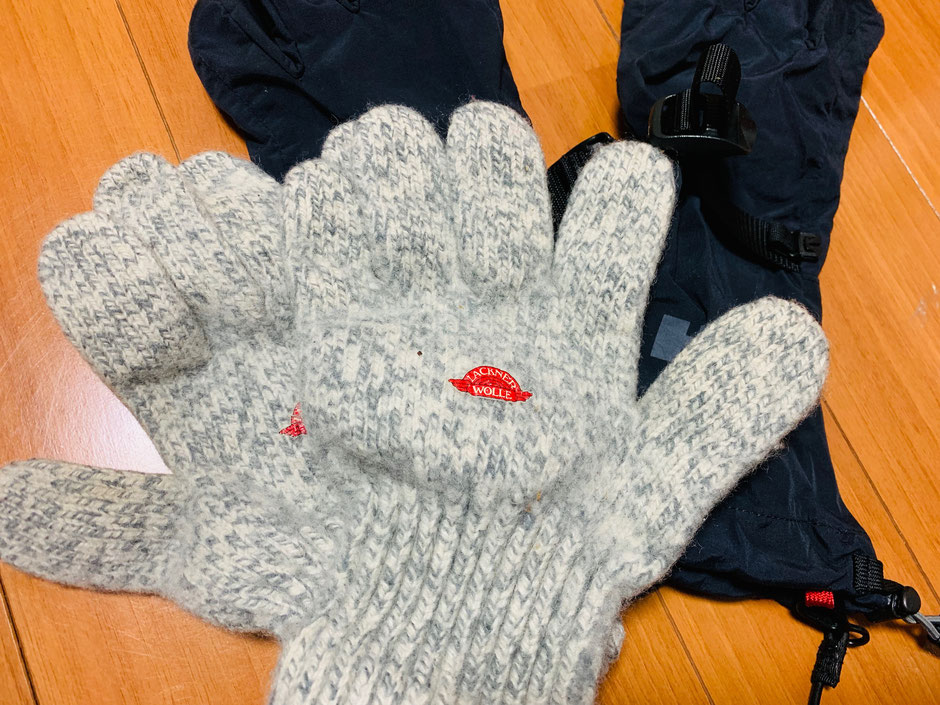
.
.
冬山のグローブは結局これがベストだ!
雪山登山に求められるグローブの選択はシビアです。
時に−20℃を下回ることもあり、乾いた日も、湿り雪の日もあり、その両方が一日のうちに交互する日だってある。濡れに強く、寒さに強いことが求められます。
一方でアイゼンの脱ぎ履きや、山行によってはロープの操作、支点などのシステム構築など、手先の繊細さも求められます。
この2つの条件は相反するものであり、保温力を求めれば分厚くなるし、手先の繊細さを求めれば保温力を下げざるを得ない。2つの条件を満たす絶妙な厚さが求められます。
その昔、初めて雪山登山をはじめる時に先輩から言われたのが " 冬グローブはウールにペラペラグローブが一番良いらしい "
とのことでした。それを信じて数年使ってみましたが、指先が冷たく感じることがあったり、いまいち細かい作業がやりにくかったり、なんかすごい中途半端な性能に感じていました。
" そうか、これは昔から言い伝えられている、もはやカビの生えた古い手法なんだ。きっと…。" などと生意気なことを思い、最先端マテリアルを使用したあらゆるグローブを使ってみました。
凡そ15年。使ってきたグローブはその年数よりも多い数を試してみたものです。まさに " 沼 " にはまり込みました(^_^;)
しかしようやくこの数年、1つの答えにたどり着きました!
それがこれ!ウールにペラペラオーバーグローブ!!結局これが一番良いっぽいww
先輩の言うことはちゃんと聞いとくものですねー。

ラックナーウールのヒマラヤングラブ。未脱脂のウールを使用した手袋で、雪が付着しにくい特性を持っています。湿っても保温力を失いにくいのはウールの大きな利点です。

ゴアウィンドストッパーを使用した、ヘリテイジのオーバーグローブ。中綿は入っていない、一枚生地のグローブで、指先の操作性に優れています。
ウールのグローブとペラペラオーバーグローブと言っても、各社様々な商品が出ています。これは好みで選べば良いとは思いますが、個人的にはラックナーのヒマラヤングラブと、ヘリテイジのオーバーグローブを愛用しています。
ウールは未脱脂のものが良いと思いますが、メーカーはどこが理想ってのも無いと思います。たぶん大きな差は無い。でも僕はこのラックナーのヒマラヤングラブを信頼しています。
ある日、ご参加者様と話しながら、よそ見した状態でバーナーの火を止めようとしてしまったんです。
でもなんかバルブが閉まらない?
手元を見ると、なんとゴトクを手で摘んでおり、ウールのグローブは思いっきり炎に包まれています!!!!!!!!!!
でも。。。
なんか髪の毛が燃えたようなくっさい匂いがするだけで、手は一切の暑さを感じる事はありませんでした。しかも手袋を洗ったら、焦げまで取れてどの手袋でそんなミスをやらかしたのか分からなくなってしまいました。
あわや大惨事になりかねないミスをしでかしましたが、ラックナーのヒマラヤングラブは熱を伝えませんでした。
この手袋で冷たさを感じる時は、だいたい手袋が湿ってきたとき。
氷を握っても雪の中に手を突っ込んでもほとんど冷たさは感じませんが、湿ってきちゃうとやっぱり熱伝導率は高まります。
こうなったら乾いたグローブに換えなくてはなりません。

そんな時は湿ったグローブを懐にしまい込んでおきましょう!
買えのグローブが再び湿ってしまうまでには懐のグローブが乾きます。これを繰り返してグローブの交換を行っていけば、雪山登山中に手が極端に冷たい思いをすることはなくなるでしょう。
グローブと外気の内外温度差が生じる以上、結露による濡れは避けようがありません。冷たいなと感じた時に無理はせず、なるべく早く交換することが大切です。濡れたグローブを懐で乾かすことができる点こそ、インナーグローブとオーバーグローブが別体式であることの最大の利点かもしれません。


オーバーグローブは商品によってけっこう違いがあります。
ナイロンだけで構成されたものや手のひらがゴートレザーなどの素材になっているものがあり、後者の方が明らかに耐久性が高いのですが、まぁ凍ります。
一方でナイロンだけのものにも種類があり、滑り止め加工がされているものとそうでないものがあります。これも前者ならアックスなどを握り込んでも滑りませんが、後者のほうがより凍結しにくい傾向にあります。
サイズの選択も重要です。
保温力を考えればゆったりめのサイズにした方がずっと温かいし、細かい作業をするのであればぴったりめサイズを選択すべきでしょう。例えば寒風に当てられやすい縦走登山ならば前者の方が良いし、細かい操作をするアルパインクライミングやアイスクライミングならば後者の方が扱いやすいでしょう。
この辺りは好みの問題もありますし、シーンによって使い分けても良いでしょう。
僕の場合、ちょっと手が小さめで通常はMサイズを使うことが多いです。ラックナーのヒマラヤングラブはMサイズを使っていますが、ヘリテイジのオーバーグローブはXSサイズを使っています。
ヘリテイジのグローブはかなりゆったりめに作られており、Mサイズではちょっと大きすぎます。普段使っているサイズより1サイズ下を選ぶと丁度良いかも?
僕は2サイズ下を選んでいますが、これはかなりぴったりサイズで、操作性を最優先させているためです。保温力はかなり犠牲になりますが、業務上一日にたくさんの支点を構築・回収するので、その作業の正確性とスピードを優先してこのサイズを選んでいます。
通常は1サイズ下。保温性を優先するなら通常選ぶサイズの選択で良いと思います。

少しゆったりめのグローブを選択した場合などは特にそうですが、オーバーグローブの流れ止めは用意しておいた方が良いかとは思います。
基本的に雪山登山ではオーバーグローブを可能な限り外すべきではありませんが、ゆったりめのオーバーグローブで作業性がスポイルされている場合、インナーグローブで作業せざるを得ない事もあるかと思います。またそうでなくても、インナーグローブの交換時などにはどうしてもオーバーグローブを外さざるをえません。
この様な時、うっかりオーバーグローブが飛ばされてしまうと致命的です!
凍傷リスクが高まってしまうので、オーバーグローブは紛失しないように気をつけましょう。
また万が一オーバーグローブを失った場合に備え、こちらも予備があった方が良いかと思います。
失うとは風に飛ばされるだけでなく、例えばアイスクライミング中に氷が割れて手袋をずぶ濡れにしてしまったり、温かい日の日本海側の山の水っぽい雪のラッセルで濡らしてしまう事もあるでしょう。この様な時はオーバーグローブの換えが欲しいものです。
そこでおすすめしたいのがダウンミトン。
アルパインクライミングなどのためにタイトめなオーバーグローブを使用している場合などにおいて、ビレイ時に手が冷える場合があります。この様な時にビレイ中のグローブとしてダウンミトンを使用すると、とても暖かく過ごすことができます。
また大きめのダウンミトンを選択しておけば、テントシューズの変わりに足に履くこともでき、就寝時も快適に過ごせます。
オーバーグローブの換えとして、ビレイグローブとして、テントシューズとして役立ちます。

雪山を始めた頃に中途半端で使えないと感じたウールインナーとペラペラオーバーグローブの組み合わせでしたが、その中途半端さこそがあらゆるシーンでオールマイティーに使える魅力でもあったんです。
冬のグローブの選択は、やっぱりこれが一番良いのかもですね。
皆さんのご参考にして頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
今、一番おすすめの登山用ヘッドライト " レッドレンザー MH10 "

登山を行う上で絶対に持たなくてはならない道具のひとつにヘッドライトがあります。ちょっとしたイレギュラーで日没を起こしてしまう事も多い登山では、夜を迎えてしまうと光なしでは行動ができなくなってしまいます。
登山用のヘッドライトは各社より本当に様々な種類が出ており、どれを選んだら良いか分からなくなります。
そんななか、ドイツのレッドレンザー社が凄いヘッドライトを出してきました!!
一年ほど前に販売が開始され、そのあまりの高性能っぷりに話題となったMH10。
ヘッドライトに求められる最低限の機能と最大限の性能を紹介します。

.
.
夜闇を切り裂く600ルーメンの光
ドイツの名門レッドレンザー社が凄いヘッドライトを開発しました!まさに登山にフォーカスした様なヘッドライトで、登山用ヘッドライトの中で今一番おすすめなヘッドライトは何だと問われれば、間違えなくこのMH10を推奨します。
登山に求められるヘッドライトの性能の中で、一番大切なのはまず明るさ。そしてバッテリー寿命と重量だと思います。
レッドレンザー社には2000ルーメンもの大光量を誇るXEO19Rと言うヘッドライトもあるのですが、こちらは500g近くも重量があるので現実的ではありません。予備のバッテリーも含めるととんでもない重量になります。
MH10はこの辺りのバランスが考えられており、600ルーメン / 158g と程よい感じの内容です。

.
いや、確かに2000ルーメンなんてとんでもない数字から比べると600ルーメンって数字は控えめに感じますが、これでも十分すぎるほど明るいんですよ!
ペツルやブラックダイヤモンドの高性能なヘッドライトが300ルーメン程度。その倍の数字は伊達じゃありません。
各社がヘッドライトの明るさを300ルーメン程度に抑えているのは、バッテリーの問題。当たり前な話ですが、明るくなればなるほどバッテリーの消耗は早まります。
そこで MH10 ではリチウムイオン電池の 18650 を採用。3.7v / 3700mAh もの大容量バッテリーを搭載。バッテリーが長持ちする iPhone 8 のバッテリー容量が 1821mAh
であることを考えると、その容量の大きさがわかるのではないでしょうか。
最近は周辺の明るさによって光の強さを調整してくれたり、無断階で光量を調整できたりなど高性能なヘッドライトが多い様ですが、このMH10は至ってシンプル。最大光量の600ルーメン(照射時間10時間)と調度良い光量の250ルーメン(照射時間15時間)、テントの中などで使いやすい10ルーメン(照射時間120時間)の3パターンのみ。
例えば通常は250ルーメンのミドルモードで行動します。250ルーメンと言うと一般的なヘッドライトの多くのモデルの最大出力に近い光の強さで、登山における光としては十分な光の強さとなります。その光量を15時間継続できるので、冬至に夜通し歩いても問題無い計算になります。
でも登山道以外の場所を歩いている時やトレイルランニングなどでは、一時的にもっと遠くを照らしてルートファインディングを行いたい場合もあります。
この様な使い方においては、250ルーメンだと少し心もとない感じもします。
そこで600ルーメンに切り替えると、それこそすごく遠くまで光が届き、これから進むべき先を示してくれます。
600ルーメンでも10時間もの照射時間なので、600ルーメンのまま行動しても多くの場合は問題無いでしょう。
さらに手元を照らすのに調度良い光量となる10ルーメンでは、なんと120時間もの照射時間に! これならば5日間くらいブリザードが続いて雪洞に閉じ込められても大丈夫ですね ♪ (絶対に嫌だっ!!)

.
レッドレンザーの大きな特徴のひとつに、無段階調整式の集光調整機能があります。調整リングを回すだけで、広域照射からスポット照射を無断階で切り替えることができ、しかも光の暗明差が少ない綺麗な円形の光で照射してくれます。
通常歩いている時は広域照射で足元を広く照らし、遠くを確認したい時はスポット照射で光を遠くへ飛ばすなど自由自在!

.

.
完全に光のない真っ暗闇の中で撮影してみました。
広域照射では目の前の空間が広く明るく照らされ、とても歩きやすい環境を作ることができます。しかも均一な光で照射してくれるので、目が疲れることもありません。
一方でスポット照射に切り替えてみると、今度はとても遠くまではっきりと照らしてくれます。足元を照らすと明るすぎて眩しかったりしますが、ルートファインディングには心強い明るさです。
そしてもう一つ、このMH10のありがたい特徴のひとつに充電式である点も挙げられます!
MicroUSBでポータブルバッテリーなどから充電できるので、例えばテント泊登山などでヘッドライトの充電も行うことができます。しかも80%までの充電ならば空の状態から3時間程度で充電できるので便利です。
但しこのヘッドライトのバッテリーが3700mAhもあるので、ポータブルバッテリーもそれ相応の容量が必要ですね。スマートフォンの充電なども加味し、10000mAhくらいあった方が良いかな?

実にシンプルな機能と圧倒的な性能を誇るレッドレンザー社のMH10。まさにちょうど欲しかった光の強さと、過剰すぎないバッテリー持ち、重すぎない、大きすぎない、全てが調度良く収まった高性能ヘッドライトだと思います。
他社のフラッグシップモデルに比べても特別高いわけでも無いし、機能自体はシンプルでも構わないならばすごくオススメ!
現実的に必要な範囲での十分な明るさと、影のない均一な光の照射は、想像以上に行動しやすい環境を作ってくれます。
今からヘッドライトを買うならば、レッドレンザーMH10、良いヘッドライトですよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山に傘を使う。

登山の雨具でまず必要なのが高性能なレインウェアです。これは登山において絶対に必要な装備で、何があっても欠かしては行けない重要なギアです。
しかし高性能なレインウェアがあれば、それで快適に雨の中の山行を楽しめるでしょうか?
いいえ、そうではありません。
どんなに高性能なレインウェアでも、雨の中での山行で蒸れは絶対に起こります。特にレインウェアの表面が濡れてしまうと、かなり不快な状態になるでしょう。
傘は唯一蒸れない雨具です。併せて使うことですごく快適になるんですよ!

.
.
登山に傘を使う!?
登山を楽しむ上で雨との遭遇は避けられません。天気予報では晴れと言ってたのに、山の中だけは驚くほどの集中豪雨となることも珍しくはありません。風に乗った湿った温かい空気が山の斜面を駆け上がり、上空の冷たい寒気にぶつかればそこで結露が発生します。すなわち雨雲です。暖かい季節であればあるほど、不意に雨に遭遇することは多々あります。
日本の登山シーンにおいての雨は、うまく付き合っていかなければならない避けられない相手です。
登山においてまず持たなくてはならない雨具は高性能なレインウェアです。
尾根筋や稜線上では風が強いことも多く、雨は横殴りに降ってくることがあります。この様な場合、全方位からの雨にも見を守れるよう、透湿性能を持った高性能なレインウェアが求められます。またレインウェアは高い防風性能も備えており、強風下では風によって体温が奪われてしまうのを防ぐこともできます。
一方で、その完全なる密閉性が原因となり、どうしても内部が蒸れてしまいます。その蒸れを防ぐためにゴアテックスを代表とする防水透湿フィルムを採用したレインウェアが開発されていますが、それでも蒸れを100%解決することなどはできません。
特にレインウェアの表面が湿ってくると透湿性能は大きく低下し、レインウェアの中で汗濡れが発生し始めます。
かなり不快なだけでなく、濡れによる冷えも起こります。
レインウェアは必須の道具ですが、万能なわけではありません。

.
そこでおすすめなのが傘。
当たり前の話ではありますが、傘はあらゆる雨具の中で唯一蒸れない雨具です。
軽い雨ならば傘だけで対応できるし、少し強めの雨でもレインパンツとの併用で十分雨を防げます。
これで蒸れによる濡れからほぼ完全に解消されます!
レインジャケットを着る場合にも、生地表面があまり濡れないので、防水透湿フィルムの性能を最大限発揮してくれます。
どうしようもない大雨の中でも、レインウェアと傘の組み合わせで驚くほど快適に過ごせたりします。
また傘は太陽光を避ける日傘にもなり、夏の長い林道歩きやバス待ちでかなり快適に過ごせるようにもなります。
調理の際にバーナーの風よけとしても役立ちます。
先日、西丹沢で大雨に遭遇しました。普段は涸れ沢の登山道も、この日ばかりは美しいナメ床に変貌していました^^;
そんな雨の中でも、傘があったおかげでレインジャケットを着ずに過ごせ、とても快適な登山を楽しむことができました。
もちろん傘もまた万能ではありません。
風が強いときには使えませんし、登攀を伴うときにも使えません。森林限界を超えた稜線上では、使えるシーンも限られるでしょう。でもだからこそレインウェアとの併用が求められます。
傘があれば雨の日のテント場で、テントと山小屋の往復にレインウェアを着る必要性がなくなります。
長い夏の林道歩きを、涼しく快適に歩くことができます。
レインウェアとの併用で、蒸れずに快適な登山を楽しめます。
是非装備に傘も加えることを強く推奨します!特に雨の可能性がある日は絶対に持っていくことをおすすめしたいっ!!
登山用の傘にもいろいろなものがありますが、僕は長らくユーロシルム社のトレッキングアンブレラを愛用しています。
ユーロシルムの傘はグラスファイバー製の丈夫なフレームで、風が吹いてラッパ傘状態になっても壊れない特徴を持っています。
特にこれから買うならば、ハンズフリーモデルがおすすめ!
傘をバックパックに固定し、両手を離したまま傘を差す事ができます。樹林帯のヤブっぽいところでは傘を手に持った方が便利ですが、比較的開けた場所ではハンズフリーにして使えるほうが快適です。
また選ぶならばUVカット加工のされたシルバータイプ。真夏に日傘として使うことで、明らかに涼しく歩けます。言うならば、ずっと木陰を歩いてる感じ。直射日光の下で歩くのとでは全然違います。

1gでも軽く。それは登山の基本であり、あったら便利なものは可能な限り持たない様にすべきです。しかし一方で、安全に関わる道具は必ずすべて持つべきであり、絶対に欠かしてはいけません。
雨傘はその中間に位置する道具だと考えています。
傘があることで雨による濡れのリスクを大幅に低減でき、その事は体力低下を防ぐことにも繋がります。レインウェアを持つ上で絶対に持つべきかと問われればそうでは無いかも知れませんが、あることでリスクが下げられる道具であることは間違えありません。
この中間位置にある道具って結構あるもので、そこをどう捉えてどう判断するかが登山者としてのスタイルや在り方の差なのかなとも思います。
あなたの登山にもし傘の選択がマッチするならば、是非試してもらいたい!
きっと今よりももっと快適な登山を楽しめますよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
おすすめのビレイデバイス " EDELRID MEGA JUL " (エーデルリッド メガジュル)

ビレイデバイスはクライマーの命を守る最重要クライミングギアの1つです。
カラビナによるムンターヒッチの時代から、エイト環、ATCやルベルソなどの現代的なビレイデバイスを経て、最近ではブレーキアシスト機能のついたビレイデバイスも増えてきました。
グリグリなどに代表される自動補助ブレーキ機構付きビレイデバイスは大きく重いものが多かった印象ですが、近年では実にシンプルで軽量なビレイデバイスも一部ラインナップされてきています。
そんな中でも特におすすめなのが、エーデルリッドのメガジュルです。

.
.
安全性最優先の最新ビレイデバイス!
クライミングや高難度な登山においてビレイデバイスの選択はとても重要です。
パートナーの墜落を止めたり、懸垂下降を行なったり、ロープを登り返したりと多岐にわたって使用します。クライマーにとって、ビレイデバイスは最も身近な道具のひとつです。
一般的なビレイデバイスは、摩擦によって抵抗を増やす事で制動を行います。このためビレイを行う手がロープから離れてしまうと、クライマーは墜落してしまいます。
そのリスクを低減させるためにグリグリやシンチなどに代表されるブレーキアシスト機能付きのビレイデバイスが流通して少し経ちますが、スポーツクライマーを除いてはあまり流通していなかったりします。その最大の要因は重量の重さ、そしてシングルロープでしか使用できない点にあります。
ところが近年、重量の軽い一般的なビレイデバイスにブレーキアシスト機能がついた商品がいくつか発売されました。
その中でも特に注目されるのが、エーデルリッド社のメガジュル。
これまでのブレーキアシスト機能付きのデバイスの様にどっかんとブレーキをかける感じではなく、僅かに自然な流れが起こるため、支点にかかる衝撃もマイルドなものになりました。重量も一般的なビレイデバイスと変わらず、しかもハーフロープシステムやツインロープシステムでも活用できる利点があります。
懸垂下降を行う場合、これまでのビレイデバイスでは手を離してしまうと墜落が起きてしまうので、フリクションノットによるバックアップシステムが必要でした。しかしメガジュルはグリグリなどと同じくブレーキがかかっているので、握り手とは別にブレーキレバーでのコントロールを行うのでうっかり手を離しても墜落が起きません。
これにより懸垂下降途中からの登り返しシステムの構築も楽になりました。
構造やアイデアは実にシンプルですが、とても安全性の高い優れたビレイデバイスだと思います。
今後はきっとこの様なビレイデバイスが増えてくるのでしょう ^_^

デバイスのボディにカラビナがはまり込む事でロープがロックされる仕組みになっています。

ロアダウンやリードビレイの送り出し時には、解除レバーを上に引き上げながら行います。

懸垂下降のブレーキ解除は、解除用の穴にカラビナを通してコントロールレバーにします。

セカンドビレイ時は取り付け方が通常のデバイスとはロープを通す向きが逆になりますので注意が必要です。
エーデルリッドのメガジュルと、細経ロープにも対応したマイクロジュルは、Kuri Adventures クライミングジムでも販売しております。またレンタル用のデバイスとしてもお貸し出ししております。
人気商品なので取り扱っている店舗さんも多いかとは思いますが、是非 Kuri Adventures クライミングジムにて実際に触り、使用感を確認した上でお求め願えれば幸いですw
個人的にも愛用していますが、もう他のデバイスには戻れないくらいの安心感でとても気に入っています。
特にこれからの時期、冬用グローブをしたままでの細経ロープのビレイは怖いもの…。
これならば安心感があります!
本当におすすめですよ ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
山岳遭難の切り札!ココヘリ

山岳遭難捜索における切り札として現在注目を集めている " ココヘリ " 。
以前よりあるヒトココと言うビーコン探知機器を応用したサービスで、民間航空会社と連携して上空よりヘリコプターでビーコン捜索してくれます。
ヒトココは障害物などの影響でさほど遠くまで電波が届きませんが、これが空から探す場合には抜群に効果を発揮してくれるそうです。実験では1.5km程度先から検知できている様ですので、捜索対象となる山域をナメるように飛べば高確率で発見できそうです。
このサービスが、びっくりするくらい安いのもまた魅力的です!

.
.
ココヘリで山の安全を確保せよ!!
昨年よりはじまった " ココヘリ " と言うサービスはご存知ですか?
高齢者施設や保育施設などで安全管理に採用されたりしている " ヒトココ " と言うビーコン探知機器があります。950MHz帯の電波を使ったビーコンで、最大 1km 程度の範囲で捜索ができるシステムです。
一時は山での捜索に大きな期待が寄せられましたが、複雑な山岳地形においては百数十m程度しか電波が届かない場合も多いらしく、いまひとつ普及しませんでした。しかしここに来て、一気にブレイクし始めています!!
複雑な地形の中では百数十mしか届かない電波も、全く障害物の無い状況であれば 1km 以上電波が届きます。
そう、空に向かって飛んでいる電波を捕捉しようと考えられたのが、新たに始まったサービス " ココヘリ " です。

.
ココへリは民間航空会社と連携して行われるサービスで、救助要請が入った際にヘリコプターが捜索対象山域に急行します。
上空よりビーコンでピンポイントに遭難者を捜索し、その座標を警察や消防などの行政救助機関へ連絡してくれます。
これにより、これまで長期間に渡って行われていた遭難捜索の時間が大幅に短縮させられ、生存の可能性を大きく高めてくれます。
ヘリコプターを飛ばすと言うとなるとお値段も高くつくのではと思ってしまいますが、実はこのサービス、年間3,650円とかなり現実的なプライスで、しかも1回の遭難に対して3回までヘリコプターを無料で飛ばしてくれる凄い内容!
こんなんで本当に儲かるのかと考えてしまいましたが、計算してみるとこれでもガッツリ利益でるっぽいですw
私たち職業登山者の場合には道に迷って脱出不可能に陥るリスクはほぼありませんが、それでも負傷によって身動きが取れなくなる場合などもあるでしょう。
人間は3日間水を絶たれると生命の危機に瀕します。これにより、救助の世界では72時間が生存の期待できる一つのラインと考えられています。ココヘリを使えれば、72時間の壁は容易に打ち破れると期待できます!
また万が一山中で死亡した場合も、遺体が発見されないと行方不明扱いになり、遺族に保険が下りるのは7年後となってしまいます。また住宅ローンの支払なども免除とならず、残された遺族に多大なる迷惑をかけてしまいます。
全ての登山者が加盟するくらいでも良いサービスだと感じます。
ココヘリを有効活用するには、登山計画書の正しい運用が欠かせません。
いくら長距離からサーチできるビーコンでも、山域を特定できないと捜索のしようがありません。登山に行く際には、必ず家族や職場などに行き先と登山計画書の提出先を伝え、指定した警察機関や登山ポストなどにしっかりと登山計画書を提出しましょう。
現在では電子登山計画書提出サービスの " コンパス " などもあり、手軽に出すことが出来るようになりました。
ココヘリと合わせて登山計画書を運用することで、万が一の際に見つけてもらえる可能性が高くなります。
登山における自己責任とは、この様な準備をしっかりと行うことにこそあるのではないでしょうか?
なんだか凄い時代になりました。最新鋭のシステムにより山の安全は益々高まりますね^_^
ココヘリ、とても良いサービスだと思います。
ご興味ある方は加入してみては如何でしょう?
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雲上の寝心地 EXPED AirMat UL Lite

最高の寝心地と圧倒的な軽量化を実現してくれる、EXPEDのエアーマットULライトをご紹介します。 全身用サイズにも関わらず、その重量は実測で僅か342g。5cmの厚さが地面の凹凸を完全に消してくれ、しかも両サイドのチューブだけ太く作ってあるので、寝ている間のズレ落ちも起きにくくなります。
それに加え、クローズドセルマットを組み合わせることで、積雪期の背中の冷えや万が一のパンクに備えます。このことでお尻から背中の沈み込みが抑えられ、より自然なカーブを描いてくれるので腰痛も起きにくくなります。
本当に最高の寝心地になりますよ♪

.
.
最高の寝心地を山へ
登山において睡眠による体力回復は、翌日の山行の安全管理においてとても重要なポイントであると言えます。
眠りが浅かったり、夜中に何度も起きてしまうと、回復率が30%も低下してしまうそうです。特に連日テント泊を繰り返す縦走登山においては、眠りの質が山行のリスクを左右すると考えられます。
けっこうこの眠りの質には拘りがあり、これまで幾つものマットを買ってきています。
それこそ今我が家には、7つものスリーピングマットがあったりしまして…。どーすんだよこれ…。
そんな中、新たにもう1つ、スリーピングマットが加わりましたw
EXPED のマットはすでに3種使ってきています。
レクタ型(長方形型)とマミー型がありますが、これはもう圧倒的にレクタ型の勝ち!
しばらくマミー型の EXPED を使ってきていますが、夜中にずり落ちて目が冷めてしまうんです。
レクタ型はこの問題が起きにくく、抜群の寝心地です。
厳冬期には EXPED のダウンマットを愛用していますが、これがまぁ重い。なんせ900gもあるのです。
それにエアマットはどうしてもパンクの心配があり、冬は特に死活問題となります。
そこで冬はエアマットのクローズドセルマット(フォーマット)を組み合わせて使っています。これならしてもどうにかなります。
今回購入したEXPED AirMat UL Lite なら、実重量僅か342g!クローズドセルマットと組み合わせて、約500g!!
これならばずいぶん軽量化できます。
実際に使ってみると、その寝心地はまるで雲の上♪
エアマットの上にクローズドセルマットを重ねているので、腰やお尻周りが過度に沈み込まず、腰の痛みなどが出にくい。
十分な厚さのエアマットが地面の凹凸を覆い隠してくれるので、薄いクローズドセルマットでも快適な寝心地が実現します。
これは最高の寝心地です!!

とてもコンパクト。500ccのペットボトルくらいですかね?

空気入れ、修理キット、スタッフバッグを含んだ重さ、421g。

マット単体だと342g!軽いっ!!

空気入れが付属。僕はドライバッグタイプを使用なので不要。

空気を入れるとこんな感じ。ブルーが鮮やかです^_^

冬はクローズドセルマットを組み合わせて使います。
山の中での睡眠は、山の安全に直結します。そして山を最大限に楽しむためにも、睡眠環境を整えることは大切だと思います。
昔は軽量化のために睡眠に関わる装備を犠牲する様な事もしました。
しかしそのことで失われる体力は、微々たる軽量化よりもずっと大切なものであると気が付かされました。
山の中でも常に快適な睡眠を得られると言うことは、より山を楽しいものにしてくれます。
エアマットとクローズドセルマットの組み合わせ、最高に良いですよ!
その組み合わせでも軽さを追求するならば、EXPED AirMat Lite はおすすめです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
トレッキングパンツの裾を絞る

トレッキングパンツの裾に、絞り用のドローコードがついているタイプとそうでないタイプがあります。パンツの裾を絞れないと、クライミングシューズの様にヒールが低い靴を履いた時、かかとを裾に引っ掛けてしまうトラブルが起きがちです。
お気に入りのパンツがクライミングには使いにくく、泣く泣く違うパンツを履いていくって方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?
今回お伝えするのは、そんなゴム無しトレッキングパンツの裾を簡単なカスタマイズで絞り機能を追加する方法!
早速試してみましょう♪

.
.
トレッキングパンツのカスタマイズ
トレッキングパンツの裾に、絞り用のドローコードがついているタイプとそうでないタイプがあります。パンツの裾を絞れないと、クライミングシューズの様にヒールが低い靴を履いた時、かかとを裾に引っ掛けてしまうトラブルが起きがちです。
また雨の日などは裾が泥で汚れてしまったり、藪っぽいところでは虫が腿まで這い上がってきたり…。
一方でドローコードがついていれば、真夏の暑い時期のアプローチでは、裾を捲し上げてニッカボッカの様にして歩いたり、渡渉の時なんかにも便利だったりします。
そうは言ってもお気に入りのパンツにゴム紐が無かったりする場合も…。
そこで今回お伝えするのは、パンツの裾にゴム紐を入れ、簡単にドローコード付きパンツに仕上げる方法です!
早速試してみましょう♪

パンツの裾部分は2重~3重程度に折り返されて縫われていると思います。足首一周をぐるっとチューブが巻かれているような形状になっています。
ここにゴム紐を通していきます。

パンツの裏側の内くるぶし側2箇所にハサミで切れ目を入れます。この時表地を切ってしまわないよう、必ず表地と裏地を剥離させ、浮かせた状態でハサミを入れましょう。
縦に2箇所、2~3cm程度離して穴を開けます。

使用するゴムは手芸用のもの。裾周りは汚れやすいので、できれば黒いタイプをご用意頂くことを推奨します。

紐通しを使って穴にゴム紐を通していきます。
あまり一度にやり過ぎないように、丁寧に通していきましょう。
使用する紐通しは短めの方が使いやすいように感じます。

一周通したゴム紐を、オーバーハンドノットで結びます。
解けないようにダブルフィッシャーマンズノットで結びたいところですが、結び目を裾の反対側に移動させる時に引っかかります。
最初から縛りを強くしすぎると後で調整するのに解くのが大変です!
左右の足の絞り感のバランスを見ながら、最後に増し締めしましょう。この時、末端側を引っ張って締め込む様にすることで、リング内径に影響を与えずに締め込むことができます。
このあたりはロープワークの基本と同じですねw

ゴムの一報を引っぱっては馴染ませ、これを繰り返しながら結び目を反対側の縫い目まで持っていきます。
こうすることで結び目が目立たず、且つドローコードの動きもスムーズになります。

ドローコードを引っ張って足を通してあげると、自然な足首の絞りを作れます。

ドローコードなしでは引っかかってしまっていた裾も…。

とてもスッキリと絞ることができます♪

裾を捲し上げることで、ニッカボッカの様なスタイルにして履くこともできます。
夏の暑い林道のアプローチなどでは裾を捲し上げ、藪っぽいところに入る時に裾を下ろすなどすると快適です。
針も糸も使わず、簡単にパンツの裾にドローコードを入れることができます。
お気に入りのパンツがより使いやすくなり、けっこう便利ですよ!
お試しください^_^
ちなみに、写真のパンツはモンベルのサニーサイドパンツ。
薄手のトレッキングパンツながら丈夫で、とても強い撥水効果が長く続き、お値段もお手頃。僕の仕事パンツはいつもこれです。
登山インストラクターとして日々山で使い続けていますが、ハードな業務にもしっかり耐えてくれます。
ストレッチも効いてとても快適!おすすめですよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山におすすめなカメラ

登山において、カメラは切っても切れない道具。
美しい景色に出会ったり、共に山に入る仲間の笑顔は是非思い出として写真に納めておきたいものです。
登山という限られた条件にフォーカスし、どの様なカメラを選ぶべきかを考査してみました。そして個人的におすすめなカメラの選択を示しています。
カメラ選びに正解はありませんが、登山と言う限定された環境での撮影において何をどう選ぶべきかは自ずとその特徴から選ぶことができます。
カメラ選びのひとつの参考にして頂ければと思います。

.
.
登山におすすめなカメラの選択
新緑の森、流れ落ちる滝、苔むした沢、切り立った岩稜に、稜線からの雄大な大展望。
共に山を歩く仲間の汗と笑顔、テント場の賑やかな雰囲気、満点の星空。
登山を行うと、次々に現れる非日常な素晴らしい自然が現れ、その感動を是非思い出として持ち帰りたいと思うことでしょう。
そんな時、その臨場感をそのまま表現することができる優れた描写力のカメラが欲しくなります。
登山にあるべき道具として、カメラは切り離すことのできない道具のひとつではないでしょうか?
中には写真を撮ることを目的に登山を行う人すらいます。
その価値は十分に理解できるほど、カメラも奥深い趣味であり、その奥深さと面白さは登山のそれに匹敵するのかも知れません。
しかし山に入る目的は人それぞれで、長期縦走を好む者、渓流釣りを楽しむ者、山スキーにロッククライミング、アイスクライミングなど、重い装備をもって行動し、山行中にあまり時間の余裕を持てないケースも多くあります。
高画質なカメラを用意すればそれがいつもベストなのかと言えば、そうでは無いと感じます。
コンデジやスマホでも十分に美しい写真が撮れる時代にはなりましたが、やっぱり一眼カメラには敵いません。
大きなセンサーサイズによる高い画質に、レンズ交換による多彩な表現力。レンズ交換式のカメラはやはり優れています。
レンズ交換式カメラは大きく分けて2種類、一眼レフカメラとミラーレスカメラに分類されます。
ミラーレスとは一眼レフカメラにある機械式のミラー反射式光学ファインダーを排除し、代りに液晶モニターや電子ファインダーを搭載したカメラを指します。
発売当初にはレンズの種類が少ない、バッテリー消費が激しい、高画質なカメラが無いなどの欠点もありましたが、現在ではそれらの問題もほぼ解決し、少なくとも登山においてはミラーレスの方が利点がずっと多いと思います。
一言にミラーレスカメラと言っても様々なセンサーサイズがあり、その特徴によって装備重量や撮影される写真が大きく異なってきます。カメラ選びとは、すなわちセンサー選びであると言っても過言ではありません。

.
ミラーレスカメラのセンサーサイズは、中判・フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズ・1型センサーの5種類があります。(表にある1/1.17型は高級コンデジ、1/2.3型は一般的なコンデジのセンサーサイズとなります。)
中判サイズはまったく一般向けでは無いので、選択肢はそれ以下の4種となります。
現在ではフルサイズでも1型でも、ミラーレスカメラなら本体重量にはさほど重量差はありません。
センサーサイズが大きいほど高画質になる一方、レンズの焦点距離が伸びる分、レンズ重量が増します。またセンサーサイズが大きいほど、バッテリー消費も早い傾向にあります。
センサーサイズが大きいほど被写界深度が浅くなり、強いボケの撮影がしやすくなります。
これらのセンサーの特徴を踏まえ、登山に適したセンサーサイズのカメラ選びを行っていきましょう。
もし写真撮影を目的として登山を行うなら。すなわち写真が趣味であり、素晴らしい景色の撮影を行う目的で山に入るような方の場合、やはりフルサイズセンサーのカメラを選択すべきでしょう。
レンズの重量が重く、またサイズも大きくなるため、歩行や登攀に大きく支障が出ます。しかしやはり美しい写真を撮る上で、大きなセンサーは欠かせません。特にボケの大きさはセンサーサイズに大きく影響するため、背景ボケの写真を撮影したいのであれば、フルサイズセンサーの方が圧倒的に有利です。また星空を撮影したいような場合には高感度耐性の強さが必要になり、紅葉などの色合いをよりキレイに表現したければダイナミックレンジの大きさが問われます。
これらはセンサーサイズの大きさに影響されるため、より美しい写真を撮りたい場合にはフルサイズセンサーが優れています。
写真を趣味とする場合には、山は選択肢の一つに過ぎず、対象被写体も様々になると思います。その応用幅を考えても、フルサイズを選ぶべきでしょう。
一方で登山を主目的とし、その中で風景の写真を美しく撮影できたらと考える方はマイクロフォーサーズセンサーのカメラをおすすめします。
マイクロフォーサーズは"人間が現実的に気兼ねなく持ち運べる機材重量の範囲で、最大限の画質を追求する"ことをコンセプトとしており、まさに登山の最中に出会った美しい風景を思い出に納めるのに適したセンサーサイズであると言えます。
一眼カメラの特徴は"大きなセンサーサイズで美しい写真を、目的によってレンズを変えることができる”事です。言い換えれば、"レンズ交換をしないと応用が効きにくいカメラ"でもあります。
センサーサイズが小さければ小さいほど、同じ画角(同じ大きさになる)の写真を撮る際の"センサーからレンズまでの焦点距離"を近くすることができます。この為にスマートフォンやコンパクトデジカメの方がレンズ交換も無しに広角から望遠までの撮影が可能なのです。
美しい写真を撮影するためにはある程度大きなセンサーサイズが必要で、しかもズーム効率は悪ければ悪いほど高画質なレンズが作りやすくなります。この為、一眼カメラではレンズ交換を行うことが、その価値を最大限に活かす秘訣ことができます。
センサーサイズの大きさによりレンズの大きさや重量が大きく異なってしまいますので、登山の様に運搬に制限がある環境の中でいくつかのレンズを持っていこうと思えば、センサーサイズに制限をかけるべきであると思います。
それを言うとセンサーサイズの小さなコンデジが優れている事になるのですが、満足行く写真が撮影できるかと言えば、その表現力は乏しいものとなります。
個人的には、登山に使用するセンサーサイズはマイクロフォーサーズが最もそのバランスに優れ、使いやすいカメラなのではないかと考えています。
登山を主体とするのか、カメラを主体とするのか、どちらとは決められない様な方は、その中間に位置するAPS-Cが良いでしょう。被写界深度も、フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズでちょうど1段分ずつの差となります。
ある意味一番バランスの取れた機材であるかもしれません。
1型センサーは Nikonn のミラーレスカメラだけが採用しているサイズで、それ以外のメーカーはコンデジの最高品質カメラで使用しています。つまりレンズ交換ができる点を除いては、高級コンデジと差の無い画質の写真撮影しかできない事になります。
しかし現時点で完全防水・耐衝撃性の一眼カメラは Nikonn にしか存在せず、沢登りやクライミングなどの過酷な環境で一眼カメラを使用しようと思った時、ストレス無く扱える一眼カメラは1型センサー以外に存在しないことになります。
またセンサーサイズの小ささから、全体的なシステムのコンパクトさも当然随一となります。
唯一無二の魅力が確かにあります。

マイクロフォーサーズはフルサイズのほぼぴったり 1/4 の大きさになります。この為、同じ画角の撮影に必要な焦点距離は、1/2 となります。この為、小さくて軽いレンズが作りやすくなり、フルサイズとマイクロフォーサーズではその差は圧倒的な差となります。
例えば山で高品質な人物写真を撮ろうとした時、F2.8 通しの望遠レンズ欲しくなります。。フルサイズで70-200mmの望遠ズームを用意したとしたら、その重量は凡そ 1,500g にもなります。
これをマイクロフォーサーズで考えると、同じような画角で 35mm - 100mm (フルサイズ換算 70mm - 200mm ) の Panasonic レンズが 360g となります。
また大きさも、フルサイズでは Φ88mm × 200mm に対し、マイクロフォーサーズでは Φ67.5mm × 100mm と半分以下の大きさになります。バズーカの様なフルサイズの望遠を登山に持っていくことはあまりに非現実的ですが、マイクロフォーサーズでは十分現実的な重量とサイズになります。
人物や植物を撮影するような場合にはボケも重要です。ボケ量だけで言えばマイクロフォーサーズのF2.8はフルサイズのF5.6と同等となりますが、山の中では背景を遠くに取りやすい分ボケさせやすい点や、こちらに向かって歩いてくる同行者の写真を取りたいと考えた時の、被写体が歩いてくる事によるピントずれを考えると、現実的にはこのくらいの絞り開放度が現実的だと思います。
しかし樹林帯などの薄暗い環境においての撮影でブレない様に素早く撮影を行っていくには、明るいレンズが必要になります。
ISOを上げずに撮影するには、やはり明るいレンズが求められます。
ここでは換算 70-200mm F2.8 望遠ズームレンズについて語りましたが、風景撮影を考えると少なくとも広角~標準ズーム、場合によっては超広角レンズやマクロレンズも欲しくなります。
仮に数本のレンズを持つと考えると、その体積や重量差はもっと大きくなります。登山を目的として山に入る場合、フルサイズでこの様なレンズをいろいろと持ち込むことは非現実的な重量となります。
システム全体を現実的な重量で持つことができる事こそ、マイクロフォーサーズの魅力です。

フルサイズ 70-200mm f2.8
.

マイクロフォーサーズ 35-100mm f2.8 (フルサイズ換算70-200mm)
.
マイクロフォーサーズはボケないと言われます。
ボケは F値、センサーサイズ、焦点距離 で決まってきますので、マイクロフォーサーズではやはり圧倒的に不利です。
凡そ2倍のF値の差があると思って間違えありません。マイクロフォーサーズで明るいレンズを用意し、仮に F 0.95 などと"人の目で見るより明るい"すごいレンズを選択しても、そのボケ量はフルサイズの F 1.8 と同程度となります。
もちろんマイクロフォーサーズでも背景ボケの写真を撮影できますが、フルサイズの方がもっと簡単に撮影できます。
一方で登山で良く行われる風景写真では、パンフォーカスで撮ることがほとんどです。
パンフォーカスはボケの逆で、手前から奥まで全体にピントが合った写真を言います。風景を撮影するには全体がクリアに写る必要がありますので、パンフォーカスでの撮影が求められます。
パンフォーカスの場合、F値を絞る必要があります。マイクロフォーサーズはフルサイズの2倍ボケないと言うことは、すなわち半分のF値で同じくらいパンフォーカスにできると言う事でもあります。
シャッタースピードはF値、ISO、EV値に影響されるので、仮に同じ F8 であれば、フルサイズでもマイクロフォーサーズでもスマホでも同じです。しかしマイクロフォーサーズと同じ被写界深度にするのであれば、フルサイズでは F16 にしなくてはなりません。
マイクロフォーサーズなら手持ちで撮影できる風景写真も、フルサイズの場合には三脚が必要になる場合もあります。
登山の途中に何気なく風景の写真を撮ろうと思った時、このアドバンテージはとても大きなものとなります。
またF値を絞るといわゆる"小絞りボケ"、回析現象が起きます。光がレンズ内で屈折反射を起こすことで画質が乱れる現象で、F値を絞れば絞るほどに起きやすくなります。
これはF値が同じであればセンサーサイズが大きいほど発生しにくいのですが、シャッタースピードが重要な撮影ではなく、パンフォーカスを主体に考える場合、マイクロフォーサーズの方が絞りが浅い分ずっと有利となります。
これらの事から、登山に持っていくカメラとして、マイクロフォーサーズがとても優秀であることが分かります。
ただもし写真が目的で山に入る場合には、時間や機材でフルサイズの欠点を消すことができます。
丈夫で重量のあるしっかりした三脚を用意したり、様々な種類のフィルターを用意したり、バッテリーをいくつも用意したりなど、重量や体積、撮影時間を気にせずに撮影するならば、やはりフルサイズの方が良い写真が撮れます。
腰を据えた撮影にはフルサイズが良いでしょう。
マイクロフォーサーズの利点はスピードと機動性にあります。
気に入った景色があればどんどん手持ちのままパンフォーカスな写真を撮影し、ポーチに入れたいくつものレンズを交換しながら稜線からの雄大な景色、遠くの野鳥、咲き誇る野花、共に山を登る仲間の写真を次ぎ次ぎに撮影していく。
登山に的を絞ったカメラ選びとしては、マイクロフォーサーズが優れていると感じます。
登山に持っていくカメラは、どれが正解と言うものでもありません。またフルサイズだから偉いということも、コンデジだから悪いと言うこともありません。
撮影者が何を目的にどの様に撮影したいか次第であり、その選択は個人の自由です。
より小さいセンサーの特徴を強めるならば、1型センサーの 1NIKKOR にするなどの選択肢もあります。何よりも高画質な写真を撮りたいならば、やはりフルサイズを選択すべきでしょう。
マイクロフォーサーズを奨めている理由は、レンズの豊富さや画質と携行性のバランスに優れると個人的に感じているだけであり、その選択が誰にとっても正解であるわけではありません。
大切な事は、自分自身がどの様なシーンでどの様に撮影したいかを良く考えることです。
その上でカメラを選びましょう。
登山インストラクターと言う職種の中で、日々の講習業務の中でご参加者様やフィールドの写真などを、荷を下ろすこともなく、極力足を止めたり、三脚を出したりせずに、業務の隙間を縫って素早く撮影を行っていくのにマイクロフォーサーズはとても役立っています。
仲間と登山にでかけ、その合間を縫って"作品"としての写真ではなく、"思い出”としての写真を残していく。
そんな用途にマイクロフォーサーズは適していると思います。
皆様のカメラ選びのひとつの選択の指針としてお役立て願えれば幸いです。
カメラと共に山に入り、素晴らしい景色を切り取って人生の思い出に彩りましょう!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
山を表現する超広角レンズ " LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH "

登山を行うと、雄大な大自然に出会います。
その美しさを写真に納め人に伝えようと思っても、なかなか本来あるべき自然を表現することは難しいものです。その最大の理由が、遠近感と景色の広がりにあると考えました。
そこで購入したのが超広角レンズ!
人間の視野よりも広いエリアを写し込むことができる上、自然の奥行き感をグッと引き出す事ができる素晴らしい特性を持っています。
写真に悩んでいる方は、ちょっと検討して見る価値あるかもしれませんよ?

.
.
大自然の雄大な景色を切り取るレンズ
例えば北アルプスの稜線上からの大パノラマや、沢の奥に聳える雄大な大滝。
大自然の美しさを是非思い出の記録として残しておこうとカメラを取り出し撮影。しかし、その雄大さを伝えることはなかなか難しいものです。
写真で自然の美しさを表現することの難しさに、遠近感や画角的な広がりにあると考えられます。
人間が持つ視野より狭い画角で、のぺっとした表現では、今自分自身の目の前に広がる雄大さが伝わりません。
そんな時に使いたいのが、超広角レンズ!
35mm換算で焦点距離28mm以下のレンズを超広角レンズと言います。
超広角レンズには人間の視野を超える広い画角の撮影が可能なばかりでなく、遠いものをより遠くに表現する特性があります。
写真の一箇所に向かって、線が集約される事で、とても遠近感のある写真が表現できます。
欠点として写真の周辺角付近に歪みが出やすかったりしますが、その特性を考えた構図にすることで解決できるでしょう。
個人的には登山に使用するカメラはマイクロフォーサーズを選択しています。
焦点距離をフルサイズの半分で済むと言うことは、すなわちレンズのサイズを小さくできると言うこと。この結果、何本かのレンズを持った時、フルサイズよりずっと軽く済みます。
またレンズもカメラボディもフルサイズよりずっと安価で、ラフに扱う環境でもそこまで気負わず使える事は大きな利点です。
今回新たに導入したのは、LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 と言うレンズです。
フルサイズ換算 14 - 28 mm のズームなので、超広角~広角までをカバーできる便利な一本です!
そして僅か 300g とこの手のレンズとして驚異的に軽く、登山に持ち出すのにストレスが少ない優れたレンズです。


コンパクトな Panasonic LUMIX DMC-G7 に装着しても、違和感の無いコンパクトなデザイン。
同等のスペックを持つオリンパスのレンズと比べて凡そ半分程度、フルサイズなどと比べると1/3ちょっとの重量で済んでいます。
登山において、軽いことは大切なことです。


上の写真が広角14mm(換算28mm)、下の写真が超広角7mm(換算14mm)。
この焦点距離では1mmの変化がとても大きい領域で、超広角の方がとても奥行き感のある表現が出ていることが分かります。


.


写真撮影を目的とした登山であれば、やはりフルサイズの方が適しているでしょう。センサーサイズの大きさは画質に大きな差が出ます。
しかし写真を本格的な趣味として楽しんでいる方以外の登山者は、トレッキングやクライミングなどを目的としており、そこで見た風景を写真に納められたらなぁって場合がほとんどであると思います。
作品として優秀な写真を撮ることよりも、思い出の一枚がより伝わるものである必要性があります。
LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 とマイクロフォーサーズセンサーのミラーレスカメラの組み合わせなら、複数本のレンズを持ってもさほど苦にならない重量に収まります。
撮りたい時に撮りたい画角のレンズをいつも携行していられること。
これこそ、登山者に求められるカメラの在り方なのではないかなって感じます。
そういった意味で、LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 はとても使えるレンズです!
マイクロフォーサーズを使用されている方や、これから一眼カメラを検討されている方にはおすすめの一本ですよ(^^)
大自然のありのままを切り取りに行きましょう。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪山登山技術 - スタンディングアックスビレイ -

森林限界を超える雪山登山は、あらゆる登山カテゴリーの中でも特に危険性の高いアクティビティです。 その最大の理由が確保のしにくさにあります。
確固とした支点を構築しにくく、中間支点の設置にも手間のかかる雪山登山において、ロープによる安全確保がなかなかしにくい傾向にあります。
それでも危険な箇所では積極的にロープを出し、安全確保を行う必要性があります。 スタンディングアックスビレイは、雪上において比較的手間なく、且つ強固な確保を行うことができる優れた技術です。
しっかりと練習を重ね、安全な登山を行いましょう!

.
.
スタンディングアックスビレイ
雪山登山の危険箇所で安全確保を行うのに、特に有効なスタンディングアックスビレイを覚えましょう!
比較的簡単に行え、確実性の高い確保技術となります。
大きな滑落事故を防ぐ上で、とても有効な方法です。

手でスノーバーを押し込めないくらい雪が締まっている場合、スノーバーは立て埋めでも効きます。地面の垂直軸より拳一個分程度山側に寝かし、ピッケルのヘッドで雪に叩き込みます。
スノーバーは完全に雪に埋め、足で踏んで雪を固めます。
可能な限り2本のスノーバー、又はハンマーなどから分散支点にしましょう。

雪が柔らかい場合、T字アンカーにします。
まず雪面を踏み固めます。続いて斜面と平行に、深さ50cm程度の溝を切ります。

シャフトとスパイクでT時に溝を切っていきます。
この時、横溝の底と並行、又はそれより下向きになるように深く溝を掘ります。

スノーバーに120cm程度のスリングをガースヒッチ、またはクローブヒッチで固定します。スリングの反対側の末端には、安全管付きカラビナを取り付けておきます。

斜面の上側から雪を落とし、横溝を完全に埋めます。
斜面下側を破壊しないように気をつけながら、雪を踏んで固めます。

メインロープと安全管付きカラビナを繋ぎ、セルフビレイとします。
この時、横溝の底辺より腰の位置が低い場所になるよう、ロープの長さを調整します。

セルフビレイが張られる位置に、スタンディングアックスの支点を構築します。
スリングをピッケルのシャフトに通し、安全管付きカラビナを取り付けます。
スリングの長さは15cm程度とします。

ピッケルのヘッドが外に吹き飛ばされないよう、ヘッドに靴の側面をピッタリと添わせ、スリングを踏み込んで固定します。
安全管付きカラビナにロープを通します。この時。パートナー側のロープが雪面側を通るようにします。

肩絡みビレイの体制を取り、パートナーを確保します。
森林限界を超える雪山登山は、あらゆる登山カテゴリーの中でも特に危険性の高いアクティビティです。
その最大の理由が確保のしにくさにあります。
確固とした支点を構築しにくく、中間支点の設置にも手間のかかる雪山登山において、ロープによる安全確保がなかなかしにくい傾向にあります。それでも危険な箇所では積極的にロープを出し、安全確保を行う必要性があります。
スタンディングアックスビレイは、雪上において比較的手間なく、且つ強固な確保を行うことができる優れた技術です。
しっかりと練習を重ね、安全な登山を行いましょう!
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

雪山登山講習
雪山登山に必要な、歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪崩対策技術、雪洞泊技術をお伝えします。訓練形式の講習で、しっかりと技術を身につけられます。
確かな技術を持った上で、雪山登山を楽しみましょう!
料金:18,500円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪山登山技術 - 雪洞の掘り方 -

雪山登山の大きな危険に、気温の低さがあります。
寒いということは、ただそこに居るだけで命を奪われると言うこと。万が一ビバークに追い込まれれば、非常に厳しい状況に陥ります。
しかし、もし雪洞を素早く作ることができればどうでしょう?
風雪を遮り、寒気を遮断する雪洞の中は、常に室温が0℃前後を保たれます。
決して温かい環境と言うわけではありませんが、それでも十分耐えることができる寒さです。実際に、自然界に生きる動物達は、こうして生き延びています。
そんな雪洞の作り方を学びましょう!

.
.
雪洞の掘り方
雪山登山には様々な危険がありますが、その一つに気温の低さがあります。
寒いと言うことは、ただそこに留まるだけで低体温症に陥り、最終的には命を奪われるということです。雪山登山で怪我をしたり、暴風雪などで身動きが取れなくなったり、道迷いで夜が近づいてくれば、それはとても厳しい状況に陥ります。
しかしもし雪洞が掘れれば、状況はかなり改善します。
雪はその70%程度が空気であり、非常に高い断熱性を持っています。仮に外気が−20℃を下回る様な寒さであっても、雪洞の中は雪の温度である0℃前後を保ってくれます。
その一方で、内部でいくら火を起こしても、気化熱により温度を奪われ、結局0℃前後から変わりません。
それでも外と比べれば雲泥の差!
雪洞の中は常に0℃前後を保たれる、ちょっと肌寒いくらいの環境になります。
雪洞内部でツェルトなどを被れば、さらに5℃~10℃くらい温度をあげられます。
マットや厚手のダウンジャケットなどがあれば、十分仮眠をとることもできます。
雪洞を掘れること、そしてそのための装備、ビバークの為の装備を持っていれば、雪山のリスクの一部を大きく軽減できます。
まずは知識として身につけていきましょう。

まず十分な深さがあるかプローブで確認します。
3m程度あると安心です。

掘る方向も、十分な空間があるか確認します。
収納人数が横になれる空間が必要です。
緊急時でも、体育座りの状態で入れるサイズが最低限必要となります。

斜面の手前を足で踏み固め、少し地面を掘ります。
凡そ、人がしゃがんだくらいの高さを目安とすると良いでしょう。
掘り進める時は、ショベルで溝を切ってブロック単位で切り取っていきます。
天井には十分な厚みを持たしておきましょう。
入り口から50cm程度進んだあたりから、横への拡大をはじめましょう。

内部を広げながら、どんどん掘っていきます。
入り口にツェルトやシートなどを広げ、その上に雪を置いておけば、あとで雪を捨てるのが楽になります。
人が一人横になれる程度の空間を作りましょう。
夜の間に溶けて天井が下がってきますので、作成段階で床を掘り、十分な天井高にしておきましょう。快適度の面からも、天井高は横の広さより重要です。
天井はなるべく滑らかに仕上げることで、水がポタポタ垂れてこなくなります。
床の端に一段低くなる溝を掘っておくと、寒気が足元から抜けて快適です。

雪洞が出来上がったら入り口をシートなどで覆います。
雪洞の入り口から50cm進んだところから空間が広がっているので、その手前の雪の層を活用してピッケル、スノーバー、拾ってきた枝の横埋めなどで固定しましょう。
エマージェンシーシートなどを使用する場合、30cm程度の細引きを輪にしたものを3~4本程度用意しておき、シートの固定用にすると便利です。
シートが無い場合は内部から雪を盛って入り口を塞ぎます。
この場合、必ず拳3つ分程度の隙間を残しておき、換気しておきます。

内部の壁に穴を開けて小さな棚を作り、ロウソクを置いておくと照明として便利です。
ロウソクは酸素濃度15%程度で火が消えます。通常待機中の酸素濃度は20%程度。ロウソクが点かなくなると言うことは、すなわち換気するべきであると言う目安にもなります。
内部温度は0℃前後になりますので、内部でツェルトをかぶれば、その内部は5℃~10℃くらいになります。バックパックなどの上に座り体温消失を避ければ、まどろむ程度に仮眠がとれるでしょう。
マットと温かい防寒着を持っていれば、十分眠ることもできます。
ここでは一人用の十分寝れるスペースを確保する方法をお話していますが、仮にもっと緊急な状況であれば体育座りで収まるギリギリの大きさでも構いません。例えショベルが無くとも、ピッケルや鍋などで凡そ30分程度で掘ることができます。

.
また大人数で協力し合えば、大きな雪洞を掘り、快適空間に仕上げることも可能です。
テントを装備から外すなど、装備の大幅な軽量化を図れます。
雪洞なら、寝袋も3シーズン用で十分です!
厚手の防寒着を使用したり、プラティパスやナルゲンで湯たんぽを作れば快適に眠れます。
雪洞は、何度か経験しないとなかなか難しい部分もあるかと思います。特に雪洞泊としてキャンプをするのでは無く、最低限の装備でビバークするとなると尚更です。
まずは雪の多い地域に赴き、危険の少ない場所で実際に雪洞に泊まってみましょう。
その経験は、いざという時に命を救います。
Kuri Adventures では雪洞に関する講習も行っています。
現場で雪洞を作っても良い地形を学び、実際に自分自身で穴を掘り、ビバークを行ってみる。指導者監修の安全な環境で雪洞を体験しておくことで、いざという時に的確な雪洞作りが行える様に技術を養います。
雪洞に関することをお伝えすることで、皆様の安全登山に繋がれば幸いです。
下の動画で、さらに詳しく説明しています。
是非ご覧頂ければ幸いです ^ ^
.
.
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

雪洞体験
雪山登山の大きな危険の1つに低体温症があります。
気温が低いと言うことは、ただそこでじっとしているだけで命を奪われると言うこと。雪山登山におけるビバークは、極めて困難な状況になります。
安全に雪山でのビバークを行うために、雪洞を作って泊まる技術が欠かせません。
料金:13,880円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
アイスクライミング用のおすすめリーシュ

アイスクライミングを行う際に利用するリーシュ。なかなか納得できるものが無いので自作してみました!
業務用ランヤードに使用するスイベルにデイジーチェーンを繋ぎ、スピナーリーシュに近い自作リーシュを使用しています。
業務用ランヤードは墜落荷重に耐えられる上、デイジーチェーンの組み合わせなのでアックスの位置に関係なくアックステンションをかけられる利点があります。
またアックスを打ち込めば、どこでも簡易セルフがとれる優れもの!
なかなか便利でおすすめです♪

.
.
アイスクライミング用リーシュを自作!
各メーカーからアイスクライミング用のリーシュが販売されていますが、今ひとつ納得できない部分があります。
それは強度。せっかくビレイループとアイスアックスのスピッツをつなぐのに、ほとんど全ての商品が墜落荷重に耐えられません。これでは、アックスそのものを簡易的なセルフビレイとして使ったり、レストに使うことができません。
かと言ってスリングを使ってリーシュにしようとしても、2本のスリングが捻くれたり、微妙に長さが足りずにつっぱった感じを受ける場合もあります。
これらの問題を解決すべく、アイスクライミングのリーシュを考えてみました。
市販のリーシュの多くが強度を出せていない理由は、スイベルの強度にあります。
かと言ってスイベルを設けなければ、やっぱり2本のリーシュコードが捻れて絡み合ってしまいます。
高強度なスイベルにしようとすると、こぶし大程度のスイベルしか無かったりしました。
しかし最近、PETZLより比較的小さくて軽いスイベルが販売されました。
高所作業などの業務用に使用するスイベルで、ランヤード(登山で言うところのセルフビレイコード)を接続するために開発された様で、まさにリーシュは使用用途としてピッタリかもしれません♪
これを利用して工夫し、とても高強度で便利なリーシュを作ってみました。
かなり便利な道具となり重宝しています。おすすめですよ ^_^

PETZLのプロフェッショナルライン(業務用)の商品に、最近マイクロスイベルと言う商品が発売されました。
レスキュー用のものよりずっと小さくて軽い!
しかも墜落荷重に耐えられる強度を持っています。

カラビナ連結用の穴にはゴムのブッシュが取り付けられており、カラビナが回転して横向きになる事を防いでくれます。
とても安全性の高い、親切な構造♪

スイベルには 140cm のダイニーマデイジーチェーンを2本繋いでいます。
スイベルがあることで、2本のリーシュが捻じくれる事を防いでくれます。このあたりは、各メーカーさんが作っているアイスクライミング用リーシュのアイデアを流用!

先端には超小形軽量タイプのカラビナを取り付けています。
ハーネス接続の安全管付きカラビナから、スイベル、デイジーチェーン、カラビナと全てがクライミングに耐えられる強度!
連結をガースヒッチにしているので最大で50%程度の強度低下が考えられますが、それでも一本あたり 10kN 以上の強度が見込めます。スイベルや安全管付きカラビナの強度を考えると、丁度よい感じですね ^ ^
まぁ、2本同時にテンションかかることも無いでしょうが…。

高強度なリーシュですので、例えば氷や締まった雪面、凍った草付きにピックを刺し、リーシュをアックスのスピッツに繋いでおくことで簡易的なセルフをとったりもできます。
またデイジーチェーンを使用しているので沢山の輪があり、どこにでもフィフィをかけてレストできます。
アックスの位置に関係なくアックステンションが行えるのは大きな強みです。

ちょっと重たいのは欠点ですね ^^;
いつでもセルフがとれ、アックステンションが行える高強度のアイスアックス用リーシュはとても頼もしい存在です。
そりゃアックステンションをかけず、途中でレストもせずに登れりゃ一番良いわけですが、でも安全なアイスクライミングを楽しむ上で墜落を防止する策をバックアップとして設けておくことも大切だと思うんです。
アイスクライミングのリードはリスクを伴います。
少しでも安全なクライミングを楽しむ為に、逃げ道を用意することも大切な選択だと考えています。
皆様の安全な登山にお役立て願えれば幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2017.3.5 はじめてのアイスクライミング講習

アイスクライミングは一部のクライマー達だけに許された遊びだと思われている方も多いのですが、現在では人工アイスクライミング施設のおかげで誰でも手軽に、安全に楽しめるようになりました。
森林限界を超えた雪山登山を行うと、氷化した危険箇所が現れる場合もあります。
その様な場所でも落ち着いて、安全に行動する為の技術をアイスクライミングで養うことができます。アイスクライミングはもはや特殊な遊びではなく、雪山登山を行う全ての登山者が行うべき訓練なのかもしれません。
そんなアイスクライミングの講習の様子をブログにまとめています。

アイスクライミングは一部のクライマー達だけに許された遊びだと思われている方も多いのですが、現在では人工アイスクライミング施設のおかげで誰でも手軽に、安全に楽しめるようになりました。
アイスクライミングとは、" 氷化した超高難度な箇所を移動する技術を安全に学ぶことができるスポーツ " でもあります。
森林限界を超えた雪山登山を行うと、氷化した危険箇所が現れる場合もあります。
その様な場所でも落ち着いて、安全に行動する為の技術をアイスクライミングで養うことができます。
アイスクライミングはもはや特殊な遊びではなく、雪山登山を行う全ての登山者が行うべき訓練なのかもしれません。
Kuri Adventures のアイスクライミング講習は、岩根山荘のアイスツリーにて行っています。
車を降りて目の前にある氷壁を登る企画なので、まだ雪山登山経験が浅い方でも問題無くご参加頂けます。
アイスアックスの使い方、アイゼンの蹴り込み方、基本となる体の動かし方などを学習します。
アイスクライミングをこれから始める方はもちろん、雪山登山の為にご参加頂く方も歓迎します。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!
またのご参加を心よりお待ちしております(^^)




登山技術講習へのご参加はこちらから!

はじめてのアイスクライミング講習
まったく初心者の方からご参加頂けるアイスクライミング講習です。
アックスの打ち込み方、アイゼンの蹴り込み方、登る際のバランスのとり方など、アイスクライミングの基礎中の基礎を学びます。
対象:冬季登山靴、ワンタッチ 又は セミワンタッチ式アイゼンをお持ちの方
料金:12,000円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2017.3.4 山岳ロープワーク講習

登山における安全確保に必要なロープの結びと、その結びを活用した安全確保技術を学ぶ " 山岳ロープワーク講習 "。
山岳遭難死亡事故のワースト1が転滑落によるもの。そのほとんど全てを、ロープによる適切な安全確保技術で防ぐことができます。
エイトノットやオーバーハンドノット、ダブルフィッシャーマンズノット、プルージック、クレイムハイスト、クローブヒッチに加え、タイトロープ、スタカットビレイを学びます。
その様子をブログにまとめています。

登山における死亡事故ワースト1は、転滑落によるものです。
そしてそのほとんどすべてを、ロープによる安全確保技術で防ぐことができます。
ロープワークを覚え、安全確保技術を身につけると言うことは、それすなわち登山における重大事故発生率を下げることに繋がります。安全登山の為には、ロープによる安全確保技術が欠かせません。
Kuri Adventures の山岳ロープワーク講習では、ロープの結びに加えて2つの確保技術について学びます。
支点を設置して、セルフビレイをとった上で相互確保を行うスタカットビレイと、メンバー全員がロープに繋がったまま移動する、コンティニュアスビレイの1つ、タイトロープ。
特にタイトロープ技術は、誰でも簡単に覚えられ、安全性が飛躍的に高まる素晴らしい技術です。
恐らく、一般登山道を歩く上でもっとも実用性の高い確保技術でしょう。
一日かけ、しっかりと学習して頂きました。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!











登山技術講習へのご参加はこちらから!
山岳ロープワーク講習
登山中に現れる危険箇所の通過や、バリエーションルートを歩く際に必要な安全確保技術を指導します。積極的にロープを使った確保を行うことで、山の安全は確実に高まります。
安全登山の為にも、是非ロープワークスキルを身につけましょう!!
料金:9,250円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
ペツル クォーク カスタマイズ

オールマイティーに使えるアイスアックスとして定評のある、ペツルのクォーク。
きっと日本で一番売れているアイスアックスでしょう。どこに行っても見かける、定番中の定番商品です。
みんなに選ばれるのにも理由があり、かなり扱いやすい、完成度の高い道具です。
しかしそれでもノーマル状態では少し使いにくい部分もあったので、オリジナルカスタムを施してみました!
全ての人に適しているとは言い難いのですが、けっこう便利なアイデアもあるので試してみては!?

.
.
PETZLのクォークをカスタムしてみた。
様々なシーンで使いやすいアイスアックスとして定評のある、ペツルのクォーク。たぶん日本一番売れているアックスでしょう。
その使用用途はアイスクライミングに留まらず、岩稜バリエーション、雪山登山、低山バリエーション、沢登りなど、実に様々なシーンで活躍してくれます。
とても扱いやすく、クセのない、完成度の高い道具です。たくさんの方に選ばれているのも納得です。
そんなペツルのクォークですが、さらに使いやすくするためにカスタマイズを施しています。
定番のカスタムからちょっと変わったカスタムまで、いくつかご紹介させて頂こうと思います。

定番のカスタマイズ。ピックの側面を削って全体にテーパーをかけながら薄くしています。
上部の角度を鋭くし、少しだけ抜けも良くしています。
先端部は鋭く下向きに尖らせ、デフォルトよりも掛かりを強くしています。



ハンドリーシュを取り付けるための穴には、カラビナをかけるためのリングを取り付けています。
5mm の超低頭ネジを使用し、反対側にはアイナットを取り付けています。またアイナットには4mmの細引きも取り付けています。


緩斜面の登攀時は、ローダガーポジションで杖のように使ったり、ピオレトラクションで登ったりとアックスの持ち方が変化します。緩斜面ではアックステンションをかける事は無いので、リーシュはスピッツにある必要はありません。
様々な持ち替えに対応するよう、シャフトの中央部にリーシュを繋げます。
このカスタムは以前から行っておりますが、とても使いやすくおすすめです!
4mm の細引きはハンドリーシュを繋ぐために使用しています。
エーデルリッド社のハンドリーシュは先端部がカラビナ接続になっています。このハンドリーシュの長さを調整するために、4mmの細引きを取り付けています。

緩斜面登攀時に握っている時間の長いシャフト上部には、自己融着テープを巻いています。
滑りを防止し、手の冷えを緩和してくれます。
道具を自分なりにカスタマイズし、使いやすくすることで、より愛着が湧いたりします。
そしてその道具を使って冒険を繰り返すことで、その道具は自分の体の一部のようにすら感じるようになっていきます。
道具を選び、使い、愛でる感覚もまた、登山の楽しみの1つかもしれませんね ^_^
定番カスタムから僕のオリジナルまでいくつか紹介させて頂きました。
皆様のご参考にして頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2017.3.1 富士山 二ツ塚

富士山の中腹に位置する2つのピーク、二ツ塚へ行ってきました。
二ツ塚は宝永山の噴火の際にできた山だとされており、富士山の斜面の途中に山が盛り上がっている不思議な景色を楽しめる山です。
真っ白で広大な雪原の先にそびえる富士山と宝永山、そして雪原の中に盛上がる二ツ塚。手軽なハイキングながら、そのダイナミックな景観は圧巻です。
また二ツ塚に登頂する前には、富士山特有の雪崩である"雪代"により削り取られたハーフパイプ状の地形の中も歩きました。
様々な地形を歩くことで、雪山の歩行技術を身に着けて頂きます。

富士山の中腹に位置する2つのピーク、二ツ塚へ行ってきました。
二ツ塚は宝永山の噴火の際にできた山だとされており、富士山の斜面の途中に山が盛り上がっている不思議な景色を楽しめる山です。 真っ白で広大な雪原の先にそびえる富士山と宝永山、そして雪原の中に盛上がる二ツ塚。
手軽なハイキングながら、そのダイナミックな景観は圧巻です。
また二ツ塚に登頂する前には、富士山特有の雪崩である"雪代"により削り取られたハーフパイプ状の地形の中も歩きました。 様々な地形を歩くことで、雪山の歩行技術を身に着けて頂きます。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!
またのご参加を心よりお待ちしております。











Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2017.2.26 雪上訓練

森林限界を超える雪山登山は、あらゆる登山形態の中でも特に危険度の高いアクティビティです。
他のカテゴリーではロープによる安全確保が比較的行いやすかったりしますが、雪山登山では確実な支点が設置しにくい傾向にあり、安全確保が難しい傾向にあります。
だからこそ絶対に滑落しない様、歩行技術をしっかりと身につけたり、初動停止技術を体に叩き込む必要があります。
Kuri Adventures の雪上訓練は、超実践的な訓練内容でお送りしています。
雪上訓練の様子をブログにまとめてみました!

雪山登山はあらゆる登山カテゴリーの中でも特に危険なアクティビティです。
なんせ岩や氷、木などが全て雪に埋まってしまい、強固な支点を設ける事ができません。すなわち、ロープによる安全確保が難しい登山なのです。
もちろんスノーバーを使った支点構築やスタンディングアックスビレイなどの確保方法もありますが、そのシステム構築には時間がかかります。実際に運用できるのは、本当に危険な箇所だけになります。
しかし森林限界を超えた雪山登山では、全体的にクラストしていればそのほとんど全ての場所が危険箇所となります。
転倒すれば、多くの場所で滑落のリスクを伴います。
雪山登山を行う上で重要な事は、絶対に転倒しない確実な歩行技術を身につける事と、そして万が一転倒した時に備えた初動停止技術を身につけることです。
滑落停止技術の訓練も行いますが、実際に滑落した場合に滑落停止技術で滑落を止めることは極めて困難です。
こんなに滑落停止技術の練習をするのは日本くらいなものらしく、ヨーロッパなどでは滑落しない技術の習得を重視している様です。
転倒したその瞬間にピッケルのピックを雪面に刺す事で、流れそのものを止めることができます。
ふいに転倒した際に初動停止が行えるよう、徹底的な練習を行います。
また万が一の滑落に備えた滑落停止訓練、ロープによる安全確保技術もお伝えしております。
雪山登山を楽しむ上で、しっかりと技術を習得することがとても重要です。
是非一度ご参加頂き、安全な登山技術を身に着けて頂ければ幸いです。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!
またのご参加を心よりお待ちしております。









登山技術講習へのご参加はこちらから!

雪上訓練
森林限界を超える雪山登山は、全ての登山カテゴリーの中でも特に危険度の高いアクティビティーです。滑落を絶対に起こさないよう、確実な歩行技術や初動停止技術を徹底的に訓練します。また滑落停止技術、ロープによる安全確保技術も学びます。
安全な雪山登山に備え、是非一度しっかりと学習しておきましょう!
料金:12,000円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2017.2.25 懸垂下降技術講習

懸垂下降技術講習を行いました。
登山は登りより下りの方が技術的に難しいものです。特に急峻な斜面では滑落のリスクも伴います。
懸垂下降技術を身につけると、そんな危険箇所も安全に下ることができます。それどころか、完全にオーバーハングした空中ですら下ることができる優れた技術です。
しかしその一方で、クライミング中の死亡事故ワースト1なのもまた懸垂下降だったりします。
確実で安全な技術を身につける必要があります。

懸垂下降技術講習を行いました。
登山は登りより下りの方が技術的に難しいものです。特に急峻な斜面では滑落のリスクも伴います。
懸垂下降技術を身につけると、そんな危険箇所も安全に下ることができます。
それどころか、完全にオーバーハングした空中ですら下ることができる優れた技術です。
しかしその一方で、クライミング中の死亡事故ワースト1なのもまた懸垂下降だったりします。
確実で安全な技術を身につける必要があります。
Kuri Adventures の懸垂下降技術講習では、バックアップを設けた懸垂下降をお伝えしています。これにより、万が一途中で手を話してしまっても、墜落せずにその場でバックアップシステムが制動してくれます。
また懸垂下降を行う上で絶対に身に着けておかなくてはならない技術に、登り返しがあります。
懸垂下降を始める支点からは、ロープが地面まで届いているか確認できないことがほとんど。懸垂下降をはじめてからロープが地面に届いていないことに気がついた場合、再度支点を作れるポイントまで登り返す必要があります。
複雑なシステムなので、見よう見まねでは覚えにくい技術です。
この手の技術は一手のミスも許されないものが多く、確実な学習が求められます。
多くの方により安全な懸垂下降技術を学んで頂くことで、山の安全に貢献できればと考えております(^^)
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!







登山技術講習へのご参加はこちらから!
懸垂下降技術講習
安全性が高い懸垂下降技術に加え、懸垂支点についての注意点や懸垂途中からの登り返しなど、1日かけて徹底的に懸垂下降を学ぶ講習です。
クライミング死亡事故ワースト1の技術が懸垂下降です。しっかり学ぶ必要があります。守りの技も同時に覚え、懸垂下降マスターになりましょう!!
料金:9,250円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
アイススクリュー - 長さと本数 -

アイスクライミングを始める時、悩ましいのがアイススクリューの購入。
いろいろな長さがあり、どれを何本買ったら良いのかわからないものです…。
もちろんどんな時期にどこを登りたいのかなどでも変わってくるものですが、個人的にこのくらい用意するのが良いだろうと思われる目安を指針として示してみたいと思います。
これが必ずしも正解とは限りませんが、しかし1つの答えでもあります。
これを参考に揃えはじめ、自分なりのスタイルを築いて頂ければと思います。
僕のスタイルは、安全重視型な内容となります。

.
.
アイススクリューの本数と長さ
アイスクライミングはほんの一昔前まで、一部の"変人"だけの遊びでした。
なんせ中間支点の設置が大変で、アイススクリューなんてものは無かったわけですから。アイスアックスにセルフをとってぶら下がり、ハンマーで氷に釘の様なものを打ち込んで登っていたわけです。そんな頭のぶっ飛んだ遊び、一般化する日が来るなんて誰も思わなかったわけです。
しかし近年、アイスクライミングはかなり一般的なウィンターアクティビティとなりつつあります。
一番大きな要因はアイスキャンディーなどの人工アイスゲレンデの普及でしょう。安全な場所でトップロープで、誰でも楽しくアイスクライミングが楽しめる場が、確実にアイスクライミング人工を増やす役割を担っています。
そしてもう一点、アイススクリューの進化が挙げられます。
この10年ほどで格段に良くなったアイススクリューのお陰で、アイスクライミングにおける中間支点の設置は大幅に手軽になり、しかも強固で確実性も高いものになりました。
アイスクライミングのフリー化など不可能に近い話だったわけですが、現在ではアイススクリューの進化によりフリーで登ることは決して難しいことではなくなってきています。
今回はそんなアイススクリューについてお話します。

.
アイススクリューには様々な長さがあります。
凡そ、10cm~22cm程度まで、4~5段階の長さがあります。
この為、最初にアイススクリューを購入する時にどれを購入したら良いのか悩んでしまいますね…。
登るルートや地域、時期などによって氷の厚さや状態が変わるので一概になんとも言えませんが、個人的には短めのものから中程度の長さのものを中心に中間支点用としています。
また支点構築用として中程度の長さのものと、V字スレッド用として一番長いものを1本持つようにしています。
これは僕のアイスクライミングのスタイルによって、この様な長さの選択になっています。
僕の場合、西上州や南アルプスエリアのアイスクライミングルート。特に冬期沢登り的な長いナメ滝を中心とするような渋めな登攀を好みます。スポーツとして高難度を目指すと言うより、冬の静まり返った沢の遡行を静かに楽しむ事に重きを置いており、高難度な登攀を楽しむことは求めていません。
この為、氷は比較的丈夫で安定しているものの、全体的な厚さはさほど無い場合も多く、短めのアイススクリューである必要性があります。
仮にこれが高難度なアイスクライミングを目的に、細い氷柱の集合体の様な滝を登る様な場合には、長いアイススクリューでより強固な中間支点を作る必要性が出てきます。
使用目的に併せて選択していくことが大切です。
以下に、僕個人が用意しているスクリューを紹介していきます。

.

中間支点用に、短めのものから中程度のものを、6~9本用意しています。
10cm × 3本、13cm × 3本、17cm × 3本の中から、ルートによってどれを持っていくかを選択します。
念のため、最低でも6本持っていきます。50mロープを目一杯出す様なルートでは、9本全てを持っていくことも多くあります。
一見すごく多そうに感じますが、50mロープ目一杯出すことを考えると、これでも5mに一本の計算になります。実際には両端をエイトノットで結んだり、下部の傾斜が浅い部分もあるわけですが、それでも際どいバーティカル部分ですら3mに1本も打てない量です。安全を重視するのであれば、この程度はあっても良いのかなと思います。

支点構築用に中程度のスクリューを2本、又は4本用意しています。(17cm)
1ピッチで登れる滝しかない場合には1セット、マルチピッチになる場合には2セット用意しています。
スクリュー2本に対し、120cm のナイロンスリングと安全管付きカラビナを1つセットにして持っておき、すぐに支点構築が行えるようにしておきます。

懸垂下降支点や終了点、スクリューが足りなかった場合の中間支点にV字スレッドを作ることがあります。この為、V字スレッド作成用として長いアイススクリュー1本とフックツールが必要となります。
V字スレッド用のスクリューは他の用途には使用しません。
切り札となる1本なので、いつでも必ず持っていきます。
V次スレッドを作るにはスリングが必要です。
必ず自由に使える状態のスリングを2本と、捨て縄にも使えるよう 7mm × 7m の細引きとナイフも必ず携行しています。
ここでお伝えしている内容はあくまで目安として考えて下さい。
ご自身の登攀スタイルに併せて、適切な長さと本数をご用意頂くことが大切です。
またアイスクライミングのリードは安易に行わないようにしましょう!
氷の状態や形状を見抜く力や落ち着いて中間支点を設置する能力が求められます。フリークライミングのゲレンデでの絶対的なリード経験、沢登りや岩稜登攀における、自然地形の中での支点構築経験、アイスクライミングのフォロー回数をたくさん積むことによる氷を把握する能力などを十分に養った上で、トップロープ併用でのスクリュー打ち込みなどを経て、傾斜の浅いナメ滝でのリード経験から十分に段階を経て行いましょう。
遊びで死んじゃ馬鹿らしいですからね!
皆様の安全登山にお役立て願えれば幸いです(^^)
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

はじめてのアイスクライミング講習
まったくの未経験から学ぶアイスクライミング教室です。
基本となるアイスアックスの打ち込みやアイゼンの蹴り込み、アイスクライミングのムーヴ、クライミングやビレイにおける注意点などを学習します。
料金:12,000円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
トイレットペーパー登山カスタマイズ!

登山の隠れた必須アイテムにトイレットペーパーがあります。
山のトイレにはトイレットペーパーがないこともありますし、トイレが無い山域では当然そこらで用を足さなきゃなりません。また食事後の鍋の拭き掃除や万が一のビバークにおける焚き火の焚付など、様々な用途に使います。
そんなトイレットペーパー、どうやって持っていっていますか?
芯を抜いて中央から取る方法ではトイレットペーパーが捻れながら出てきちゃうし、トイレットペーパーが潰れてスムーズに出てこなくなる場合もあります。
しかしこの方法なら、そんな悩みから解決されます!

.
.
便利なトイレットペーパーの携行方法
登山に欠かせない装備の一つにトイレットペーパーがあります。
山のトイレにはトイレットペーパーがない場合も多いですし、トイレがない山域ではそこら辺で用を足すしかありません。
また食事の後の拭き掃除や万が一のビバークにおける焚き火の焚付など、実に様々な用途に使います。
よくあるトイレットペーパーの携行方法に、真ん中の芯を抜いてそこからトイレットペーパーを出す方法が使われます。しかしこの方法だと、トイレットパーパーがぐるぐるにねじれて出てくるので今ひとつ使いにくかったりします。
僕は以前より芯に紐を通して首からぶら下げて使ってましたが、これもバックパックの中でトイレットペーパーが潰れてしまうと、スムーズに紙が出てこなくなります。
そこでトイレットペーパーの芯を潰れないようにするアイデアを思いつきました!
この方法ならバックパックの中でトイレットペーパーが潰れてしまうこともなくなるし、実にスムーズに紙が出てくるようになり使いやすいです。
では、作り方を見てみましょう!

まずはホームセンターに行き、塩ビパイプのコーナーを探します。

トイレットペーパーの芯にギリギリ入るパイプを買いましょう。

トイレットペーパーの芯の長さより、少し短めの長さにパイプを切ります。

パイプを中に入れ、トイレットペーパーの芯を少しだけ内側に向かって潰し、パイプが芯から出てこないようにします。

続いてジップロックの大サイズを用意し、底辺の角2箇所をハサミで切り取ります。

ジップロックにトイレットペーパーを入れます。

ジップロックの底辺の穴から紐を入れ、パイプの中に紐を通し、反対側の穴から出します。紐を輪になるように結びます。
細引き紐などでも構わないと思いますが、僕はトイレットペーパーの交換が楽なようにプラスチックバックルを取り付けたナイロンテープにしています。

首から下げて使うことが出来ます。
ビニール袋に入っているので防水性も高く、塩ビパイプが入っているのでスムーズに紙が出てくれます。
作るのがちょっと手間ですが、超快適にトイレットペーパーが使えるようになります。
もうこれは、トイレットペーパーの革新的アイデアだと思っていますww
山登りと切っても切れない関係であるトイレットペーパー。
かなりオススメなアイデアなので、是非お試しあれ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
ビバーク技術 - ビバークマットの作り方 -

ビバークの要となるのは、地面からの断熱です。
山の中で急遽ビバークしなくてはならなくなっても、地面への放熱を防ぐことができればしっかりと睡眠を取り、翌日に向けて体力を回復させる事ができます。
可能であればスリーピングマットを持っていきたいところですが、日帰りや小屋泊の登山、スピードを要求されるアルパインクライミングなどでは少しでも荷物を軽くしたいもの。かと言って、軽いフォームマットなどはなかなか嵩張ります。
そこで考案したのが栗山式ビバークマット!
これなら軽く、あまりバックパックの収納スペースを犠牲にせず持ち運べます。

.
.
栗山式ビバークマットの作り方
野外で寝る時、重要となるのが地面との断熱です。先日、ツェルトビバークの記事でもご説明させて頂きましたが、ビバークにおける最大の注意点は低体温症。そして低体温症を防ぐには、雨風から身を守るシェルターに加え、地面からの断熱が重要であるとお話致しました。
この記事では小枝を集めて地面からの断熱方法をご説明しましたが、できればやっぱりスリーピングマットもほしいもの。
スリーピングマットがあれば小枝などの手に入りにくい森林限界以上の山域や積雪期でも安心です。もちろん地面からの断熱ができる小枝などのを敷き詰めた上でビバークマットを使えれば、実に快適に眠ることができるでしょう。
しかしスリーピングマットを持っていくのにはいくつかの問題点があります。
一般的に多く使われているインフレーターマットは重量が重く、日帰りの登山に持ち出すのには現実的ではありません。
エアーマットと言う選択もありますが、これもまた決して軽くなく、また冬は断熱性能に問題があります。
重量的に軽く、破損のリスクがなく、断熱性にも優れているとなるとフォームマットとなりますが、今度はその体積に問題があります。あまりに大きな収納サイズに、とても日帰り登山に持っていこうと言う気にはなれません。
ところが、ふと良いアイデアを思いついちゃいました!
この方法なら、フォームマットをさほど嵩張らずに持っていくことが可能です。

まず半身用サイズのフォームマットをバックパックの中めいっぱいに広げます。
サイドコンプレッションベルトなども最大まで緩めておきましょう。

2重に重なる部分が大幅にバックパックの収納スペースを奪います。
二重部分を切り落とすので、きっちり一周となる部分に印をつけます。

バックパックからマットを取り出し、先程印をつけた部分からまっすぐマットを切ります。40Lのザックの場合、大凡80cm程度のマットと40cm程度のマット2つに切り分けられます。

ポンチを使って、マットに穴を開けて行きます。
マットは柔らかいので、手で強く押し付けながらねじ込めば簡単に穴が空きます。

短い方のマットの長辺側一辺に、均等に6ヶ所穴を開けます。軽量化を優先させたい場合は3箇所でも良いかも知れません。
定規などを使い、均等に穴を開けていきましょう。
続いて穴の位置が同じになるように、短いマットを重ねながら、長いマットにも穴を開けていきます。長いマットは短辺側の各両辺に穴を開けましょう。
全部で18箇所に穴を開けます。

開けた穴にハトメを止めていきます。
ここでは8mmのハトメを使用しました。

3mm × 1m のアクセサリーコードを2本。
3mm × 50cmのアクセサリーコードを6本用意します。

短いマットの真ん中2つのハトメ、長いマットの片側一辺の左右各2つ(計4つ)のハトメ、それぞれにガースヒッチで50cmのアクセサリーコードを取り付けます。
続いて長いマットの反対側の辺の真ん中2つのハトメに、1mのアクセサリーコードを取り付けます。

使用時は裏返し、長いマットの4つのアクセサリーコードと、短いマットの2つのアクセサリーコードを使って、切り離したマットを繋ぎます。
裏面に結び目を作ることによって、就寝時に背中へのあたりを減らせます。
すべて結んだら、マットを表に返します。

スタッフバッグに、寝る時に着ない衣類を入れます。
長いマットの一辺に取り付けた長いアクセサリーコードをつかってスタッフバッグを固定します。これを枕として使用します。

これで、頭から膝辺りまでの断熱が可能となります。
足元には空にしたバックパックを横向きにして使うことで、全身を覆うマットとして使用できます。
地面が雪などで特に冷える場合には、短いマットを折り返してお尻から腰あたりをマット2重状態にし、保温力をアップさせます。足元はバックパックを縦向きに使います。

携行時は長いマットの短辺同士を繋ぎ止め、筒状にします。

これをバックパックのインナーフレームとして使用します。
こうすることで最低限の容量低下に留められます。また外部からの衝撃からバックパックを守れたり、バックパックの防水性が高められたり、夏は内部の温度が上がりにくく、冬は食べ物などが凍りにくいという利点もあります。
この内側にゴミ袋を入れ、荷物の防水を行います。

短い方のマットは丸めてアクセサリーコードで止めておきます。

細い筒状にしたマットを、バックパックのサイドコンプレッションベルトに固定して携行します。
雪の上での休憩時や雨上がりの休憩時に、座布団として使用します。
スリーピングマットを持っておくことで、ビバーク時の快適性が明らかに向上します。
この方法であればさほどバックパック容量を犠牲にしませんし、フォームマットの半身用サイズであれば重量も負担になりません。(ものにもよりますが、150g 〜 300g程度です。)
低体温症の予防や進行防止にも、スリーピングマットの存在は欠かせません。特に冬の登山では超重要な装備となります。
ちょっと作るのに手間がかかりますが、ご興味ある方は作ってみては如何でしょうか?
この情報が皆さまの安全登山にお役立て願えれば幸いです。
しっかりと準備しておきましょう!
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

ビバーク技術実践訓練
いざ山の中でビバークしなくてはならない時を迎えてしまった時、実際に一晩生き延びることはできますか?その為の知恵や経験はありますか?
事前に学習し、実際に体験しておくことで、万が一のビバークに備えましょう。
料金:13,880円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
最強のダウンジャケット" THE NORTH FACE ヒマラヤンパーカ "

冬季登山で最も恐ろしいリスクに低体温症があります。万が一を考えた時、冬の防寒着はまさに生命線とも言うべき最重要装備の一つであると言えます。
本来登山における装備は少しでも軽くするべきですが、個人的に冬の防寒着はオーバースペックで構わないと考えています。
防寒着は停滞時に使用するものであって、行動時はまず着用しません。だからこそ、絶対の保温力は正義です。
THE NORTH FACE のヒマラヤンパーカは、まさに最強のダウンジャケット!
厳冬期の登山を支える頼もしい相棒です。

ノースフェイス ヒマラヤンパーカ
~ 最強のダウンジャケット ~
冬季登山は夏山に比べて大きなリスクがあります。滑落、ホワイトアウト、雪崩など、そこに訪れる人の命を簡単に奪います。
そしてこれらのリスクとも常に絡む、冬の登山の最大のリスク。それは低体温症です。
深部体温が低下する事で生命維持に関わる生理現象に支障をきたします。
そのまま放置すれば、比較的短時間で命を落とすことになります。
最初に掲げた滑落、ホワイトアウト、雪崩などに遭った結果、行動不能になり、そのまま低体温症を起こすケースが多くあります。人は行動する限り発熱しますが、停滞状況になれば瞬く間に体温が奪われ、低体温症に陥ります。
登山では軽量化が原則ですが、こと冬の防寒着に関してはオーバースペックでかまわないと個人的には考えています。
そもそも防寒着を行動中に着ることはまずありません。
ビレイ中であったり、昼食時であったり、テントの中であったり、基本的に停滞時に着用するものです。
オーバースペックだからと言って、冬山の停滞時に着て暑すぎると言うことは殆どありません。

.
今シーズンより新たに装備に導入したのが、THE NORTH FACEのヒマラヤンパーカ。
8,000m峰における行動着として開発されたジャケットで、−40℃の環境下で行動するのに適した保温力を備えています。
あの三浦雄一郎大先輩がエベレスト登頂の際に着ていたジャケットでもあります。
日本では完全にオーバースペックな気もしますが、−40℃はあくまでも行動着として着用した場合。
一般的な厚さのダウンジャケットだって、日本の冬山では着て歩くことは殆どありません。
停滞時に着用することを考えれば、使用状況によってはまったくもってオーバースペックとは言い難い。
正直、このくらいが適正な場面もけっこうあります。
例えばアイスクライミングやアルパインクライミングにおけるビレイ時。動かない時間がどうしても長くなります。
また僕達職業登山者にとっては、厳冬期のシビアな状況でなくても、長時間のビレイを余儀なくされる場合が多々あります。
この様な場面では、圧倒的保温力を持つジャケットがあると、とても快適に過ごせます。(それでも寒い時もある)
それは結果として体力を温存することになり、安全な登山に繋がります。
絶対的な保温力を持つ防寒着を携行するということは、就寝時の寝袋をもっと軽いものにすることもできます。
確かに一般的なダウンジャケットの3倍近い重量と倍近い収納性はネックですが、テント泊の時に関しては結果としてあまり差がない状態となります。むしろ起きている時間の快適さたるや、一度使うとやめられなくなりますw

フロントはダブルファスナー仕様となっており、ファスナーが当たる部分はナイロンテープで補強されています。
この為、ファスナーの動きが実にスムーズ!まったく噛みません。
厳寒での仕様において、ファスナーの動きがスムーズなのはとても大切なことです。
またファスナーが位置を変えて2重に付けられており、ダウンチューブもそれぞれに設けられています。この構造により、寒気の対流を徹底的に防いでいます。

胸のポケットの中には、もう一個ファスナーが付いています。このファスナーは、ジャケットの内側へと繋がっています。
ジャケットのフロントファスナーを開けなくても内部にアクセスできるので、ジャケットの内側にあるメッシュポケットや中間着の胸ポケットに直接ものを出し入れすることができます。

左胸ポケットには小さな穴が空いています。ここは無線機のアンテナを通すものだと思われます。
胸ポケットに入れておくことで、バッテリーの電圧低下も防げそうですね!

表面素材にはゴアウインドストッパーが採用されており、高い防風性と透湿性が両立されています。
ゴアウインドストッパーに高い防水性はありませんが、極めて高い撥水性があります。冬ならこれで十分!
さらに表面生地への縫い目を極力減らし、溶着にて仕上げられています。
針穴からの空気の対流を防ぐことで、コールドスポットがほとんどできないような工夫がなされています。

首周りにダウンチューブが設けられ、寒気が首元から入り込まないようになっています。もはや寝袋のようですw
人間は体温の30%以上を頭から放熱していますが、このジャケットはフードにもたっぷりダウンが封入されています。
間違えなく、3シーズン用の寝袋より保温力が高いと思います!

内面素材にも強力な撥水処理がされているようです。
高所登山では行動着として着用するジャケットですが、それ以外の使用では原則的に停滞時しか使用しないと考えられます。
ハードシェルの上にそのまま羽織る事を考えての撥水処理だと思います。これはありがたいですね!
胸の内側にはメッシュのストレッチ素材のポケットが両側に設けられています。このポケットには、反対側の胸の外ポケットからアクセスできます。曇ったゴーグルや湿ったインナーグローブを乾かすのに良さそうですね。
これまでは化繊に強い拘りを持っていました。
過去にダウンジャケットに水分を含み、完全にぺしゃんこになってしまった経験が2度あります。
水没させるなどの致命的なミスをした訳でなく、長時間着用後にバックパックに入れておいたらそうなっていました。
これは着用時の汗などが一番外側の生地の内側で結露していて、それがテントや山小屋の中で溶け出した事が原因だと考えられます。些細なミスですが、事態は深刻です。
それ以来、防寒着は化繊の中綿がベストであると考えていました。
しかし近年では、防水性・撥水性の高い表面生地を使ったり、ダウンそのものに撥水処理をすることでこの問題が解決されてきました。ヒマラヤンパーカもその一つで、ゴアウインドストッパーを表面に使い、撥水処理されたダウンが使用されています。
さらに前身胴体部分に至っては、内側が化繊中綿とポリエステルの組み合わせになっています。
これによりダウンのロフトが落ちてしまうリスクを大幅に軽減しています。
全ての登山者におすすめとは言い難い商品ではありますが、より安全に、より高難度な登山を目指す方には良い相棒になるかも知れません。最強のダウンジャケットを持つということは、確かな安心があります。
今シーズンから、僕はヒマラヤンパーカを持って雪山に出かけようと思います^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
ビバーク技術 - 地面の断熱方法 -

登山を行っていると、時にビバークに追い込まれることがあります。
捻挫して下山が大幅に遅れた、ちょっとした道間違えで時間をロスした、初参加のパーティーメンバーが想像以上に遅かった、怪我をした仲間と共に翌朝の救助まで待機しなくてはならない。
この様な事態は誰にでも起こり得ることであり、全ての登山者に可能性があります。
ビバークで最も重要なのは保温です。ツェルトで雨風を避ける話は良く耳にすると思いますが、それと同時に大切なのが地面の断熱です。
森で手に入る素材で、ビバーク時の床断熱方法をお伝えします。

.
.
ビバーク時の地面からの断熱方法
登山におけるビバークは特別なことではなく、全ての登山者に起こり得る事です。
怪我や道迷いなどで大幅に時間をロスしたり、始めて参加したメンバーが想像以上にペースが遅かったり。山の中で日が落ちてしまうこともあります。
山慣れしたメンバーで安定した登山道を歩く場合なら、ヘッドライトでの夜間歩行も考えられます。
しかしそこが岩稜であったり、沢の中であったりした場合には、夜間行動は極めて危険。また下山までにまだ何時間もかかる場合にも、夜間行動は避けた方が無難でしょう。
この様な場合には、山の中でビバークを行う必要があります。
ビバークにおいて最も重要なのが保温です。
温かいテントや寝袋、マットを持っているテント泊登山ならともかく、日帰りや小屋泊の場合には最低限の装備しか持っていないことが多いと思います。
この様な状況でのビバークで特に注意しなくてはならないのが低体温症です。
ツェルトで雨風を避ける話は聞くと思いますが、それに加えて地面からの断熱もかなり重要です。
風を避けたり放射冷却の影響を小さくすることができるツェルトの中にいれば、空気による熱伝達のロスはかなり小さくすることができます。しかし地面への熱伝導はもっとずっと大きなロスになります。
そこでビバークを行う際に、まず地面からの断熱処理を行わなくてはなりません。
今回はこの断熱方法の一例について紹介します。

まず森の中で小枝を拾います。
できれば枝分かれしている部分は全て折り取り、一本の棒状にした方が良いです。
大凡人が寝るスペースくらい縦方向に枝を敷き詰めたら、引続き横方向に枝を並べていきます。
これを繰り返し、地面から5cm程度高さを出しましょう。

続いて落ち葉をたっぷりと枝の上に乗せ、足で踏み固めます。
人が寝てもふんわりとした感触になるまで積み重ねましょう。

その上にツェルトを設営します。
まずツェルトの床部分をつなぎ合わせます。小枝のベッドが覆われるような感じにツェルトを置き、綺麗な長方形になるようにペグダウンします。
可能であればグランドシートも用意しておくと、枝によりツェルトに穴が空いたり、落ち葉に隠れたダニの被害を少なくすることができます。
(グランドシートは、雨天時に焚き火を起こす場合や低体温症対策のラッピング時、冬季であれば雪洞の入り口を塞いだり、負傷者を運ぶための担架を作ったりと、いろいろ役立ちます。できれば用意しておきましょう。)

最後にツェルトを設営して完成です。
落ち葉が多い季節ならツェルトの中を落ち葉で埋め尽くすようにして眠ると、氷点下に差し掛かるような気温の中でも眠りにつくことも可能です。
そうでない季節なら人が4人位入り、背中合わせに寄っかかり合いながら座れば氷点下でもわりと暖かく過ごせます。比較的温かい時期なら、この断熱方法で眠ることもできます
限られた装備の中で厳しい夜を過ごすこととなりますが、可能な限り睡眠はとったほうが翌日の行動に影響が出にくくなります。
ここでお伝えしている技術は、ビバークにおけるほんの一部の技術の紹介に過ぎません。
安全にビバークを行うためには、定期的に安全な場所でビバークを経験しておくことが大切です。
例えば車でアクセスできるキャンプ場など、いざという時に避難できる場所や十分な防寒装備を用意した上で、実際のビバークを想定した訓練を行っておきましょう。
またビバークは安易に判断しないようにしましょう。
低体温症を引き起こすリスクや睡眠不足による行動中の負傷リスクなど、ビバークそのものにもリスクがあります。
特に冬期にはこのリスクが極めて高くなります。
もちろん、日没後でも安全に下山できると判断した場合を除いては、ビバークを早めに決断することも大切です。
ビバークは登山の一部であり、限られた人にしかやってこない状況ではありません。誰にでも起こり得るものです。
事前に様々なケースを想定し、持つべき最低限の装備を常に用意しておきましょう。
またどのような装備が必要なのかを判断するためにも、やはり訓練は大切です。
この情報が皆さまの安全登山にお役立て願えれば幸いです。
しっかりと準備しておきましょう!
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

ビバーク技術実践訓練
いざ山の中でビバークしなくてはならない時を迎えてしまった時、実際に一晩生き延びることはできますか?その為の知恵や経験はありますか?
事前に学習し、実際に体験しておくことで、万が一のビバークに備えましょう。
料金:13,880円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
パタゴニア " ハイブリッド・スリーピング・バッグ "

パタゴニアが2016年に発表した新しいレイヤリングコンセプト " ハイアルパインキット "。着ているもの全体をシステムとして捉え、組み合わせることで最大限の機能を発揮するコンセプトとなっています。
その中で、寝具に位置するのがハイブリッド・スリーピング・バッグです。
半シュラフに上半分だけシュラフカバーを取り付けたような商品で、厚手のビレイパーカーなどと併用することで必要最低限の保温性を保ちつつ、最大限の軽量化を望める優れた道具だと感じます。
緊急のビバーク用に携行するのに、ギリギリ許容できるサイズと重量でもあります。

ハイブリッド・スリーピング・バッグ
~ パタゴニア・ハイ・アルパイン・キット ~
登山装備の中でも、特に大きく思い存在である寝袋。当たり前の話しですが、行動中にはまったく使うことがない存在です。
それでも快適な睡眠は連続した登山を継続する上で欠かすことの出来ない、とても大切な回復の時間です。
そんな回復の時間を支える重要な装備がビバークギヤであり、登山の成功の鍵を握る重要な道具です。
また登山における恐ろしいトラブルの一つに低体温症があります。
短い時間で傷病者の命を奪う低体温症に対しては、素早い加温と確かな保温が求められます。これまでもツェルトやビバークマット、プラティパス、ジェットボイル、予備の水などを用意しておりましたが、保温に関してはやや脆弱でした。
それでも日帰りの登山に寝袋まで持参する事が、重量的、容量的な問題からなかなかできずにおりました。
2016年にパタゴニアが掲げた新しいレイヤリングコンセプトに、ハイ・アルパイン・キットがあります。
これは着用する衣類各々が最高の製品でありながら、組み合わせて使うことによって最大のパフォーマンスを発揮する組み合わせを提案しています。その中に、寝具としてハイブリッド・スリーピング・バッグがあります。
これまでの常識を覆すアイデアで、大幅な軽量化、小型化に成功した優れた寝袋が販売されました!

.
ハイブリッド・スリーピング・バッグは、ビレイパーカーなどと組み合わせて使うことを前提に開発されています。
長時間のビレイを伴うアルパインクライミングでは、保温力の高い防寒着を用意していきます。
行動中はまったく使用できないほどの保温力で、基本的に停滞時間しか着用することはありません。
止まると動くがはっきりとした登山では使いやすい選択です。
ハイブリッド・スリーピング・バッグは、下半身のみの半シュラフに、上半身部分をシュラフカバーの様な状態にした商品。
ビレイパーカーを始めとし、持っている衣類の全てを組み合わせることで睡眠に必要な最低限の保温力を維持しつつ、最大限の軽量化を行うことができるシステムです。
実に良く考えられた道具だと思います。
パタゴニアのハイ・アルパイン・キットの防寒着にあたるグレードⅦ・ダウン・パーカと組み合わせた場合、最大で−12℃まで対応しているとのこと。
着替えとして持っているアンダーウェアを重ね着し、中間着やアウターシェルを全て着込み、バラクラバやニットキャップを装備し、冬季用手袋を装着する。持っている衣類を全て総動員すれば、実際にギリギリ−12℃まで対応できそうな程度のボリューム感です。(モンベルの#2くらい?)
個人的に使っている防寒着はBlack Diamondのビレイパーカーであり、グレードⅦ・ダウン・パーカより少し保温力は下がりそうですが、それでも−10℃くらいまではなんとか耐えられるでしょう。
快適な睡眠が得られる使用温度は0℃といったところでしょうか?
これは無雪期であればツェルトなどのシェルターを、積雪期であれば雪洞を使った状態で眠れるギリギリの設定。
極限まで削ぎ落とした、攻めたコンセプトであることが見えます。
アルパインクライミングにおける軽量化としてももちろんですが、収納サイズは大凡ジェットボイルくらいの大きさで、重量も実測で541gと、万が一のビバークに備えた緊急用装備として携行するのにもなんとか許容できるサイズと重量です。
ツェルトやバーナーなども大変軽量化された現代の山道具は、もはや幕営に必要なギリギリ最低限の道具をいつも持ち歩けるほどに進化しています。
ビバークとは、予め想定されたものと、予期せぬ急なものとがあります。究極のビバークギヤとは、その両方を満足させるもので無くてはなりません。
予め想定されたビバークでなんとか快適に眠れるスペックを持ちながら、予期せぬビバークに備えていつも持ち歩ける。
その両方を兼ね備えた、絶妙なバランスに仕上がっています。

.
また温かいシーズンにおいても、薄手の防寒着と組み合わせる事でかなり幅広く使用できると思われます。
どのシーズンでも、それぞれの時期に併せた最適な衣類を全て着込む事によって快適な睡眠が得られると思います。
もちろん真夏の最盛期の利用には暑いかもしれませんが、そもそもその様な条件では防寒着一枚で事足りる事も多いでしょう。
ダウンが腰から下しか入ってないくせに普通のダウンシュラフと同じくらいの値段がしちゃうのはさすがのパタゴニアですが、幅広いシーズンで使うことを想定すれば決して高い買い物では無いでしょう。(それでも4諭吉円はちと痛いが…(;´Д`))
何よりも、何時でも快適に眠れる環境を持ち歩くことができると言うのは、この上ない絶大な安心感となります。
ハイブリッド・スリーピング・バッグ、一考の価値がある道具かもしれませんよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
おすすめのアプローチシューズ " アディダス テレックススコープ "

クライミングの時、岩壁までの短い道程を安全に歩く事を目的に開発されたアプローチシューズ。一般に、岩でのグリップ力を徹底的に高めたソールを使用しています。
アディダスのテレックススコープはちょっとコンセプトが違うのか、もう少し硬めのシャンクにブロックパターンのソール。ゴアテックスブーティーを搭載。
絶対的な岩でのグリップ力を削って、アウトドアでの使用感を高めています。
この事で純粋なアプローチシューズとしての価値を低く見る方も居るようですが、一方で違う目的に使った場合は最強の一足となります。
岩稜を歩くには、こいつ以上の相棒はなかなかいません!!

アディダス テレックススコープ
~ 岩稜で最強のアプローチシューズ ~
アプローチシューズと呼ばれる靴をご存知でしょうか?
クライマーが岩場までの道程を行くために使用される、まさにアプローチのための靴。トップロープ支点を作ったり、足場の悪い、滑りやすい岩の上でのビレイなど、岩の上で高いフリクションを持つ靴が重宝されます。
クライミングシューズを作る各メーカーがアプローチシューズを販売していますが、中でもファイブテンのアプローチシューズは人気です。圧倒的なフリクション性能を持つステルスC4ソールが魅力です。
近年ではこの絶対的なフリクション性能が注目され、岩稜登山などに多く使用されるようになってきました。
しかし元々登山を目的として作られている靴ではないので、多くの問題が発生します。
例えば多くのアプローチシューズは、岩の上でのフリクションを最重視して作られています。
クライミングシューズのソールになぜデコボコがないのか?
それは岩との接地面積を少しでも多くすることで、より大きなフリクションを得るため。
アプローチシューズもこのコンセプトに沿って、靴の裏の接地面積をなるべく多くとるデザインで作られています。
対岩の場合、ソールと地面はヒステリシス摩擦と呼ばれる、ゴムの復元力で岩のデコボコに食い込む様にグリップしますが、対土の場合は機械摩擦と呼ばれる、土に突起が埋まって噛み合うことで生まれる摩擦でグリップします。
つまり、土に対しては平らなソールパターンは相性が悪いことになります。
アプローチシューズを登山で使う場合に、土のヌメったところで極端に弱いといった弱点が露呈します。

.
ところが、アプローチシューズの新参者メーカーがおかしなものを作ってきました。
アディダスのテレックススコープは、ソールパターンが見事にブロックパターン。
クライミングで重要になるつま先部分と、岩場歩きでグリップ力が欲しいかかと部分に関してはクライミングゾーンを設けていますが、それでもベタッと足裏を岩に押し付けるような使い方では、ファイブテンのガイドテニーなどと比べると半分程度しか無いかもしれません。
この為、アプローチシューズとして使いにくいと悪評をつける方も居るようですが、僕はこの靴がとても気に入っています。
デコボコが多いと言うことは、一方で土でのグリップ力が高いということでもあります。
使い方次第では、この靴の特性が大きく味方します!
僕はこの靴を、主に岩稜登山で使っています。特に西上州あたりの低山岩稜登山において、圧倒的な信頼を寄せています。
岩場でのフリクションは確かに大切ですが、だからと言って土の上でのグリップ力を犠牲にしても良いのかと言えば、決してそんなことはありません。少なくとも日本の登山シーンでは、岩の上より土の上を歩く時間の方がよっぽど長いんです。
じゃあこの靴は土に強くて岩に弱いのかと言うと、決してそんな事ありません。
だってこの靴のソール、実はファイブテンのステルスC4ソールなんですもの!
確かに足をベタッと置いた時のフリクションには劣るのかもしれませんが、本当に高いフリクションが必要になるのはつま先で岩を捉えている時。
この部分にはしっかりと接地面積が確保されています。
もしかしたらガイドテニーなんかよりも接地面が多いかも?
実際にこの靴を履いて、クライミングゲレンデで 5.10a くらいまでは問題無く登れます。
それ以上を求めるなら、クライミングシューズに履き替えるべきです。

.
他にも、ゴアテックスが採用されていたりとか、一般的なアプローチシューズより少し固めのシャンクを使用していたりとか、総じて山歩きを考慮した作りの靴に仕上がっているように感じます。
それでも一般的な登山靴とは比較にならないほど高い岩でのフリクション性能を持ち、特に雨で濡れた岩では雲梯の差が生まれます。岩稜登山において、このコンセプトの靴は、本当に強い味方です!
さらにこの靴、ミドルカットバージョンもあります!
マルチピッチクライミングやアルパインクライミングなどで、クライミングシューズに履き替えた後に持ち歩かなきゃならないような場合にはローカットが優れていますが、登山にしか使用しないならミッドカットの方が優秀でしょう。
足首にかかる負担が大きく軽減されます。
小さなスタンスに乗れるようにタイトなつま先だったり、アッパーが足全体にぴったりとフィットさせることによって剛性を出す作りになっていたりと、このあたりの作りはアプローチシューズのそれと同じです。
やはり超重量、長時間の歩行には向きません。
スピードを重視した、軽量で短時間の岩稜あるきと、土っぽいアプローチを求められるクライミングで真価を発揮する靴です。
そのコンセプトに合致した時、きっと最強の支えとなってくれる一足です。
この情報が皆さまの道具選びのヒントにお役立ていただければ幸いです^^
テレックススコープ、なかなか良いですよ!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山の基本装備 " ファーストエイドキット "

登山は自然地の奥深くまで足を踏み入れる行為です。人里から遠くはなれているため、万が一の負傷時には自分たちでなんとかしなくてはなりません。
そこで必要になってくるのがファーストエイドキットです。
自力下山、もしくは救助までの間を耐える為のひとまずの応急処置を行うために、最低限必要な医薬品を用意しておきましょう。
何でもかんでも持ち歩くと、ファーストエイドキットはどんどん膨れ上がってしまいます。生命維持のために必要な優先順位を考え、緊急性の高い装備を中心に持つようにしましょう。

ファーストエイドキット
~ 登山の基本装備 ~
登山にファーストエイドキットは持っていっていますか?
街から遠く離れた自然地の奥深くまで足を踏み入れる登山では、万が一怪我をしてもすぐに助けは来ません。
例えば深い傷を追ってたくさんの出血をしてしまった場合、その場の応急処置で止血しなければ時に命にすら関わります。
骨折や捻挫では固定が必要になりますし、頭痛や下痢など、登山のパフォーマンスを下げる症状にも対応しなくてはなりません。
これらのトラブルに対し、ファーストエイドキットの備えが必要です。

.
登山中に起こるトラブルの内、特に出血に関する対応はとても重要です。
外傷を終えば必ず出血します。出血が続けば身体のパフォーマンスは著しく低下し、いずれ命を落とします。
また命に関わるほどの怪我でなくても、細菌感染による腫れ、熱発などの可能性も考えられます。
山の中で止血を行い、可能な限り衛生状態を保っておく。それに必要な装備を最優先して、ファーストエイドキットの中身を考えます。
また出血した仲間の応急処置を行う上で、必ずゴム手袋の装着も必要です。お互いに気が付かず持っている感染症があるかもしれません。また傷口の衛生状態を保つ意味でも必要です。
感染予防に必ずゴム手袋も数枚用意しておきましょう。
医薬品としては、以下のものを備えています。
◯ イソジン液:消毒に必要
◯ 抗菌軟膏:傷口の保護や虫刺され時の感染予防など
◯ ステロイド軟膏:植物や虫によるかぶれ、かゆみ、腫れなど
◯ 抗菌目薬:一回ずつ使える小分けタイプ
◯ 解熱鎮痛剤:痛みや発熱を抑える薬。血液凝固抑制が心配なので、個人的にはサリチル酸系は念のため避けています。
◯ 胃薬:胃粘膜保護剤と胃酸抑制剤の2種類を用意しています。
◯ 下痢止め:数日に及ぶ登山の時には必須です。
◯ 抗ヒスタミン剤:鼻水、かぶれ、かゆみなどのアレルギー症状に使用します。
衛生用品としては以下のものを備えています。
◯ 滅菌ガーゼ数枚:止血や傷口の保護に使用
◯ 包帯:固定と傷口の保護に使用
◯ テーピングテープ:捻挫や骨折の固定に使用
◯ サージカルテープ:ガーゼや包帯を止めるのに使用
◯ 絆創膏:小さな傷に使用
◯ コンドーム:手や足の傷を汚れや水から保護する為に使用
◯ ゴム手袋:感染予防に使用
◯ アルコール綿:器具の洗浄に使用
◯ 体温計:熱発や低体温症の目安に使用
ここで紹介したファーストエイドキットは、あくまで参考例です。
各個人ができる範囲の処置内容の装備を、想定しうるトラブルに備えて用意しましょう。
皆さまの安全登山にお役立ていただければ幸いです。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山のエマージェンシーキット " 小さなノコギリ "

木を切ったり、大雑把な加工を行う場合、ナイフよりノコギリの方が役立ちます。
もちろん登山にあまり重たい荷物を持っていくべきではありませんが、本当に小さなノコギリであれば持ち歩くのも殆ど苦にならないほど軽いものだったりします。
簡易的な担架や松葉杖を木から造ったり、沢登りでの焚き火の際に薪の長さを整えたり、焚き火のファイアーリフレクターを作るのにもノコギリがあると便利です。
実際には、ナイフより出番が多いかも知れません。
小さなノコギリを持つことで、きっといざという時に役立ちます。
なかなか便利ですよ^^

野外生活の鋸
~ 登山のエマージェンシーキットに入れたい装備 ~
エマージェンシーキットの中身って何を入れていますか?
人によって様々だとは思いますが、エマージェンシーシートやら、細引きやら、ダクトテープやら、登山雑誌で見たり、登山用品店でなんとなく買ってみたって言うような、そんな漠然としたものを持っている方が多いように感じます。
大切な事は、サバイバルな状況に陥った時、どの様にして生き延びるのかをイメージすること。
そのイメージしたことを行うのに、何が必要かを考え、それを用意することが大切です。
生命維持3の法則というものがあります。
◯ 3分間の心肺停止で生命の危機に瀕する。
◯ 3時間の低温、又は高温で生命の危機に瀕する。
◯ 3日間、水を得られないと生命の危機に瀕する。
◯ 3週間、食料を得られないと生命の危機に瀕する。
とあります。
山岳遭難におけるサバイバルでは、まず3時間以内に低温を避ける準備をし、3日間以内に水を得る必要があります。
食料は後回しで良いし、なんなら無理して摂らなくても大丈夫です。

.
まず最初に、雨風を避けるシェルターを作ります。
ツェルトを立て、もし寒い時期であれば程よい木々を使ってツェルトの周囲を覆うようにデブリハットを作ります。
もっと寒い時期なら、その周りを覆うように雪をかけると良いでしょう。
続いて火を起こします。
薪となる枯れ木を拾い、長さと太さを併せて仕分けます。
焚き火を起こす場所の地面を少し掘り、風上側にファイアーリフレクターを作ります。
ティンダーとなる素材から、徐々に焚き火を大きくします。
これらをナイフ1本で行うこともできなくはないですが、できればノコギリがあると遥かに作業性が良くなります。
ノコギリを持っていくと荷物が重くなりそうな感じもしますが、探せば中にはとても小さく、軽い商品も存在します。
個人的には、みきかじや村の " Plant Hunter mini " と、アルスコーポレーションの " 花小町 " を使っています。
折りたためば手のひらに収まるほど小さく、Plant Hunter mini で 49g、花小町で 32g と大変軽く作られています。
このくらいのノコギリであれば、エマージェンシーキットの一つとして加えても苦ではありません。
しかし小さいからと行って侮るなかれ!
あると無しでは大違いな、圧倒的な作業効率を生み出してくれます。
もちろんあまり大きな木を切ることはできませんが、焚き火の薪やシェルター作りに関しては問題無く使えます。
切れ味や作業性では Plant Hunter mini の方が使いやすいのですが、なんせ花小町は安い!
お値段1,000円以下で買えちゃいます^^
フォースト、フォーカスト問わず、ビバーク時に素晴らしい仕事をしてくれる小さなノコギリ。
エマージェンシーキットに加えとくことをおすすめします♪
※ 緊急時を除き、基本的に山に生えている植物を切るのはやめましょう。特に国立公園内でそれを行うことは犯罪です。
沢登りなどで使う際には、必ず流木や落木など、落ちている木を拾い集めましょう。
ただし緊急時に関しては、生命維持を優先させましょう。
皆さまの安全登山にお役立て下さい。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
Gサカイ アウトドアナイフ " 12 Outdoors STAG "

僕は3つのナイフを使い分けています。
一番出番が多いのが、トレッキングに使っているハサミがメインの小さなレザーマン。ついでクライミングや救助に使うスパイダルコのレスキューナイフ。
一番出番が無いのが、このシースナイフ。ぶっちゃけ、沢の泊まりかキャンプでしか使う機会がありません…。
しかし一番大切にしている刃物で、一生涯付き合っていくであろう相棒でもあります。
程よいサイズの刀身に、フルタング構造の丈夫なシースナイフ。鹿角のグリップ。
剃刀の様に鋭く切れる日本製。そのひとつひとつが男心を擽ります。

野外生活の相棒
~ Gサカイ アウトドアナイフ 12 アウトドアーズ ~
人類が人類たる所以は、自ら道具を作り出し、それを操る能力こそであると思います。
他の大型動物に比べ、丈夫な被毛も鋭い牙や爪を持たない私達は、自然界において非力な存在でもあるわけですが、それでも地球を支配するに至ったのは優れた道具を作り出すことが出来るからでしょう。
そうして現代社会では車が走り回り、コンピューターが普及し、とても自然の摂理とはかけ離れた文明を築くに至っています。
しかし人間もまた、地球という大いなる大自然の中の一種の動物に過ぎないことを忘れてはいけません。
いざ自然界に放り出されれば、そこで生き抜くためにスマートフォンが命を助けてくれるとは限らないのです。
それでも、人類が太古に生み出した文明の利器は大いに役立ちます。刃物の存在は偉大です。
大げさな話でなく、ナイフ1本と圧倒的な知恵があれば、自然界で生き抜く事は可能でしょう。

.
登山に使うことを目的に、僕は3種類のナイフを使い分けています。
ハイキングやトレッキングには、ハサミがメインとなった小さなレザーマンツールナイフを。
クライミングやレスキューのシーンでは、ロープを切りやすいようにつけられたセレーションと、安全のために先端が丸められ特徴をもつスパイダルコのレスキューナイフを。
そして自然地での野営を求められる時には、Gサカイのアウトドアナイフを持っていきます。
どれも大切な道具たちですが、一番愛着があるのは間違えなくGサカイのアウトドアナイフ " 12 Outdoors " です。
野営の際に、生活のための道具を作り出すための道具。そこに、人間の野生な部分が刺激されるのです。
グリップから切っ先まで一枚の鋼材で構成された、丈夫で軽く、美しいテーパードフルタング構造。とても手間がかかる構造なので、通常は量産型のナイフには使われない構造です。
刃厚4mm と強靭な強度を持たせながらも、ホローグラインドされたドロップポイント形状、VG-10鋼材も相まって、大変素晴らしい切れ味も持っています。
手に優しく丸みをつけられた、鹿角のグリップ。長めのヒルトとマッチし、その美しさを際立てます。
まさに生涯付き合っていきたい、男心をくすぐる一本です。
Gサカイは、日本の刃物メーカーです。スパイダルコなど、海外メーカーからも刃の製造を一任される圧倒的な信頼が持てます。
その切れ味はまさに日本刀が如く。購入時点で恐るべき切れ味を持っています。(あまりの切れ味に、Gサカイの刃物でうっかり危うく指を切断仕掛けたことがある事はナイショの方向で…。)
このナイフは主に沢での野営の際に使用しています。
流木の枝を切り落としてトライポッドを作ったり、ポットハンガーにファイアーリフレクター、時にはシェルターやペグを作ることもあります。もっと経験を積めば、ナイフ一本であらゆる事ができる日もやってくるかも知れません。
そういった目的で使うこのナイフには、ちょっと特別な感情を持っています。
実はこのナイフ、2本目。
以前はこれと同じナイフの木製グリップのものを使っていました。
しかしある日気がつくとその姿は見当たらず…。(たぶん秩父のとある沢の切り株の真ん中に、伝説の剣的に刺さってます。見つけた方は大切に使って下さいw)
紛失しましたが、実際に登山では違うナイフを使うことが多いので、あえて買わなくても不便はしていませんでした。
でもね、心が寂しいんですよ。
ただの道具として使っているナイフと、一生涯のパートナーとしようとしていたナイフとではその重みが違います。
いろいろ見ましたが、結局同じのにしちゃいました^^;
野外生活を送る男の相棒となる一本。
今日も、このナイフを腰に野外へと出かけて行く。
そんな相棒となる一本を、皆さんも手に入れてみては如何でしょう?




Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山のエマージェンシーキット " ティンダー "

徹底した安全対策を行っても、山の危険を完全に取り除くことはできません。
万が一の時には、持ち合わせの道具を頼って生き延びる為の知恵を身につけていなくてはなりません。サバイバルの為にまず欠かせないのが、体温を維持すること。
ツェルトなどのシェルターで雨風を避けるとともに、焚き火などで体を温めることが大切です。特に秋~春にかけては焚き火がかなり有効です。
しかしいきなり拾った木の枝に火をつけようとしても、焚き火は起こせません。まずは火口となるティンダーに火をつけ、小枝から徐々に太い木に火を移していきます。
焚き火の火付け役、ティンダーの作り方をここでは紹介していきます。

.
.
麻紐ティンダーの作り方
~ 焚き火の火付け役となる種火となれ ~
うっかりスマートフォンを機内モードにし忘れ、気がつけばバッテリー切れ。
そんな時に限って下山時に支尾根に迷い込み、いつの間にか沢床を彷徨っていました。
振り返っても、もうどこをどう歩いてきたのか検討もつきません。
GPSを見ようとスマートフォンの予備バッテリーを取り出そうとバックパックを漁ってみても、どこにも予備バッテリーは見当たらない。どうやら家に忘れてきたようだ…。
しかもツェルトまで忘れてきてやがる…。
こういう日はとこんとんやらかすもので、幾つもの小さなミスの積み重ねが大きな困難へと繋がります。
間もなく日も暮れようとしている今、一刻も早くビバーク準備をしなくてはなりません。
こんなミスが多い日だが、いつもこうな訳じゃない!
非常事態に備えて用意していたエマージェンシーキットをいつでもバックパックの底に忍ばせてきた。
今、こいつが役に立つ!!
気がつけば小雨までパラついて来た。
エマージェンシーシートをタープ代わりにどうにか雨は凌げるが、保温できるものが何もない。
そうだ、火を起こさなきゃ。
雨に濡れた枝に火をおこすのはなかなか大変だけれども、エマージェンシーキットに入れておいた麻紐があれば難しくはない。
麻紐を解し、火種を起こすためのティンダーさえ作れば、濡れた木々でも焚き火は起こせます。
それでは、ティンダーの作り方を見てみましょう!

沢での野営時に流木でトライポッドを作ったり、負傷者が出た時に担架を作ったりなど、負荷のかかる箇所に使う場合もあるので、個人的には3本撚りタイプの強度が高い麻紐を使っています。

まず大きく3つ撚りになっている麻紐を分解します。

さらに各1本ずつを解して行きます。

長さ20㎝ 程度の3つ撚り麻紐を全て解すと、大凡1回分のティンダーとなります。
非常に燃えやすいので、これを予め作っておくと焚き火の際に便利です。

沢登りなどに持っていったり、雨天時のことを考慮してジップ付きのビニールパックに入れて携行しています。(濡らしてしまうと着火が困難になります。)
ぺたんこになっていますが、取り出して解せば上記写真のようにふわりと復元します。
万が一のビバークでは、事前にどれだけシュミレーションできていたかが重要です。
持っていくものが増えれば増えるほど、登山の原則である軽量化に反することになってしまいます。サバイバルにおける鉄則もまた、最低限の装備で如何に出来ることを広げるかにあります。
そこで重要になるのが想像力です。
どんな事が必要になるのか?
その事態に対応するためにどんな装備が必要なのか?
事前に準備しておくことが出来るものはあるのか?
多くの知識を身に付け、知恵を振り絞り、想定されるあらゆる事態に対応できるギリギリ最低限の装備を用意しましょう。
そしてそれを実際に使えるように練習し、何時来るか分からない万が一の事態に常に備えましょう。
皆さまの安全登山のヒントになれば幸いです^^
※ 沢沿いなど、限られた環境を除いて原則山の中で焚き火をするべきではありません。
また沢においても、登山道から目に止まるような場所での焚き火は景観を損ないます。
緊急時を除き、指定箇所以外での焚き火は行わないようにしましょう。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
ディート 98.11% 最強の虫除けスプレー "REPEL100"

ナチュラル100%の虫除けスプレーが流行する中、真逆にぶっ飛んだケミカル100%!
完全なる化学物質系虫除けスプレーです^^;
日本ではディート30%の濃度までしか製造が認められていませんが、REPEL100 はなんとディート98,11%。もうほとんどディートだけ。なんか体に悪そうです…。
しかしその効き目は抜群で、これまで試してきた虫除けスプレーの中では間違えなく最強です。
蚊やブヨ、マダニ、ツツガムシ、ヤマビルなど、被害に会いたくないやっかいな虫を寄せ付けません!

,
ディート98,11% 最強の虫除けスプレー
~ 蚊、ブヨ、マダニ、ツツガムシ、ヤマビルなどに有効 ~
今年はブヨやヤマビルにひどい目にあわされています。山をやる以上はどうしても避けられない、人間にとって有害な虫達。
どうにかうまく付き合っていかなくてはなりません。
やはり虫除けスプレーを上手く使って、出来る限り害虫被害に遭わないようにしたいものです。
最近、ものすごい強力な虫除けスプレーを手に入れました。
近年ではノンケミカルなナチュラル100%の天然成分虫除けスプレーが流行っていますが、この虫除けスプレーは100%ケミカル。
虫除け成分として有名なディートですが、日本の薬事法では永らくディート配合量は12%までしか製造してはいけないことになっていました。最近でその濃度が30%まで認められるようになりました。
しかし海外より入手した REPEL100 は、なんとディート98,11%!!
もう化学物質しか入っていません。体に悪そうです^^;

.
第二次世界大戦の際、ジャングルでの戦いで多くの兵士が蚊を媒介とする病気で命を落としました。
その後アメリカ軍が軍用の虫除け成分として開発したのがディートです。ベトナム戦争、湾岸戦争では、蚊を媒介とした病気で命を落とす兵士の数は激減したようです。
その後民間でも使われ始め、現在では市販のほとんど全ての虫除けスプレーにディートが使われています。
主に昆虫類を中心とした、多くの虫に効果を示します。
長期間、高濃度で摂取し続けた場合に神経毒性がある事が確認されていますが、よほど大量に、且つ日常的に毎日使い続けない限りは基本的に安全性の高い成分だそうです。
皮膚が弱い方などでは赤みやかゆみが出る場合もあるそうですが、衣類に使うなどの工夫をすれば大きな問題は無いでしょう。
日本国内では濃度12%までしか製造してはいけなかったのも、この様なリスクがあるからだそうです。しかしそのリスクは決して大きくないと分かってきたことから、30%まで製造が認められるようになりました。
例えばマダニやツツガムシによる感染症のリスクを考えれば、ディートによるリスクは微々たるものでしょう。
先日で言えば、いつもならシツコクつき纏うはずのスズメバチの偵察が、ちょっと周りを飛んだらすぐに逃げて行きました。スズメバチに対して虫除けスプレーはあまり効果が無いとされていますが、ディートは全ての昆虫が嫌がることが確認できています。
さすがに98%超えの濃度のディートはスズメバチに対しても多少効果があるのかも知れません。
まだ試せていませんが、ヤマビルに対してもかなり期待ができるのではないかと考えています。
山に入る方にとっては、とても心強い味方になってくれると思います。
個人的には、このスプレーを衣服にだけ使って、皮膚には国産のものを使うようにしています。
このあたりは個人でご判断下さい。
山における害虫被害は侮れません。
この REPEL100 はかなり期待できると思います。
ご興味ある方は是非お試しください^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山のロープワーク " ダブルフィッシャーマンズノット "

ダブルフィッシャーマンズノットは、登山のロープワークとして身に付けておきたい基本的な結び方の一つです。
エイトノットの末端処理として行ったり、ロープスリングの末端の連結に使ったり、自在結びの末端の処理に使ったりなど様々。
とても強固にロープの末端を主軸となるロープに結びつけることが出来ます。
何度も練習し、いつでも迷わずに素早く結べるようになっておきましょう。
ここでは写真とブログで結び方を説明しています。

.
.
ダブルフィッシャーマンズノットの結び方
~ 登山のロープワーク ~
ダブルフィッシャーマンズノットは登山のロープワークとして身に付けておきたい基本的な結び方の一つです。
エイトノットの末端処理や自在結びの末端処理、ロープの末端同士を繋ぐダブルフィッシャーマンズベントを結ぶ時など、様々なシーンで使用します。
いつでも迷わず素早く結べるようになるまで、しっかりと練習しましょう!

ロープの末端を写真のように持ちます。(右側がロープの末端です。)

ロープの末端を手前側に向かって2周巻きつけます。

指を抜いて出来た穴にロープの末端を通して締め上げます。

これがダブルフィッシャーマンズノットとなります。
結び終わった後、必ずロープの末端がロープ径の10倍以上でているか確認しましょう!

ダブルフィッシャーマンズノットの応用として、ロープの末端と末端を繋ぐ"ダブルフィッシャーマンズベント"も覚えましょう。
まずロープの末端と末端を向かい合わせで並べます。

相手側のロープも一緒に巻き込み、ダブルフィッシャーマンズノットを結びます。

反対側の末端も同じように結び、ロープを引っ張って結びを固めます。

これでダブルフィッシャーマンズベントの完成です。
とても強固にロープを繋ぐことが出来ます。
様々なロープの結び方を、迷わず結べるようになるまでしっかりと身につけることは、山でロープによる安全確保を行う第一歩となります。登山者としてロープを使いこなせるようになることはとても重要な事です。
安全な登山を継続するためにも、まずはひとつずつの結びを覚えていきましょう!
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

ロープワーク基礎講習
登山に必要な様々なロープの結び方を学習して頂く、ワークショップ形式の座学講習です。まずは基本となる結び方を覚えることから、登山における安全確保の第一歩が始まります。しっかりと身につけましょう!!
集合場所:Kuri Adventures オフィス 料金:2,500円(税別)
山岳ロープワーク講習
登山中に現れる危険箇所の通過や、バリエーションルートを歩く際に必要な安全確保技術を指導します。積極的にロープを使った確保を行うことで、山の安全は確実に高まります。安全登山の為にも、是非ロープワークスキルを身につけましょう!!
料金:9,250円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
1/3 レイジング(倍力)システムの手順

レイジングは、滑車の原理を利用して小さな力で重たいものを引き上げることができるシステムを言います。その特性から、レスキューの世界では倍力システムなどと呼ばれ、救助活動の要となる技術として使用されています。
安全の為にロープで確保していても、宙吊りになった仲間を引き上げられなければその技術は意味を成しません。
ここではダイレクトビレイ中に、フォローが宙吊りになってしまった状態からレイジングを構築する流れを説明しています。

.
.
レイジング(倍力)システムの手順
~ 救助活動の要となる、基本技術 ~
レイジングは滑車の原理を利用した技術で、小さな力で重い重量物を引き上げる事ができるシステムです。救助の要となる基本技術で、登山者によるセルフレスキューとしても是非身に付けておきたい技術です。
登山において、ロープによる安全確保技術はとても重要です。
雪庇の踏み抜きやクレバスへの転落、岩稜歩行、沢の高巻きなど、ちょっとしたミスで転滑落を引き起こす可能性がある様な場面でも、ロープによる確保を適切に行うことでその危険を最小限に留めることが出来ます。
しかし、墜落を止めただだけでは不十分。宙吊り状態から引き上げることができて、初めて安全確保技術となりえます。
ここでは、セカンドフォローでダイレクトビレイを行っている際に、パートナーがオーバーハングの下で墜落して宙吊りになった様なシーンを想定したレイジングシステムの作り方を紹介しています。
まずは基本の形を覚えていきましょう!

ここではフォローで登ってくるクライマーがハングした場所で墜落し、自力で登り返せない設定での流れを説明します。
岩稜でのタイトロープ中に墜落した場合や、雪庇・雪渓を踏み抜いた、クレバスやシュルンドの落ちた様な場合はまず最初に支点を作って下さい。

まずパートナー側のロープにアッセンダーを取り付けます。(フリクションノットでも構いません。)

支点にスリングを通します。この時、ビレイデバイスよりスパイン側(ゲートとは反対側)にスリングを通すように注意しましょう。

スリングをアッセンダーと繋ぎます。(タイトロープで墜落した場合のレスキューでは、アッセンダーではなく直接セルフジャミングプーリーでロープとスリングを繋ぎます。この時点で、荷重を支点に移すことが出来ます。)

ビレイデバイスのロックを解除し、荷重をスリングに移します。

荷重が支点に移ることで、ビレイデバイスを取り外すことが出来るようになりました。

ビレイデバイスを支点から取り外します。
スリングを支点に通す時、うっかりビレイデバイスよりゲート側にスリングを通してしまった場合、ビレイデバイスを支点から外せなくなるので注意しましょう。

ビレイデバイスをロープから外し、セルフジャミングプーリーを取り付けます。
向きを間違えると確保出来ないので、必ずセット後にロックがかかっているか確認しましょう。
セルフジャミングプーリーが無い場合は、プーリーとアッセンダー(またはフリクションノット)でも構いません。遊び分戻りが出てしまうので、ロープを引いた後に遊びを解消してあげる必要があります。
作業効率を高めるためにも、できればセルフジャミングプーリーを用意しましょう。
プーリーを使わずにカラビナで折り返す方法は、エネルギーロスが大きくなります。
プーリーは常備すべき装備であると思います。

続いてセルフジャミングプーリーで折り返したロープに、もう一つプーリーをセットします。このプーリーはセルフジャミングプーリーである必要はありません。(タイトロープで墜落した場合のレスキューの場合の流れは、この項目から再開します。)

アッセンダーとスリングを繋いでいるカラビナにアッセンダーを取り付けます。
この時、システム全体に擦れや捻れが発生しないように気をつけましょう!

この時点で1/3 レイジングシステムが出来上がっています。
ロープを引くとスリングからロープに再びテンションが移ります。

この時スリングに緩みが出ます。一度アッセンダー側のカラビナからプーリーを外し、スリングを回収しましょう。
支点側は折り返してるだけなので、引っ張れば抜けます。

1/3 レイジングシステムは、理屈上これで 1/3 の力で引けるはずなのですが、実際には岩との擦れやプーリーの摩擦などである程度フリクションロスが発生します。
またパートナーが重い場合、仮に体重 65kg の人が 15kg の荷を背負っていた様な場合には、引く力は凡そ 30kg にも達するでしょう。
ロープの先に 5kg の米袋が6つぶら下がっているとイメージして下さい。2Lペットボトル15本でも構いません。
引っ張りあげられますか?よほど豪腕な方以外なかなか難しいでしょう。

そこで、支点もしくは支点の付け根などにもう一つプーリーを取り付け、ロープを通して折り返します。

ビレイループにビレイデバイスをセットし、ロープを通します。
自分の体重を使って真下にロープを引きましょう。
仮に体重40kgしか無い小柄な女性でも、30kgの荷重を引くのに十分なエネルギーとなります。
この方法でも引き上げられないような場合(救助者と要救助者など複数名がぶら下がっているような場合)は、1/5・1/7・1/9 とシステムを変えながら、ちょっと頑張れば引き上げられるくらいの分散率を使用しましょう。
ここで紹介した技術はレイジングシステムのほんの一部です。
この技術を応用することで、様々なシーンに対応する事が出来ます。まずはこの基本の流れをしっかりと身につけることで、後に応用が覚えやすくなります。
またレイジングは作り方を覚えるだけではダメで、実際に人を引き上げる経験を積んでおくことが大切です。
沢山の練習の上に、初めて技術となりえます。何度も練習し、いざという時に備えておきましょう!
Kuri Adventures では、セルフレスキュー講習を通じてレイジング技術の指導を行ったり、登山技術訓練会にて実際に技術を使って練習を重ねる機会をご用意しています。是非ご参加頂き、技術力向上にお役立て下さい。
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

レイジングシステム技術講習
セルフレスキューの引上げの基本となる 1/3レイジングシステムの作り方を学びます。平日のお仕事帰りに、都内で2時間で学べるお手軽なワークショップですので、是非お気軽にご参加願えれば幸いです^^
集合場所:芝公園 料金:2,500円(税別)

登山のセルフレスキュー講習
登山中に滑落し負傷した仲間を救い出すと仮定し、実際に救助活動シュミレーションを行って頂く実践形式の講習会です。松葉杖や担架の作り方、レイジングシステムを使用した背負搬送技術など、実際に役立つ技術が身につきます。
料金:9,990円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
今、登山に衛星電話が現実となりました!

登山を行う上でいつも心配なのが、山の奥から通信が困難な事。
稜線上であれば、場所によって携帯電話が通じることもありますが、その多くの場所では電波は通じません。無論、谷では一切電波は通じません。
無線機の利用も考えられますが、これもいつでも電波が届くわけではありません。特に携帯電話が普及した現在では、趣味で無線を傍受している人も少なくなりました。
しかしその一方で、もっと確実に通信が行える通信システムが最先端技術により可能となりました。それは衛星電話です。現在ではとても手に入れやすく、維持費も現実的になりました。これなら安心料として持っておくのも良いかもしれません。

登山の最強携帯電話 衛星電話システム
大自然の奥地にまで足を踏み入れる登山は、様々なアウトドアアクティビティの中でも特に原生の自然を感じることができます。しかし深く自然地に足を踏み入れていけば、その分文明の力は及ばなくなってきます。
山がなぜ危険なのか?その大きな要因に、すぐに助けが呼べない場合が多い事にあると思います。
安全な登山を楽しむ上で、通信の確保はとても大切です。
現在では遭難救助の要請の多くが携帯電話から為されていますが、山の中でどのくらい携帯電話が使えるでしょう?
実際には、一部の稜線上で使えるに限られ、山域の多くの部分において使用ができません。
無線機を保つ方法もありますが、携帯電話が普及した現代では無線趣味の方も減りました。通信を試みても、誰にも繋がらないことも多いでしょう。

.
そこで最終兵器となるのが衛星電話!
衛星電話にも弱点はありますが、地上インフラに頼る携帯電話と違い、条件を満たせば原則としてどこからでも電波が届きます。この安心感は絶対的です。
衛星電話はとても高いイメージがありますが、現在ではその価格もだいぶ現実的になりました。
特に超高度域に静止衛星を配置し、少ない衛星数で広いエリアをカバーする、DoCoMoが提携するインマルサット衛星電話サービスやSoftBankが提携するスラーヤ社の衛星電話サービスはかなり安価です。
どちらも月4,900円の基本使用料で、通話料も1分160円と驚くほど高いわけではありません。SoftBankに至っては実質機種代タダ。基本使用料に1,000円分の無料通話まで含まれます。
今や衛星電話は一般的なスマートフォンと大差無い価格で購入でき、維持費も現実的値段で手に入ります。
これらの衛星電話には使用制限エリアがあり、その制限エリア内では法的に通常利用はできません。しかし、大幅に下山が遅れた場合やビバークに追い込まれた場合など、遭難までに至らなくても生命に関わる可能性があるトラブルの際の緊急時利用は認められています。(事後報告の届出が必要です。)
そもそも通話料がけっこう高額なので、通常利用することはまぁあまり無いでしょう。
どちらの衛星電話もIP54相当の防塵防滴性能を有し、インマルサット社のアイサットフォンプロで−20°、スラーヤ社の201THで−10°までの動作環境が保証されています。バッテリー電圧の関係があるので普通の携帯電話と同じく冬は体に密着する場所で携行する必要があるとは思いますが、それでも一般的な携帯電話に比べて環境に強く作られています。
通信エリアにも少し差があり、スラーヤはアメリカ大陸全域がカバーされていません。インマルサットは世界中のどこからでもほとんどどこからでも通話が可能です。世界を旅する方にとっては、インマルサットの方に利があるでしょう。
一方で、利用制限エリアに関してはスラーヤが有利です。インマルサット社の静止衛星とスラーヤ社の静止衛星の位置が異なることもあり、スラーヤ社の衛星電話の方が利用制限エリアが少なく済みます。
そもそも通話料が高額なので、緊急時以外は使用することも少ないでしょうが^^;
Kuri Adventures では、SoftBank が提供するスラーヤ衛星電話サービスを導入しています。
まだ導入から日が浅いので細かなところまでは実験できていませんが、今のところ山の中で電波が届かなかったところはほんの僅かに限られています。(南西方向が完全に塞がれた斜面のトラバースや、岩壁前では使用できないようです。)
電波が届かないようなところでトラブルにあっても、通信係を設けて無線機などで現場と更新できる状態にすれば、ほぼどんな条件からでも地上と更新できると考えられます。
単独行などでそれが難しい方には、KDDI
のイリジウム衛星電話と言う選択もあります。こちらは導入金額が一番安いもので25万円と高額ですが、基本使用料や通話料に大差はありません。インマルサットやスラーヤの様な静止衛星とは違い、GPSと同じような衛星を何十機も上空に飛ばしています。空さえ見えればどこでも通信ができるので、現在考えられる通信システムの中では最強でしょう。
いずれにせよ、衛星電話の導入で大きな安心を手にすることができます。
イリジウム衛星電話はなかなか難しいにしても、例えば初期導入費用がかからないスラーヤ衛星電話なら、月4,900円の基本使用料のみで持つことが出来ます。もはや衛星電話は、個人でも持つことができる時代になったのです。
より安全な登山を楽しみたいと考えている方は、検討してみても良いかもですよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
支点構築の流れ

支点は、パーティー全体の命を預かる最後の要。
スタカットビレイシステムは、一方が確実に大地と繋がっている事で安全が成り立っています。信頼のおける支点の構築は、安全なクライミングを楽しむ上で絶対に欠かす事のできない技術です。
ここでは最も基本となる、シングルロープで相互登攀を行う場合のシステムを紹介しています。
しっかりと指導を受けた後の復習にご活用下さい。

.
.
マルチピッチにおける支点構築の流れ
~ 確実な支点、終了点を作れる事は、安全なクライミングの必須技術です ~
マルチピッチクライミングやアルパインクライミングを楽しむ上で、絶対に欠かすことのできない大切なスキルに支点構築技術があります。
沢の滝など、シングルピッチの壁をトップアウトする場合にはフォロアーのビレイが必要になります。強固な支点を構築し、フォロアーの安全をしっかりと確立しなくてはなりません。
またマルチピッチクライミングなど、大きな壁を登る場合に関しては、自分も含めたパーティー全体の命がこの支点にかかります。絶対にミスは許されません。
安全なクライミングを楽しむ上でも、しっかりと確実に身につけましょう!

支点構築には以下の装備が必要です。
・ダイレクトビレイに対応したビレイデバイス + ビレイデバイス用カラビナ
・安全管付きカラビナで作ったクイックドロー
・120㎝のナイロンスリング + 安全管付きカラビナ
・セルフビレイコード + 安全管付きカラビナ
・支点用安全管付きカラビナ
※ アルパインクライミングでは、7mm × 7m 程度の細引きも用意しましょう。

アンカーポイントに到着したら、次のピッチがどちらの方向に進んでいるのかを確認します。
次に進む方向とは逆側のハンガーに、外側から内側に向かって安全管付きカラビナを取り付けます。この安全管付きカラビナに、スリングを通しておきます。

カラビナを反転させ、自分に繋がっているメインロープをクローブヒッチで結びます。このメインロープがセルフビレイとなりますので、行動が制限されない程度に長さを調整します。
安全管付きカラビナのロックは忘れずにチェックしましょう!

続いて安全管付きクイックドローを進行方向側のハンガーにかけます。こちらも外側から内側に向かってクイックドローをカラビナにセットします。

支点の頂点にクローブヒッチでカラビナを取り付けます。
流動分散にする場合、必ず結び目による可動域制限を行うようにして下さい。

支点を構築したら、セルフビレイコードによるバックアップを行い、必ず2点以上からセルフビレイが行われている状態にして下さい。
この時、メインロープでのセルフビレイに先にテンションがかかるように長さを調節して下さい。セルフビレイコードでのセルフビレイは、あくまでバックアップです。
ここまでできたら、パートナーに"ビレイ解除"とコールを出します。

パートナーからビレイ解除のコールが帰ってきたら、"ロープ引きます"とコールを出し、不要なロープを自分のセルフビレイに振り分けます。
フォローは、ロープのあまりが全て出たら"ロープいっぱい"とコールを出します。

ロープいっぱいとのコールを受けたら、ビレイデバイスのセットを行います。
まず通常ビレイを行う際と同じように、向きに注意してロープをセットします。

続いてビレイデバイスのダイレクトビレイ用の穴に、支点中央のカラビナを通します。これでダイレクトビレイの準備が完了します。
セットが完了したら、フォローに"ビレイセットOKです"と声をかけましょう。
コールを受けたフォローは、支点を回収します。
この時、安全管付きクイックドロー側から回収し、バックアップセルフをそのハンガーにかけ直します。その後、メインセルフを解除し、支点に使用した道具をまとめます。
すべて準備が整ったら、"登ります"とコールを出し、"どうぞ"と返答があったら、バックアップセルフを解除します。

下側のロープ(握り手側のロープ)を引き、パートナーに常にテンションがかかるようにビレイを行います。
フォロークライマーは、ロープの流れるスピードに併せて登って下さい。
決してたるみを作ってはいけません。

フォローは、支点に到着したらまず最初に、安全管付きクイックドローにクローブヒッチでセルフビレイをとります。続いて支点にバックアップセルフをとります。

ビレイヤーは支点からビレイデバイスを外し、そのまま自分のハーネスのビレイループにビレイデバイスをセットします。
お互いにビレイのセットを確認し、装備の受け渡しなどを行います。
準備が整ったら、お互いが確認の上で登り始めましょう。

まずメインセルフを解除し、そのままクリップします。
この安全管付きクイックドローが、そのまま1ピン目のクリップとなります。
こうする事で、墜落係数2の墜落を防ぐことができる上、ビレイヤーが下に向かって引っ張られてしまう事態も防ぐことができます。
最後に"登ります"とコールをかけて、バックアップセルフを解除します。
支点構築は、できたつもりになって間違えて覚えている方がとても多いように感じます。
また部分的に手抜きをして、セルフビレイを1点からしかとっていなかったり、ハンガーに繋ぐカラビナが2点とも安全管付きカラビナでないカラビナを使っていたりなど、リスクを伴う支点構築をしている方も見かけます。
支点構築は、仲間の命を預かる大切な最後の砦となります。
強固で確実性の高い視点を構築しましょう。
初心者のかたは、このブログで学んだだけで覚えたつもりにならないようにして下さい。
できたつもりになっても、実際には間違えていることがあります。
ここでの説明は、あくまでも予習・復習に活用して頂くに留め、必ず十分な経験を有する方の指導の元で技術を習得して下さい。
その上で、何度も練習し、一手も迷わないで支点構築が行えるようになるまで練習を繰り返しましょう。
このブログ記事が、これから大きな壁に挑戦する登攀者の安全に役立てばと思っています。
安全なクライミングをお楽しみ下さい^^
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

支点構築技術講習
マルチピッチクライミングやアルパインクライミングで必ず必要になる、支点構築技術をお伝え致します。全てのクライマーに覚えて頂きたい重要技術です。
しっかりと学習し、クライミングの安全にお役立て下さい。
集合場所:Kuri Adventures オフィス 料金:2,500円(税別)

マルチピッチクライミング講習
大岩壁を登るためのシステムを覚えるための講習です。
アルパインクライミング、沢登りなどを行う上でも必須となる技術です。
リードクライミングをマスターしている方を対象としています。
対象:リードクライミングができる方 料金:13,880円(税別)
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
クライミングレスキュー リード編 " 宙吊りからの救助法 "

マルチピッチクライミングやアルパインクライミングを楽しんでいる時、もしパートナーが墜落したり、落石があたったりして意識を失ってしまったらどうしますか?
宙吊り状態になってしまったパートナーを助け出すための技術を身につけることは、クライマーとしての最低限の責務だと思います。
救助に必要な道具を揃え、その知識と技術を身につける事こそ、登山における自己責任なのだと思います。
大切な仲間を救うことができる一人前のクライマーになりましょう!
ここでは、リードクライマーの救助方法を動画で紹介しています。

アルパインクライミングやマルチピッチクライミングでは、ロープの半分以上の高さまで登る事も多くあります。
ロープの半分以上の高さにまで登った場合、仮にトラブルが起きてもロアダウンで下ろすことができません。
もしロープの半分以上の高さまで登った状態で、もし登っていたリードクライマーが大きく墜落して頭を打ち、意識を失ってしまったら?
あなたは大切なパートナーを助けに行くことができますか??

.
正直、覚えるべき技術を覚えないまま、大きな壁に挑んでしまう方が多いような気がします。
宙吊りからの登り返しはできますか?
レイジング(倍力システム)での引上げの経験はありますか?
登れなかった場合の敗退技術は身に付けていますか?
例えば、ロープの半分以上の高さまで登り、そこで登れなくなった場合、どうやって敗退するのか説明できますか?
あらゆるトラブルを想像し、その起こりえるトラブルの解決方法を身につける事は、登攀者の責務です。
壁の中であらゆる困難を解決できるスキルを持ち合わせた者。本来、"クライマー"とはその様な存在を言うものだと思います。
そして、自分たちの事はできる限り自分たちで解決する。その為の技術と装備を身に付け、万が一に備えること。
そのことこそ、登山における自己責任なのだと僕は思います。
下の動画では、リードクライマーがロープの半分以上の高さまで登り、そこで事故が発生した状況を想定したセルフレスキュー技術をお伝えしています。ここではもっともオーソドックスな、パートナー側のロープを切る方法をお伝えしていますが、刃物を使う以上リスクがあることも覚えておいて下さい。
もし間違えて他のロープを切ってしまうと、かなり困難な状況に陥ります。
パートナー側のロープを切った瞬間に振られ、ナイフでパートナーを突き刺してしまう可能性もあります。
パートナーの体重に巻き込まれ、自分の指を腱まで切ってしまうかもしれません…。
(映像の中で手を怪我していのは、レスキュー訓練中にやらかして、まさに腱まで切っちまいました…。全治3週間コース(T_T))
実際の講習では、オーソドックスなパートナー側のロープを切る技術に加え、最新のもっと安全な救助技術も指導しています。
かなり複雑なシステムとなるので、映像でお伝えするのが難しいのです。ご興味ある方は実際の講習で受講下さい。
セルフレスキュー技術は、覚えても生涯使わない可能性が高い技術ですが、それでもしっかり身につけるべき重要な技術です。
万が一の時に後悔しないよう、しっかりと学びましょう!
クライミングレスキューを見よう見まねで行うのは危険です。必ず経験者指導のもとで学び、何度も練習を重ねましょう。
実際に一手も迷わず作業が行えるくらい練習を重ねなければ、クライミングレスキューは行うべきではありません。
また、クライミングレスキュー技術を持ち合わせていない人たちだけでのマルチピッチクライミング、アルパインクライミングは大変危険なので控えましょう。
Kuri Adventures では、クライミングレスキューを始めとしたセルフレスキュー技術の講習を行っています。
是非ご参加頂き、しっかりと技術を身につけましょう!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
山の危険生物"マダニ"

小さいが、侮るなかれ!マダニに感染して死亡する事故が、毎年起きています。
マダニを媒介とした人獣共通感染症による疫病感染し、様々な病気を発症します。その中には重篤な症状を引き起こし、時に人を死に至らしめたり、生涯残る後遺症で苦しめたりするケースもあります。
しかもその多くに有効な治療法もなく、またワクチンもないと言う恐ろしさ…。
大切なことは、しっかりと予防対策を行うこと。
そして早期発見、早期除去を行うこと!
山の恐ろしい危険生物"マダニ"に関する知識を身に付け、身を守りましょう。

先日、北海道でマダニに噛まれて死亡する事故が起きました。
熊やスズメバチなら理解できるにしても、マダニで人が死ぬ??何とも不可解な話です。
その正体はフラビウイルスと言う、マダニを媒介とするウィルスが原因で、ダニ媒介性脳炎と言う病気を引き起こします。
ダニ媒介性脳炎が発症して治療法は特に無く、効果的な薬物療法は存在しません。
発症すると髄膜炎、脳炎、髄膜脳炎などの病気を引き起こし、10%~20%の方に半永久的な麻痺が残ります。また重篤化すると死亡する事もあります。
なめちゃイケない、なかなかおっかないやつです。
有効性の高い予防ワクチンも存在するものの、日本では認められておらず、一部の医療機関にて自費で高額なワクチンを受ける他にワクチンでの予防法はありません。

ライム病と呼ばれる、ボレリアと呼ばれる病原菌を原因とする病気のリスクもあります。
初期症状としてはインフルエンザによく似た症状で分かりにくいのですが、マダニの最盛期はインフルエンザの最盛期と真逆の季節にあたりますので、春~秋にかけてインフルエンザのような症状が出た場合には、ライム病の可能性も考えた方が良いかもしれません。
ライム病の場合、噛まれた箇所に特有の腫れ模様ができます。
この様な腫れ模様ができた場合には要注意です。
放置すると、慢性的な皮膚炎、関節炎、脳髄膜炎、角膜炎、心疾患などの後遺症が残る場合があります。
こちらも日本には予防ワクチンがなく、標高800m以上の山域で噛まれた場合にのみ発症リスクが有ります。
つまり登山者以外にはさほどリスクがありません。
この病気になるのは、私たち登山者です。
(但し北海道では平野部にもいます。この病気は、中部以北を中心に見られる病気です。)
他にも、SFTSウィルスによる重症熱性血小板減少症候群や、日本紅斑熱など、これまでにたくさんの死亡者を出している病気の感染リスクがあります。これらに関してもやはり予防ワクチンは無く、内、重症熱性血小板減少症候群に関しては、有効な治療法もありません。
大切なことは、しっかりとした感染予防を行う事です!
マダニはノミの様にジャンプしたりしません。草むらや木々の葉の裏に潜み、動物がやってくるのをじっと待ちます。
そして私たちが通過すると、そっと乗り移って、皮膚に頭をねじ込みながら吸血を開始します。
数日かけて血液を吸い続けた後に剥がれ落ち、数百の卵を産みます。
まず大切な事は、皮膚を露出させないこと。
半袖や短パンで肌を露出させたまま草木に触れると、マダニに食われるリスクが跳ね上がります。
足元も、ゲイターなどを使用することでマダニの被害リスクを大幅に減らせます。
虫除けスプレーも有効性が高いです。
体に有害な可能性があると嫌う方も多いのですが、ディートが含まれた虫除けスプレーはマダニ避けには効果抜群です!
特に足元。靴下などにスプレーしておくことで、裾からの侵入も防げます。
またヤマビルにもある程度の予防効果を示します。
虫除けスプレーの効果は2時間程度なので、こまめにスプレーすることが大切です。
万が一噛まれた場合、無理に引っ張るのはやめましょう。
吸われた血液が逆流することで病原菌やウィルスが体内に進入するリスクが高まる他、頭がちぎれて体内に残留することで、別の細菌感染による化膿などのリスクも出ます。
ただし早期に発見し、早期に除去することは、感染症予防の為には重要です。
マダニの除去は、専用器具を使って取り除く他、アルコールや虫除けスプレーも有効です。
登山の後や入浴時に、しっかりと体をチェックし、もしマダニが居た場合には早めに取り除きましょう。
もしご自身で取り除けた場合にも、マダニに噛まれた場合には必ず医療機関へ受診して下さい。
マダニは時に命に関わるおっかないヤツです。
十分に気をつけましょう!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
現在地から進むべき方向をコンパスに示させる方法

登山の基礎技術でありながら、なかなか習得が難しい地図とコンパスの使い方。
いっぺんに覚えようとしてもなかなか難しいので、少しずつ覚えていきましょう。
まずは地図とコンパスの基本中の基本。
現在地から次に進む方向を、コンパスに示させる技術をお伝えします。
分岐の度に現在地を確認し、進むべき方向を確認することで、その道が本当に正しいのか、どちらに進むべきなのかが分かります。
こまめな現在地確認と進行方向確認こそが、道迷いを無くす最大のポイントとなります。しっかりと身につけましょう!

.
.
登山におけるコンパスの使い方の超基本
~ 現在地から進むべき方向をコンパスに示させる方法 ~
山岳遭難事故の半数以上は道迷いが原因で発生しています。
特に森林限界以下の山域で起こりやすく、道迷いをきっかけに滑落・転落事故から死亡事故につながっているケースも多い様です。登山を行う上で、地図とコンパスを使ったナビゲーションスキルを身につけることはとても重要であると言えます。
道迷いを防ぐためには、ピークやコル、分岐など、明瞭に分かる場所ごとに現在地を確認する事。そしてそこからの進行方向を確認することが大切です。
特に分岐での確認は重要で、今いる分岐が本当にイメージしている分岐と同じ場所なのかどうかを確認する必要があります。
地図上の分岐と分岐の間にも、獣道や作業道、バリエーションルートなど、明瞭な踏み跡がある場合があります。地図だけを見て、「よし、次の分岐を右だな」などと認識して歩くと、うっかり本来の登山道では無い踏み跡を辿って道迷いを起こしてしまいます。
今自分自身が立っている分岐が、本当にイメージしている分岐とあっているのかどうかを確認する意味でも、分岐の度に地図とコンパスを取り出し、進む方向をコンパスに示させて確認することが大切です。
ますはそのやり方をしっかりと身につけましょう。

道を進んでいたら分岐が現れました。
一つ前の分岐で確認したところ、次の分岐を左とありましたが、この分岐の左側の道は踏み跡が不明瞭で確信が持てません。
地図とコンパスを使い、本当にこの道で正しいのか確認してみましょう。

想定される現在地はここです。

現在地から進みたい方向の登山道にベースプレートコンパスの定規を合わせます。
この時、コンパスの向きを間違えないように注意しましょう。
コンパスのノースマーク側(写真のコンパスであれば左の赤い三角形側)を進みたい方向に向けるようにしましょう。

カプセル内の線と地図の磁北線を平行にします。
この時も、地図の向き、北と南を間違えないように注意しましょう。

ベースプレートコンパスを胸の前にまっすぐ持ち、地面とコンパスが平行になるように持ちます。
コンパスは固定したまま、体を回転させて、カプセル内のノースマーク(赤い矢印)と方位磁針の北をぴったりと一致させます。

この時示している方向が、本来進むべき方向です。
道の角度とコンパスが示す方向があっているので、どうやらこの道で正しそうです。
※ 実際のナビゲーションでは、方位の合わせ、地形図と実際の地形の照らしあわせ、高度計と地形図が示す高度、GPSの補足位置と実際の地形など、複合的な情報から判断して下さい。どれか一つだけの情報を頼りに確信してしまうのは危険です。
また、いつでも"間違えている可能性もある"事を忘れずにいて下さい。
ナビゲーションに完璧はありません。間違えていることに気がついた時、素早く補正していくことが重要です。
ここでお伝えした確認方法や進行方向の示し方は、ナビゲーション技術の基礎です。
まずは普段の登山で、道標があるような明瞭な場所でも毎回必ず確認するクセを付けましょう。
何度もこの作業を行っているうちに、気がつけば技術は高まっていきます。
何度も繰り返して行うことが大切です。
道迷いに対するリスクを減らせば、山は大幅に安全度を増します。
登山者として最低限身に付けたい重要な技術ですので、しっかりとマスターしましょう!
皆さまの安全登山にお役立て下さい^^
よりしっかりと学習したい方は講習もご利用下さい!

ワンコイン座学講習 / 地図の読み方、コンパスの使い方
お仕事帰りに新宿駅徒歩5分の教室で学べる、ワンコイン座学講習シリーズです。
地図の読み方とコンパスの使い方の基本を、僅か500円で学ぶことができます。
山岳遭難事故の半数以上が道迷いを起因として発生しています。言い換えれば、確実な山岳ナビゲーションスキルを身につけることで、山の危険は半分にまで減ることとなります。是非この機会に学習しましょう!!

ワークショップ / コンパスの基本マスター講習
コンパスの基本マスター講習では、基礎中の基礎となる地図とコンパスの使い方を学習します。
お仕事帰りにご参加頂ける時間帯での開催となり、2時間で基本をしっかりと身につける事ができる内容となっています。
一回2000円と、低価格に学べることも大きな特徴の1つです。

山岳ナビゲーション講習
山岳ナビゲーション実践講習では、藪を漕ぎ、沢をツメる、登山道を外れた本格的な環境でナビゲーション技術を学んで頂きます。しっかりと身に付け、山の安全に役立てましょう!
一日かけてしっかりと学びます。
登山初心者はもちろん、経験者もかなり楽しめる内容となっています。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山の持ち物

登山には様々な道具を用意する必要があります。
大自然の奥深くにまで足を踏み入れるアクティビティである登山では、その自然の脅威から身を守るための様々な装備が無いと時に命に関わります。
時期や場所、山行形態によって持っていく装備は変わりますが、ここでは最低限どんな山にも持って行くべき道具を選定してご紹介します。
ここに上げている道具は、どんな山行にも必ず用意すべき基本セットとなります。
参考にして頂ければ幸いです。
皆さまの安全登山にお役立て下さい。

.
.
登山の持ち物
登山は大自然の奥深くまで足を踏み入れるアクティビティです。
常に変化する気象条件から身を守るために、様々な道具を用意しておく必要があります。
ここでは、最低限必要な道具を紹介していこうと思います。
① バックパック
不整地を歩くために、両手を開けて行動する必要があります。
また重たい荷物を背負っても体が安定するよう、登山用に開発されたバックパックを用意する事をおすすめします。
日帰りで20L~30L、小屋泊で30L~40L、テント泊で50L~60L程度のバックパックが必要となります。
② 雨具
周囲が海に囲まれている日本では、山間部の天候がとても変わりやすい傾向にあります。
悪天予報時に山に入るべきではありませんが、仮に晴天の予報であったとしても、山だけ雨が降るような事も往々として起こります。山に入る以上、例え降水確率0%であったとしても必ず雨具を用意する必要があります。
雨具はゴアテックスなど、防水透湿素材のレインウェアが優れています。
水滴は通さず、湿気のみ通す素材な為、汗に寄る濡れ戻りを緩和してくれます。防水透湿素材のレインウェアが開発されたことにより、山での死亡率は激減しています。必ず防水透湿素材のレインウェアを上下とも用意しましょう。
③ 防寒着
山に入る以上、冬はもちろん、夏でも防寒着は持つべきです。
標高が100m上がる毎に、気温は0.6度下がります。風速が1m上がる毎に体感気温は1度下がります。
例えば東京で気温30度の真夏日でも、高度3,000mでは12度しかありません。この環境で風速10mのやや強い風が吹いていたら、実際に体が受ける温度は気温2度の状況と同等。東京の2月の最低気温と同程度です。
また低山においても沢での濡れや、万が一のビバークの際に低体温症を引き起こす可能性もあります。
仮に使わなくても、緊急時のための装備として外すべきではありません。
ちなみに、僕の場合は化繊の中綿を使用した防寒着を使用しています。ダウンより嵩張りますが、濡れても保温力がほとんど低下しない特性を持っています。また乾きも早いのでおすすめです!
④ 着替え
シャツやパンツ、靴下などの下着類だけで構いませんので、着替えも用意しておきましょう。
濡れた衣類は、乾いた衣類の20倍ものスピードで体温を奪います。汗や雨などで濡れた衣類のまま停滞すると、あっという間に低体温症で命を落とす場合もあります。乾いた衣類をもっておくことはとても大切です。
必ず化繊、またはウールのものを用意しましょう。
⑤ ヘッドライト
日帰りの予定であったとしても、必ずヘッドライトを持ちましょう。
捻挫や疲労、道間違えなど、僅かなトラブルで日没してしまうことは往々としてあります。状況によってビバークすべきか下山すべきか判断しなくてはなりませんが、いずれの場合も光がなくては何もできません。
両手が開けられる光源であるヘッドライトは必ず必要です。また替えの電池も用意しましょう。
⑥ 地図とコンパス
山岳遭難事故の半数以上が道迷いによるものです。地図とコンパスも必ず持ちましょう。
バックパックに入れてしまうと、なかなかこまめに確認することができません。小さなポーチなどを用意し、いつもすぐに取り出せるようにしておきましょう。
国土地理院の25000分の1地形図と、ベースプレートコンパスを用意しましょう。
地形図の読み方やベースプレートコンパスの使い方は、登山技術の基礎中の基礎です。講習会などで学び、必ず使えるようにしておきましょう。( Kuri Adventures のナビゲーション講習はこちら! )
また高度計やGPSも合わせて持つことで、ナビゲーションはずっと楽にになります。
⑦ ツェルト
上記したように、山での低体温症を防ぐには"濡れと風"から身を守る事が大切です。
万が一ビバークせざるをえなくなった時は、自分のまわりに対流し難い空気の層を生み出すことが大切です。
まず乾いた衣類に着替え、防寒着や雨具など、着れるものは全て着込み、その上でツェルトなどを設営して雨風から身を守ります。バックパックなどで地面からの断熱もしっかりと行い、ひたすら耐え抜きます。
ツェルトを持たなかったために失われた命もたくさんあります。
必ず持つようにしましょう。
⑧ ファーストエイドキットとエマージェンシーキット
山での不意な怪我や病気から身を守るために、ファーストエイドキットを用意しておきましょう。
止血を行うためのガーゼや、関節を固定するためのテーピングテープ、頭痛薬や下痢止め、目薬など、山で起こりえるトラブルを想定して必要なものを用意しましょう。
またエマージェンシーキットも重要です。これも何か決まったセオリーがあるわけではありませんが、万が一の緊急時に備えた道具を想定して、自分にとって必要なものを用意しましょう。
個人的には、エスビット(固形燃料)、ライター2つ、小さなのこぎり、ガムテープ、糸と縫い針、ホイッスル、靴紐、エマージェンシーシートなどを持つようにしています。(緊急時に暖や狼煙のための焚き火を行うための装備が中心です。)
⑨ 予備のバッテリー
スマートフォンの外部ポータブルバッテリーや無線機の予備バッテリー、ヘッドライトの電池など、予備のバッテリーは必ず用意しましょう。
特にスマートフォンのポータブルバッテリーはとても重要だと思います。緊急時の連絡やGPSによる現在地確認、ヘッドライト故障時の予備照明、メモや写真による記録など、一台で何役もこなしてくれる素晴らしい道具です。
バッテリーが切れやすい弱点を、容量が多めのポータブルバッテリーで補うことでとてもこころ強い道具となります。
またヘッドライトのバッテリーも、必ず予備を持ちましょう。
⑩ トイレットペーパー
意外と忘れがちですが、無いと困るのがトイレットペーパー。山のトイレにはトイレットペーパーがない場合も多く、またそもそもトイレそのものが無い山もたくさんあります。必ず用意しておきましょう。
またゴミ袋も用意しておきましょう。トイレットペーパーを持ち帰らなくてはならないトイレもありますし、野で用を足す場合も必ずトイレットペーパーは持ち帰らなくてはなりません。(繊維に石油系薬剤が使用されているので、自然には還りません。)
⑪ 水と食料
水と食料も必ず必要です。
水は少し余裕を持って、大凡 2L ~ 3L 程度を目安に用意しましょう。(2時間/500ml程度消費します。)
食事は、昼食(泊まりの場合には3食)の他に、行動食と非常食を用意しましょう。
登山は消費エネルギーがとても大きく、日帰りの簡単なハイキングでもフルマラソン程度のカロリーを消費します。
この為、行動中にもエネルギーを摂取しないと、ハンガーノック(エネルギー切れ)を起こしてしまいます。
ミックスナッツやドライフルーツ、チョコレートバーなどがおすすめです。個人的にはウィダーにしている事が多いです。
非常食は、緊急時以外手を付けない食事です。加熱せずに食べられる、十分なエネルギーを摂取できるものが好ましいです。
それぞれ分けて用意しておきましょう。
荷物を軽くしたい思いでつい省きたくなってしまうものですが、ここに載せた装備は最低限用意すべき荷物です。
これを基準に、山行に合わせて加えて必要な道具を用意しましょう。
皆さまの安全登山の為のご参考にして頂ければ幸いです^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.7.20 マルチピッチクライミング体験 "小川山ガマルート"

日本のヨセミテと名高いクライミングゲレンデ"小川山"にある、メジャーな初心者向けマルチピッチクライミングルート”ガマルート”に、常連のお客様お二人と共に足を運びました。
ガマルートは実際のグレードより難易度が高く感じるシビアなスラブの登攀を求められます。しっかりと握れるガバは少なく、足のフリクションを信じて登っていく、なかなかスリリングなクライミングを楽しめます。
この日はとても良く晴れ、素晴らしい一日となりました。
ご参加ありがとうございました^^

Kuri Adventures では、講習で学んだ技術を実際の山行において経験を重ねて頂く、実践登山も行っています。
この日はマルチピッチクライミングの流れを経験して頂く為、常連のお客様お二人と共に小川山へやってきました。
小川山は"日本のヨセミテ"などと呼ばれるほど、たくさんのクライミングルートがある、大変素晴らしいロケーションのクライミングゲレンデです。その小川山にある無数のルートから、今回はガマルートを選択。
公表グレードより難易度が高く感じる、シビアなスラブが中心のルートで、手が悪く、スメアリングによる足の摩擦を信じて登るしかありません。なかなかスリリングなルートです。
それでもマルチピッチクライミングの入門的なルートなので、総合的な難易度は低め。
それでありながら、岩の塔のてっぺんに立てる、とても気持ち良いルートです!
最後は50mの懸垂下降も楽しめ、充実した一日を過ごせると思います。
この日の前日は、いつもご利用頂いている常連様のお誕生日。
下山後にシャンパンファイトのサプライズで大盛り上がり♪
宮﨑様、31歳お誕生日おめでとうございます!!
.
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.7.17 山岳ナビゲーション実践講習

山岳ナビゲーションの実践講習を行いました。
高尾山から国道20号線を跨いだ向こう側の山域で、登山道を外れて行う本格的な読図講習です。
道無き藪をかき分け、沢床を彷徨い、四つん這いになって急峻なツメを登り、灌木を握り伝いながら斜面を下る。そんな冒険的な登山を行いながら、自然地形のヒントを頼りに現在地を割り出します。
本物の大自然の中で、道標もなく、道もなく、視界も悪い。その環境で学んでこそ、本当の意味で技術が身に付くと信じています。

山岳遭難事故の実に50%以上は、道迷いが原因で起きています。
登山技術において読図能力がとても重要であることは言うまでもありませんが、その技術は奥深く、なかなか身に付けるのが難しい技術でもあります。多くの人は読図能力を身につけることを諦めてしまいます。
だって、読図なんて出来なくたって、登山を楽しめちゃうんですから。
日本の有名山域ではしっかりと登山道が整備され、道標も立ち並び、地図もコンパスも一度も取り出さなくたって目的地に辿りつけちゃいます。
そして、だからこそ遭難事故は後を絶ちません…。
大動物の獣道や林間作業道、一部のクライマーしか踏破することが難しいバリエーションルートへの道など、登山道と見間違える可能性のある枝道はたくさんあります。
登山道を一歩外れれば、そこは皆さんが思っているより遥かに厳しい環境だったりします。
Kuri Adventures の山岳ナビゲーション実践講習では、あえて登山道を外れた場所で講習を行います。
人の手が入らない本物の大自然の中で、藪を漕ぎ、沢床を彷徨い、四つん這いになって急峻なツメを登り、灌木を握り伝いながら斜面を下る。そんな冒険的な登山を行いながら、自然地形のヒントを頼りに現在地を割り出します。
もし道迷いを起こしてしまったらどの様な環境に立たされるのか?
そこから安全に脱するために必要な技術はどの様なものなのか?
道無き大自然の深部で、どの様に現在地を割出すのか?
そんな技術を学んで頂きます。
しっかりと整備された登山道上ではなく、あえて登山道から外れた山域で講習を行うことで、より生きた技術を身に付けて頂けると信じています。
この日も、4人のお客様にナビゲーションスキルを学んで頂きました。
ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました!!
山で自分の居場所が分かる能力。その場所から次のポイントに移動する方向を割出す能力。これらを身につけることは、登山者にとってとても重要な事です。
皆さまのご参加も、心からお待ち申し上げております^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.7.16 登山のセルフレエスキュー講習

今日は登山のセルフレスキュー講習でした。
3連休の初日とあって、皆さま山登りに出かけられているのでしょうか?
いつもは人気のこの企画も、今回はお二人のみのご参加。
その分、より濃密に学習して頂くことが出来たのではないでしょうか^^
セルフレスキュー技術は、万が一に備えて是非覚えておいて頂きたい大切な技術です。一言にセルフレスキューと言っても巾が広いので、ここでは一般登山におけるセルフレスキューに必要な技術に特化して指導しています。
しっかりと身につけておきましょう♪

今日は登山のセルフレスキュー講習でした。
Kuri Adventures の一般登山向けセルフレスキュー講習では、トレッキングポールを使った松葉杖の作り方、120cmのナイロンスリングを使用した背負い搬送技術、トレッキングポールとレインジャケットで作る担架搬送技術、レイジングシステム(倍力システム)による引き上げ技術、ツェルト設営技術などをお伝えしています。
パーティーメンバーが滑落したことを想定し、駆けつけ、担ぎ、ロープで引き上げ、担架搬送し、救助が来るまでの間ツェルトで保温保護すると言ったシュミレーションをイメージしながら行います。
たくさんのシステムを覚えたり、実際に人を背負って急峻な斜面をよじ登ったり、ロープで引き上げを行ったりなど、なかなかハードな講習内容だと思います。
しかしその分、より実践的な内容になっていると思います。
セルフレスキュー技術は、役立つ日が来ないほうが良い技術です。
しかし万が一そのような瞬間が訪れてしまった時、大切な仲間を救う、とても重要な技術です。
しっかりと身に付け、安全登山に活用しましょう!!
ご参加ありがとうございました^^

.
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.6.26 小川谷廊下 遡行

西丹沢が誇る代表的な名渓"小川谷廊下"で沢登りを楽しんできました!
廊下とは、水が岩を削りとったゴルジュ地形を指します。まさに水の廊下と言うに相応しい、岩壁に阻まれた独特な景観を楽しめます。
小川谷は2級の沢。初心者が楽しめるギリギリの範囲の難易度です。
体を押し戻す水量の滝に、シビアなムーブのクライミング。登山者としての総合的な能力を求められる、刺激的な沢登りが楽しめます。
今回は梅雨の半ばにも関わらず、とても恵まれた天候の中での沢登りを楽しめました。
そんな様子をブログまとめましたので御覧下さい。

昨日は小川谷廊下の沢登り企画を行いました。
Kuri Adventures で登山技術を学ばれているお客様を中心に、実戦経験を積んで頂く機会として、様々な参考企画もご用意しています。特に沢登りは、登山者を強くします!
登山の総合格闘技と称される沢登りは、あらゆる登山技術を要求されます。
不安定な地形での安定した歩行技術。危険箇所での確保技術。素早いロープワークに、シビアな読図能力、ルートファインディング能力など。
沢登りは、登山者を著しく成長させるとても良い環境です。
小川谷廊下は、遡行グレード2級の沢。沢登り初心者がギリギリ行ける範囲の沢です。
西丹沢を代表する美渓で、ゴルジュ地形が特徴的で、水の透明度が高く、その美しさに皆息を呑みます。
初心者にとってはハードな山行となりますが、だからこそ学べることも多いのではないでしょうか?
.
予定よりずいぶんと時間がかかってしまったり、例年よりも多い印象のヤマビルに悩まされるなど、少々のトラブルもありましたが、それを含めての沢登り。アルパインクライミングとは、そのような困難を乗り越えることも含まれていると思います。
沢登り初心者にとっては少しハードな山行だったかも知れませんが、その分より多くの事を学べたのではないかと思います。
ご参加頂きました皆さま、ありがとうございました^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.6.24 支点構築技術講習

マルチピッチクライミングやアルパインクライミングに必須の技術となる、支点構築技術のワークショップを行いました。
支点は、パーティー全体の命を支える要。でも、支点構築は一人で行い、他の人からのチェックを受けることが出来ないシステム。1つのミスが、自分も仲間の命も危険に晒す事になります。
だからこそ確実に覚え、一切のミスが内容にシステムを作らなくてはなりません。
何度も練習し、しっかりと身に付けて頂きたいものです。
そんな講習の内容をブログにまとめました!

三軒茶屋の中古登山用品販売店 "Froh" (http://froh.tv/brands/topic/001999.html) を会場にお借りし、支点構築技術に関するワークショップを行いました。
支点構築技術は、アルパインクライミングやマルチピッチクライミングなど、スタカットビレイを行う上で絶対に必要となる重要な技術です。この支点がパーティー全体の命を守る要となる為、確実なシステム構築が求められます。
しかも、支点構築を行うときは自分一人しかいません。
ミスを指摘していくれる仲間はいないので、絶対にミスは許されないシビアな技術でもあります。
この講習では、5〜6人程度のチームに分かれて、お互いにインプットとアウトプットを繰り返しながら順番に支点構築を繰り返すことで、短時間で基本的なシステムの作り方を覚えて頂くことが出来ます。








責任の重い技術ですが、しかしこのシステムをしっかりと身につけることで、高い安全を得ることができる技術でもあるんです。
この講習で学んだ段階では、まだご自身の技術として確立した訳ではありません。
各自が日々何度も練習を繰り返す事で、少しずつ技術として身についていきます。
一切悩まず、手を止めず、スムーズな流れで支点構築できる様になるまで練習を続けましょう!!
より安全に、もう一歩先の登山を目指すために、しっかりとご自身の技術として身に付けて頂きたいものです。
この日は11名のお客様にお越し頂けました。
ご参加頂きました皆さま、ありがとうございました!
またのご利用も心よりお待ち申し上げております^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.6.11 第四回 夏山フェスタ にて、講演会を行いました!

名古屋で行われている、東海地区最大の登山系イベント"夏山フェスタ"で、400人規模のお客様を前に講演させて頂くチャンスを頂きました。
過去には8000m14座全山登頂の竹内洋岳氏や、エベレスト世界最高齢登頂記録保持者の三浦雄一郎氏、私たちJMIA
日本インストラクターズ協会理事長の岩崎元郎など、業界の大御所たちが立った舞台。今回もイッテQ登山隊の国際山岳ガイドの角谷氏や、山岳気象予報士の猪熊氏、グレートトラバースの田中陽希氏など、著名人ばかり。
何故呼んで頂いたのか分かりませんが、大きなチャンスと考え、本気で講演してきました!!

2016年6月11日〜12日、毎年名古屋で行われている東海地区最大の登山系イベント"夏山フェスタ"が、第四回目となる今年も開催されました。
登山用品メーカーさんや山岳地域の観光協会、山小屋などが行う出展ブースと、山業界の様々な専門家が行う無料の講演会を楽しむことができるイベントです。
過去には8000m14座全山登頂の竹内洋岳氏や、エベレスト世界最高齢登頂記録保持者の三浦雄一郎氏、私たちJMIA 日本インストラクターズ協会理事長の岩崎元郎など、業界の大御所たちが立った舞台。
今回もイッテQ登山隊の国際山岳ガイドの角谷氏や、山岳気象予報士の猪熊氏、グレートトラバースの田中陽希氏など、多くの山業界著名人が講演を行いました。無料とは思えない豪華なメンバーです!
どーゆー訳か、そんな大舞台に、何故か僕も立たせて頂くことに…。
400人ものお客様を前に、公演する事となりましたΣ(゚Д゚)
こんな大きな舞台ははじめてでとても緊張しましたが、これもまた大きなチャンスと捉え、全力でいつものノリな講習会を遂行!
今回は"登山装備とセルフレスキュー"と題した、装備の重要性に関するお話をさせて頂きました。
これまで経験したことのないシチュエーションでの講演会でしたが、終了後多くの方から"とても良かったよ"とメールやメッセージを頂き、ちょっと安心しました。
ご来場頂きました皆さま、この様な大きなチャンスを頂きました中部経済新聞社さま、推薦して下さいました駅前アルプスの千葉様、本当にありがとうございました!!








この大きな経験を糧に、もう一歩成長できたような気がします。
日本で一番わかり易い登山技術講習を行うインストラクターを目指し、日々精進して参りたいと思います。
再び大きな舞台に立たさせて頂くチャンスを得られるよう、毎日を頑張ります!!
ありがとうございました!!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
おすすめトレッキングポール "HeliNox LBB120"

HeliNox の LBB120 と言うトレッキングポールが秀逸です。
トレッキングポールを使っている方は分かると思いますが、使わない時ってけっこう邪魔になりません?
枝に引っかかったりして、進行を妨げられたりします。
また出し入れが頻繁なときは、なかなか手間だったりもしますよね。
HeliNox LBB120 は、そんなトレッキングポールの不快なお悩みを一挙解決してくれちゃった素晴らしいアイテムです!!

登山者であれば知らないものもいないであろう、あのメスナーの命を助けた道具。それがトレッキングポールです。
ある時メスナーがクレバスに転落。
しかし偶然にも手に持っていたトレッキングポールが氷の壁に挟まり、なんとか一名をとりとめました。
長さを自由に変えられる特性を活かし、トレッキングポールを足場にしながら交互に足場を作り、氷の溝からどうにか脱出したとの逸話を持つ、伝説の道具なのです。
まぁそんな奇跡の為に持つ道具ではありませんが^^;
トレッキングポールは登りでの推進力と、下りでの足腰への負担軽減。渡渉時の水ぽちゃ防止に、豪雪のラッセルのお供に。そんな歩行補助にとても 役立ちます。
また他にも、緊急時の背負い搬送や簡易担架の作成に使用したり、ツェルトやタープを立てるのにも役立ちます。
トレッキングポールに関して賛否ありますが、個人的には推奨派です。

.
しかしそんなトレッキングポールにも大きな弱点があります。
岩場や鎖場、ハシゴなどが連続する区間では、トレッキングポールはバックパックの脇などに挟んで携行する事が多いと思います。
多くのトレッキングポールは伸縮時の長さが60㎝前後。
バックパックの全長よりやや長いために、雨蓋より上に飛び出してしまいます。
これに木の枝などがひっかかり、とても鬱陶しいく感じませんか?
僕はトレッキングポール推奨派ながら、枝やロープが引っかかるのが嫌で、最近はあまり持ち歩かなくなっていました。
しかしついにステキなトレッキングポールと出合いましたよ!それが " Heli Nox " の " LBB120 " です。
最大120㎝と標準的な長さを備えながら、その収縮サイズは51㎝と平均的なトレッキングポールの収縮サイズよりも10㎝程度短く収まっています。
そのヒミツは特殊な4段収縮にあります。
一般的なトレッキングポールの多くは3段収縮ですが、1段分多く収縮させることでよりコンパクトになります。
それでいながら、テント用ポールの大手メーカーとして有名なDAC社がシャフトの製造を請け負っていることもあり、1本あたり250g程度と軽く、さらに強度的にも強いのも魅力です。
さらに、その伸縮の手間の少なさも大きな魅力です!
なんと先端を引っ張るだけでトレッキングポールが伸びます!!
1つだけあるロックフリップを起こして長さを調整すれば使用できるので、これまでの半分の手間でトレッキングポールを伸ばせます。
また収納時も、フリップを起こして先端から押しこむだけ。それでもう、最小サイズまで一気に収縮できます。
出し入れの手間が減ることは、岩場や鎖場、ハシゴなどが時折現れる、急峻な山道などでとても有利に働きます。
これはとても便利です!

.
トレッキングポールを使用される方で、買い替えを検討されている方や、現在トレッキングポールをお探しの方の参考にして頂けたら嬉しいです^^
Heli Nox LBB120 なかなか良いと思いますよ♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山のロープワーク " もやい結び "(ボーラインノット)

結びの王様"もやい結び"を覚えましょう!
ボーラインノットとも呼ばれる結び方で、昔はクライミングの確保にも使われた結び方です。たいへん強固で、それでいながら強いテンションがかかった後でも解きやすい特性を持っています。
緩みやすい、開き方向に弱いと言う欠点があるので、現在ではクライミングで使用されることはありませんが、それでも緊急時の確保には今も現役で使われます。
ツェルトやタープの設営時などにも便利です。

もやい結びは、結びの王様と呼ばれています。
素早く簡単に結べ、人の体重がかかってもびくともしない強固な結びで、しかも解きやすい。これだけ使いやすい結び方は他にそう無いかもしれません。
その昔はクライミングの安全確保にも使われていたほどで、その信用度は高いものです。
また現代においても、レスキューのシーンや緊急時には、多く使われている結び方です。
しかし欠点もあります。
解きやすいと言うことは、すなわち緩みやすいと言うこと。
クライミングに使う結び方がもやい結びからエイトノットに切り替わったのは、クライミング中の動きで自然にロープが解け落ちるトラブルが起きていたから。また輪を開く方向へは結束が弱く、間違えて輪を内側から開く方向に力が加わるといとも簡単に解けてしまいます。
これらを知らずに使った方が多くの事故を起こした為、現在ではクライミングで使用されなくなりました。
もやい結びを使用する時は、必ず ダブルフィッシャーマンズノット で末端処理を施しておきましょう。また、緊急時を除き、原則的に人の命に関わる部分への使用は避けた方が良いかもしれません。
それでも、結びやすくて解きやすいもやい結びは、覚えておくととても便利です。
タープやツェルトを設営する際に、木と木にロープを渡したりする際の結びに使ったり、ロープの末端をロープバッグに結んでおくのに使ったりと、出番の多い結び方です。
使い方の注意点も含めて、是非覚えておきましょう^^

ロープを対象物に巻きつけます。

末端側では無い方のロープを1回捻じり、輪を作ります。

末端側では無い方のロープを、2つに折って輪に通します。

その先に出来た輪に末端を通します。

末端を折り返し、末端側のロープ2本を握ります。

末端では無い方のロープを引っ張り、末端側のロープが最初に作った輪を通り抜けるように締め上げます。

この写真の形になっていれ、正しいもやい結びとなります。

そのままだと緩み易いので、ダブルフィッシャーマンズノットで末端処理を行います。
もやい結びは、とても便利な結び方です。
また緊急時に素早く片手で結べる、結び方でもあり、ピンチの際にあなたの命を守る結びとなるかもしれません。
何より、ロープワークの王道の結び方。是非覚えておきましょう!
Kuri Adventures では、気楽に参加できる登山教室を行っています。登山教室で講習を受け、安全登山にお役立て下さい♪
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームな講習会ですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
プロトレック PRG270

カシオのプロトレックを購入しました^^
コンパス、高度計、温度計が装備された高機能な腕時計でありながら、17,000円と比較的低価格で購入することが出来ました!
これまでアナログ装備がベストであると考えておりましたが、いやはやこれは便利ではありませんかw
登山用の腕時計、間違えなく山の安全に貢献してくれる装備です。

最近、時計を買い換えました。
これまで、圧倒的な強度を持つ G-SHOCK を愛用してきました。どんな使い方をしても壊れること無く時を刻み続けてくれる G-SHOCK は、僕の中で絶対の信頼を持っています。中学生の時に山を始めてから、現在に至るまで僕の腕にはいつも G-SHOCK。
しかし最近、その G-SHOCK 人生が終わりを告げました。
G-SHOCK と同じカシオ社製の登山用時計 プロトレック PGR-270 を購入したんです。
G-SHOCK にも引けを取らない耐久性を持つプロトレックシリーズは、それに加え登山に便利ないくつもの機能を備えています。
方位磁石、温度計、高度計。
これまでアナログこそ最良だと信じてきましたが、プロトレックのそれは想像以上に便利なものです。
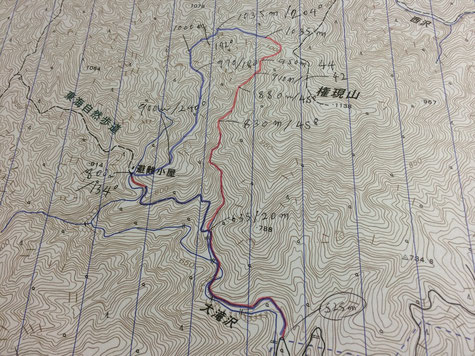
.
僕の場合、ルート上の各分岐の標高と次に進む方向の方位を地形図にメモして起きます。こうしておくことで、コンパスで確認する時に簡単に方向が確認できます。
高度計で今いる分岐と地形図上の分岐を照らし合わせ、次に進むべき方向をコンパスで確認した上で進みます。この時、高度計に出る微細な誤差も修正しておきます。
これまでは地形図とコンパスをそれぞれバラバラに出し、それぞれで確認していましたが、これが一つの道具にまとまっているんです。
それがいつも自分の腕についていて、簡単に表示することができる。
これは想像を遥かに上回る便利さです!
この手軽さこそ、山の安全にもっとも貢献してくれると言えます。
山岳遭難事故の約半数が、道迷いを起因として起きています。つまり道にさえ迷わなければ、山の危険は半分にまで抑えられる事となります。
道迷いは、うっかりと登山道から外れてしまい、どこにいるか分からなくなるから戻れなくなります。
だいたいどの辺にいるのか把握する為には、こまめな現在地確認が必要です。
この手間をとにかく減らし、一日に何度も現在地確認を行うことを怠らなければ、恐らく道迷いによる遭難の大部分が減らせると考えられます。
腕時計で手軽に方位や高度を確認できるということは、結果として山の安全に大きく貢献してくれることとなると確信しています。
もちろん、アナログな道具が不要になるわけではありません。
地形図上に進むべき方向の方位を書き出す際にも、ベースプレートコンパスを使ってその方位を測ります。
また実際の山の中でも、積極的に使う場面が現れます。
やはりどちらが重要な道具であるかと問われれば、それはアナログなベースプレートコンパスです。僕は予備も持って行きます。
しかしそれとは別に、こまめに方位と高度を確認できるのはとても良いことだと思います。
現在地確認をいかに手軽にできるか。
そしていかに事前準備を活かし、ナビゲーションの手間を減らすか。
これが重要です。
皆さまも是非、山に入る前に分岐となるポイントなどの標高や、その後進むべき方向の方位を調べてメモしておきましょう。
その上で、プロトレックなどの多機能腕時計を使ってこまめな確認をすることを推奨します。
これができると安全であることはもちろん、きっとますます山が楽しくなりますよ♪
おすすめです!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
デジタル簡易無線のおすすめオプションパーツ

デジタル簡易無線のおすすめオプションパーツをご紹介します。
登山で使う場合、これらを加える事でずっと使いやすくなります。
こうしたオプションパーツでカスタマイズを楽しめるのもまた、デジタル簡易無線の良い所だと思います^^
今回は僕が愛用しているロングアンテナSRH350DHと、ICOM純正オプションの大容量バッテリー、スピーカーマイクをご紹介します!

デジタル簡易無線のオプションパーツをご紹介します。
様々なオプションパーツによりカスタマイズを楽しめるのもまた、デジタル簡易無線の良い所だと思います。
そして、そのカスタマイズによって明らかに性能アップするのもまた、男心くすぐる魅力ですね!(女子には伝わりにくいかも!?)
今回は僕が愛用している3つのオプションパーツをご紹介します。
◯ ロングアンテナ:第一電波工業株式会社 SRH350DH
デジタル簡易無線のハンディ用アンテナとしてはもっとも長い、43㎝ものロングアンテナです。
その性能は絶大で、1W運用時の電波の飛びが凡そ2倍。5W運用時の電波の飛びに至っては、実に3~4倍程度と飛躍的に性能が向上します!
ノーマルアンテナ状態では、1Wも5Wも僅かな通信距離の差しか出ませんが、アンテナを交換した場合には遥かに5Wの方が高性能になります。また言い換えれば、1Wでもアンテナさえ交換すれば、ノーマルアンテナの5Wを遥かに凌ぐ通信距離を稼げることになります。
アンテナ自体は柔らかく曲がるので、バックパックの中に収納して持ち運べます。
例えば通常時はノーマルアンテナで仲間と更新し、不特定多数に情報発信する場合や、緊急時連絡の際に長いアンテナに付け替える様な使い方がより現実的でしょう。
アンテナの付け替えで、簡単に高性能化できるのは魅力的です!
◯ 大容量バッテリー:ICOM BP271
通信回数が多くなると、どうしても心配なのがバッテリー…。
5W運用ならば頻繁な更新で凡そ2~3時間。1W運用でも3~4時間持てば良いでしょう。実際のバッテリー持続時間も、1Wタイプのデジタル簡易無線で、0.2W運用を中心に行って、だいたい10時間程度ってところです。
登山に使うには少し心肺なバッテリー持続時間ですね。
そこで大容量バッテリーの登場です!
大容量バッテリーを1Wタイプのデジタル簡易無線で上記の様な使い方をした場合、大凡20時間。2泊3日の山行程度ギリギリ保つくらいの容量となります。ノーマルバッテリーを予備に持てば、遭難対策装備としても安心感がありますね!
◯ スピーカーマイク:ICOM HM-186LS
無線機って、案外大きくて邪魔に感じるんですよね。特にロープを使う山行の場合、アンテナにロープが引っかかってうっとおしい事も…。
そんな時に便利なのがスピーカーマイクです!スピーカーマイクも防水仕様。沢登りでも、雨降りでも使えるのは安心です。
例えばバックパックの雨蓋にデジタル簡易無線本体を入れ、チェストハーネスにスピーカーマイクだけ取り付けておくみたいな使い方が便利です!雪山では、内ポケットに本体を入れてバッテリー電圧の低下を防ぎつつ、スピーカーマイクだけ襟元にクリップしておくなんて使い方も良いですね^^
クライミングのコールをする時なんかにとても便利で、大水量の滝でも、風が強い時のマルチでも、これなら簡単に会話ができます。
見た目にも、いかにも通信機器を使ってる感がカッコイイですしねw
この様に、必要に応じて様々なオプションパーツを組み合わせ、自分好みにカスタマイズできるのもデジタル簡易無線の大きな魅力だと思います。またそのホビー性だけでなく、実際の性能にも大きく影響するのもまた大切なポイントです。
いろいろなアイテムがあるので、じっくりと選んでみましょう^^
ご参考に頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
デジタル簡易無線の箱を開けてみた。

デジタル簡易無線って良さそうだなって思っても、どこに売ってるのやら?
現実的にはあまり置いているお店もなく、インターネット通販で買うことが多いと思います。でもネット通販って、いまひとつ不安が多いものですよね…。
実際にデジタル簡易無線を注文すると、何がどの様に届くのか?
今回業務用にもう一台購入したので、その箱の中身を紹介します^^
けっこう親切なパッケージなので、ストレス無く始められますよ♪

デジタル簡易無線に興味を持っても、専門店などに足を運ばないかぎりまずほとんど売ってません。
現実的にはインターネット通販で購入するケースが多いでしょう。
でもネット通販って、どんな風に手元に来るか分からず、いろいろ不安もありますよね^^;
今回新たにデジタル簡易無線をもう一台購入しましたので、ここで皆さまと共に紐解いてみたいと思います!
ダンボールの箱を開けると、そこには何やらたくさんの書類が入っています。
デジタル簡易無線は登録局と言い、総務省の総合通信局に届出を出さなくてはなりません。
その提出書類一式と、とてもわかり易い書き方の見本が一緒に同封されています。
手元に届いたその日にすぐ書いて提出できるよう、予め郵便局で2,900円分の収入印紙を買っておきましょう!
届け出には個別登録と包括登録が選べますが、一生絶対に1台しか買わないと心に決めている方を除いて、包括で登録しといたほうが賢いと思います。一度包括で登録しておけば、その後は開設届けだけで簡単に数を増やすことができます。
その他箱のなかには、無線機本体、バッテリー、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、バッテリー、ACアダプター、充電器など、デジタル簡易無線をはじめる上で必要な道具が全て一式揃って入っています。
今回購入しましたICOMのIC-DPR3の場合、バッテリー単体だけでも充電器で充電できます。
週末の山だけでなく、毎日のお仕事にも活用される方にとってはとてもありがたい設計ですね^^
お店で説明を受けないと不安な方はともかく、ネット通販での購入でも特に問題無く始められる内容になっていると思います。
ご参考にして頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
デジタル簡易無線て何??

デジタル簡易無線ってご存じですか?
2008年に始まったばかりの無線制度なのですが、なんと免許無しで使える無線なんです。
それでありながら、アマチュア無線4級で使えるハンディ機と同じ、最大5w出力!
その上、業務、レジャー問わず使え、開放呼び出しチャンネルにて第三者を呼び出すことも、秘話コードを使って、仲間内だけで使用することもできる優れたシステムです。
これをみんなが持ったら、山の安全は確実に高まります!!

デジタル簡易無線をご存知でしょうか?
デジタル簡易無線とは、2008年に始まったばかりの無線制度なのですが、なんと免許不要で使える無線なんです!
しかもアマチュア無線四級で使用できるハンディ機と同じ、5w出力まで使えます。
見通しの良い稜線上などからなら余裕で10Kmを超える更新が可能となり、山中においても2km程度までは問題なく相互更新できるパワーを持っています。ロングアンテナを使えば、より遠くまで電波を飛ばす事もできます。
デジタル簡易無線は全30chあるのですが、15chだけは"呼出チャンネル"と呼ばれる、不特定多数に発信するためのチャンネルとなっています。
これに加え、5桁の秘話コードと呼ばれるパスワードを設ける事もできるので、仲間内だけの更新に使う際にも混線を防ぐことができます。
アマチュア無線のハンディ機と同じような条件ですが、免許不要と言う点がやはり大きな魅力でしょう。
免許が不要なので、仲間に無線を預けても法に触れません。(※ 届け出は必要です。)
また無線用語を使う必要が無いので、まさにトランシーバーのように使うことができます。
それでいながら開放チャンネルがあるので、登山中の危険箇所や天候状況、事故の救援依頼などをその山域にいるデジタル簡易無線を持つ他の登山者と情報共有する事ができます。
つまり、デジタル簡易無線を多くの登山者が持つことで、山の安全は飛躍的に高まるのではないかと考えられます。
免許取得の手間も無く、簡単な書類手続きだけで使えるデジタル簡易無線は、登山の常識を変える革命的なシステムかも知れません。
みんなで流行らせましょうw
ご共感頂けましたら、下のシェアボタンでシェアして下さい!!
Kuri Adventures では、少しずつデジタル簡易無線に関する情報をお伝えしていきます^^
※ 第三者にデジタル簡易無線を貸し出すときは、無線局の運用の特例に係る届出書を所轄総合通信局に提出する必要性があります。詳しくは総務省ホームページをご確認下さい。( http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html ) 項目番号4番
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
クライミングロープの洗い方

泥に汚れたままのクライミングロープを放置すると、繊維の劣化が早まります。
特に泥濘んだ泥や砂で汚れている場合、繊維内に粒子が入り込んでいる可能性があります。そのまま使用すると、内部の繊細な繊維の断裂を繰り返し、ロープの消耗が著しく早くなります。
定期的なロープの洗浄は、クライミングロープを長持ちさせる上で重要なメンテナンスとなります。しっかりと洗い、キレイなロープでクライミングを愉しみましょう^^

外岩でのクライミング、登山でロープを使用したりなど、クライミングロープは泥で汚れやすい道具です。
でも泥汚れに強い道具なのかと言うとそうでも無く、実はけっこうデリケートな道具であったりもします。
クライミングロープが泥に汚れると、土に含まれる雑菌やバクテリアにより繊維の分解が早まるそうです。また泥はなかなか乾きにくく、内部に汚れた水分が留まってしまうことで加水分解も早めます。
さらに厄介なのが、泥や砂繊維内に入り込んでしまった場合…。
繊維内に入り込んだ粒子が、ロープのたわみの度に内部の繊維を少しずつ断裂していきます。
汚れたままのロープを使い続けることで、クライミングロープの消耗は急速に進みます。
クライミングロープは、定期的に洗いましょう。
クライミングロープを洗う時、洗濯機はあまり使わない方が良いそうです。
ロープ同士の擦れにより、ロープ表面の消耗が早まります。個人的には、ジムやゲレンデで使う、どうしたって消耗が早いロープに関しては洗濯機で洗っちゃっています。雪山やアイスクライミングで使う、コーティングがしっかりしたお高いロープに限り、手洗いしています。
また安いロープも、泥水に浸かるような汚れ方をした場合には手洗いを心がけています。
まず大きな容器にお湯を入れます。僕の場合、衣装ケースを使っています。いろいろやった結果、これが便利です!
ロープ以外にも、靴を洗ったり、アイゼンを洗ったりなど、意外と出番が多いものです。一つ用意しておきましょう^^
お湯は 30℃ ~ 40℃ 程度のぬるま湯を、15 ~ 20 L 程度用意すると良いでしょう。
ここに"せっけん"と書かれた洗濯洗剤を使用しましょう。
たわしの真ん中の穴にロープを通します。たわしは2つ通しています。
たわしを 90° の状態にセットし、ロープ全体が洗えるようにします。
まずロープの末端部分をしっかりと洗います。
続いて、衣装ケースの取っ手部分にカラビナ2つをつけます。
ロープの末端をガルダーヒッチで繋ぐことで、とても洗浄効率が高まります。
アッセンダーやダイレクトビレイデバイスをしようしても良いでしょう。
ロープにテンションをかけながら、ブラシを細かくスライドさせてロープに付いた泥汚れを落としていきます。
ロープ全体をブラシ洗いしたら、排水を捨ててきれいな水を容器に入れます。
たっぷりの水を注いだら、ほんの僅かに柔軟剤を入れます。
柔軟剤を入れないとロープがパサパサに固くなってしまいます。
しかし柔軟剤は、入れ過ぎるとロープが保水し、重くなります。加水分解も早めますので注意が必要です。
しなやかさを保つだけなので、ほんの僅かに入れるようにしましょう。
ロープを揉むようにしながら、ロープ内部の汚れとともに洗剤を洗い流します。
ある程度したら水を捨て、再び水を注いですすぎます。
4 ~ 5 回 程度すすぎましょう。 ※ 柔軟剤を入れるのは、最初の1回のみです。
洗い終わったら、衣装ケースにロープを振り分けて、水が垂れなくなるまで干します。
水が垂れなくなったら、日の当たらない、風通しの良い所でしっかりと乾かしましょう。
部屋干しにして、窓を開けて風を通しても良いと思います。
クライミングロープは私たちの命を守る大切な道具です。
しっかりとメンテナンスし、気持よく安全に山を楽しみたいですね^^
動画でより詳しい洗浄行程を紹介しています。
是非ご覧頂ければ幸いです。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山者に必須!?破傷風予防ワクチン

死亡率30%超えの恐ろしい病気、破傷風。
登山者をはじめとし、アウトドアを楽しむ人は、そうでない人に比べて遥かに感染リスクが高くなります。
3種混合ワクチンにより幼少期に予防接種を受けていても、30代くらいからその効果はほぼ無くなります。実際に感染報告のほとんどが40代以上という報告も出ています。
再度、しっかりと予防しておくことを推奨致します。

破傷風は恐ろしい病気です。
感染者の実に30%以上が、散々苦しんだ後に死に至る病気で、しかも土があるところであればどこでも潜んでいる病原菌です。
実際に土の上で怪我をした対象者の凡そ2%の方の傷口から破傷風菌が見つかっていると言う統計データがあります。
発症こそしていないだけで、かなり多くの方に感染リスクがある事になります。
破傷風は本当に微細な傷口から進入する病気で、しかもイソジンなどでもすぐには死なない菌。
対抗するには予防しかありません!
実際に混合ワクチンによる予防接種を制度化する前には年間2,000人程度の感染があり、そのうち1,800人以上の死亡者が出ていた病気ですが、現在では大幅に減少。年間僅か100名程度の感染で、死亡者数も30名程度に留まっております。
しかしまったく油断はできません!
予防接種の有効期間は凡そ10年。最終予防接種から20年も経つと、その効果はほぼ無くなるそうです。
つまり、30代前半でほぼ予防接種の効果が無くなります。
実際に感染者の多くが40歳以上となっています。
予防接種は今からでも行えます。
全部で3回予防接種を行うことで、その後10年間はまずほとんど破傷風に感染しなくなります。
また10年以内に1回、再度予防接種を受けることで、さらにそこから10年効果が持続する事がわかっています。
つまり、一度3回の予防接種を行えば、あとは10年以内に一度予防接種をし続ければ、一生涯に渡って破傷風の危険から解き放たれることとなります。
山に入る以上、他の人より破傷風に感染するリスクは高くなります。
ご心配な方は、予防接種を受けておくのも良いのではないでしょうか?
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
無雪期の登山にはビレイグローブがおすすめです!

無雪期の登山におすすめなグローブとして、ビレイグローブがおすすめです。
ロープとの摩擦から手を守るクライミング用のグローブなので、その耐久性、防御性、操作性は大変優れています。
山の中では、手の保護をしたい時と、手袋をしないほうが安全な場面が交互に現れたりします。簡単に付け外しでき、携行がし易いのもビレイグローブの魅力な点ですね!
今回グローブを新調したので、その紹介も含めてお話しています♪

登山のグローブの選択って難しいですよね。
雪山登山のグローブの選択も難しいものですが、無雪期のグローブの選択もまた難しものです。
一般的に利用者が多いのは、メッシュや薄い化繊のグローブ等でしょうか?
防水透湿素材を使用した、雨の日に便利な薄手のグローブもありますね。
これらのグローブは確かに軽く、蒸れずに快適ですが、本当に使いやすいと言い切れますか?
僕はあまり好きではありません。
個人的には、クライミングの際に使用するビレイグローブを愛用しています。
職業柄、ロープを使ってお客様の安全を確保する必要性が多いこともあり、グローブの耐摩耗性がとても重要だったりするのもそうなんですが、それだけではありません。
ビレイグローブはクライマーの確保に使うクライミングギヤなので、高い操作性やグリップ力、ロープの摩擦から手を守る防御力などが求められます。またビレイ操作でのみ使うので、つけたり外したりを頻繁に行います。この為、脱着のしやすさや携行のしやすさも重要な要素になります。ビレイグローブは、この様なポイントをクリアした作りになっています。
登山においても、グローブをずっとつけっぱなしでは無いと思います。
鎖やロープを握ったり、藪を漕いだり、木々を掴んで急峻な斜面を登る様な時にはグローブが欲しくなりますが、平坦な登山道のハイクアップや岩場の登攀ではむしろグローブは邪魔です。
簡単につけたり外したりできる事、外した時に携行しやすいことは一般登山においても重要なポイントだと感じます。

.
これまで4年近くに渡り Black Diamond のクラッググローブを愛用してきました。
薄手で操作性が良く、手のひらは比較的丈夫で滑りにくい合皮性。親指の付け根には汗や鼻水を拭えるようにタオル地になっている親切設計!しかも大変良くできたグローブです。
しかし、仕事でロープを使うことが多いので、凡そ1年位で穴が空いてしまう。ちょっと耐久性に欠けるので、今回はメトリウスのビレイグローブを買ってみました。
多くのビレイグローブが羊革なのに対し、これは厚手の牛革。最初だけちょっとゴワつくけど、耐久性は圧倒的に高いと思われます。
個人的にはかなり気に入りました♪
全体的には表皮を使っていますが、手のひらからロープで擦れるところ全体にかけて皮を二重にし、その部分は摩擦力を増すように裏皮を使っています。手首の部分にはカラビナループを設け、カラビナを使ってハーネスやバックパックのショルダーベルトに簡単にラッキングできる作りになっています。
その昔、牛革のレザーグローブを使っていましたが、凡そ5年ほど使えたと記憶しています。
また最初は硬かったけど、使っているうちにまるで自分の皮膚の一部かのように馴染んで行くのも、とても愛着が湧く道具でした。
そんな思い出もあり、今回購入したビレイグローブにもとても期待しています^^
登山中にロープを使う方にとって、牛革のビレイグローブは大きな味方となると思います。
クライマーや職業登山者に限らず、初心者を連れたパーティーのリーダーさんやお子さんを連れたお父さんなど、初心者を連れて歩く立場にある方はロープによる安全確保技術を身につけるべきです。
しっかり学習し、練習を繰り返し、ロープによる確保技術を身につけることで山の安全は確実に高まります。
その上で、装備するグローブは牛革のビレイグローブが良いでしょう。
ロープを使わない方が登山で使うグローブとしては、僕がこれまで愛用してきた Black Diamond のクラッググローブの方が使いやすいかもしれません。薄手で違和感なく装着でき、合皮なので最初から柔らかく、洗濯機で簡単に洗えます♪
沢登りで使用するグローブとしては、これからもクラッググローブを使うつもりです。
人によって何がベストかは考え方によっても差が生まれますが、僕個人としてはこれがおすすめです。
ご参考にして頂ければ幸いです^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
クイックドローのカラビナの向き

クイックドローって、どちら側のカラビナを使うかご存知ですか?
岩場に行くと、たまに使い方を間違えたクライマーを見かけます。クライミングジムで育ち、外岩に足を運ぶようになったクライマーは、この学習機会を得られないままになっているのでは無いかと思います。
クイックドローのカラビナを良く見てみると、ゴムで固定された方とそうでない方があります。ここを誤ると超危険!しっかり覚えましょう!!

クイックドローのカラビナのどっち側をハンガーにかけ、どっち側にロープを通すか、きちんと理解していますか?
現在では山岳会などの組織登山を経験される方が少なく、またその一方で、クライミングジムのブームにより、ジムで育って外岩に出向くようになるクライマーが多くなっています。
ジム育ちのクライマーは最初から技術力が高く、かなり難しいルートへもいきなり挑戦するスキルを持つ方もいます。
しかしジムで育つと、クイックドローをクリップする経験を持たないまま外岩に行く事となります。この時、適切な指導を受けられていないと、誤ったクライミングを行って危険を伴う場合があります。
その一つに、クイックドローのカラビナの使用方向があります。
実はこの方向を間違えると、カラビナがハンガーから簡単に外れてしまい、非常に危険です。


クイックドローのカラビナは、一方はただの輪っかに通されており、もう一方はゴムで固定されています。
ゴムで固定されている理由は、クリップのしやすさにあります。余計な可動が無いので、すなおにクリップしやすいんです。
なら両方ゴムで固定しちゃえば良い気がしませんか?
実はここに落とし穴があります。

固定されていない方のカラビナをハンガーにつけた場合、ループ部分で力が逃げてカラビナが押されません。

しかし固定された側をハンガーにクリップしてしまうと、クイックドローがロープに引っ張られた場合にゲートが押されてしまいます。

こうなると、いとも簡単にカラビナが外れてしまいます。
また固定された側をハンガーに取り付けると、クイックドローが破損するリスクも高まります。
使用する向きには十分注意しましょう!
そう、固定されている側をハンガーにかけてしまうと、いとも簡単にカラビナがハンガーから外れてしまうんです。
とても危険ですね…。
また向きを間違えると、カラビナの破損リスクも高まります。
クイックドローを使用する際には、必ずゴムで固定されていない方を使用して下さい^^
他にもクイックドローの使い方には注意点がいくつかあります。
追って少しずつ紹介させて頂きますね!
皆さまのセーフティークライミングにこの情報がご活用されれば幸いです♪
Kuri Adventures では、気楽に参加できるクライミング講習を行っています。Kuri Adventures のクライミング教室で講習を受け、安全にクライミングを始めましょう ^^ 初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームな講習会ですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
山岳ナビゲーションアイテム"高度計"

山岳ナビゲーションにおいてもっとも難しいのは"現在地を把握すること"です。
晴れた日の尾根筋であれば、目標となる山と今いる尾根との位置関係から現在地を把握できますが、沢筋にいる時には現在地を特定することが困難となります。
そこで便利なのが高度計!
沢の分岐などで高度計と地形図を確認すれば、現在地は一目瞭然です。
ナビゲーションアイテムの1つとして装備に加えましょう^^

登山中の遭難事故における、実に50%以上が道迷いに寄る遭難を起因として引き起こされています。まず第一に道迷いを起こさないこと!
これがとても重要です。
道迷いを防ぐためには、山岳ナビゲーションスキルを身につける事がとても重要です。
地形図を読み解き、コンパスで方向を示し、正しい方向へ向けて歩く。このシンプルな方法を確実に行うことで、道迷いのリスクは激減します。
山岳ナビゲーションにおいてもっとも難しい事は、現在地を知る事です。
現在ではほとんどの方がスマートフォンを持っているため、GPSで簡単に現在地を知る事ができます。現在のスマートフォンに搭載されているGPSは、GPS専用機のそれとなんら遜色のないクオリティ。電波が届く範囲であれば、A-GPSによりGPS専用機を遥かに凌ぐスピードと精度で現在地測定を行えるスグレモノです!
しかし電子機器である以上、故障やバッテリー切れなどのトラブルを起こすこともあります。
アナログでナビゲーションを行うためのギヤも複数用意することで、故障やバッテリー切れ、紛失などのトラブルでもバックアップにより現状維持できる可能性が高まります。

.
現在地を知るための道具として有効なものに、高度計があります。
尾根や稜線を歩いている時には、晴れていればランドマークとなる山と今歩いている尾根との位置関係から現在地を特定できます。
しかし曇っていたり、谷にいる時にはこの方法での現在地特定は行えません。
高度計があれば、現在歩いている場所と高度を照らし合わせることで、簡単に現在地を特定することができます。
特に沢筋では、沢の分岐と高度を照らし合わせることで、ピンポイントでの現在地特定が可能となります。
GPSの精度が下がりやすい沢筋でのナビゲーションにおいて、高度計の存在はとても頼れるもの。
沢でのナビゲーションの切り札となり得る道具です!
高度計は、入山前に必ず標高を合わせておく必要があります。
日によって気圧が変動するので、毎日出発前に気圧と標高を合わせないと、狂いが生じてしまいます。
入山点の標高を地形図で確認し、高度計の針と現在の標高を忘れずにセットしましょう。
大気圧の変化や気温などにより、標高変化による気圧差に誤差が生まれます。
高低差500m以内に再度高度訂正をする事で、より正確な標高表示が可能です。
台風など低気圧が近づいている場合、急激な気圧変化により、示す高度に狂いが生じる場合があります。
本来示すべき標高より高い位置を示すような場合、低気圧が急激に近づいていたり、または近くで急激に発達している可能性が考えられます。
すなわち、悪天候になる可能性が高いと言うことです。
高度計は、急激な天候変化を知る上でも役立ちます。
腕時計などに組み込まれた高精度なデジタル高度計も便利ではありますが、アナログなものも山行途中の高度訂正が簡単に行えると言う利点もあります。
ナビゲーションによるあらゆる手間を減らすことも、こまめに進路訂正をする重要なポイントになります。
そしてそれこそが、道迷いを防ぐ最大の方法かも知れません。
高度計はアナログのものであれば、3000円~5000円程度で購入できます。
現在地を知ることができるとても便利な道具であり、山の安全に確実に貢献してくれる頼もしい存在です。
もしお持ちでない方は、これをきっかけに購入してみるのも良いかもしれませんね^^
皆さまの安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
原点とも言うべき原始的登山 "沢登り" の魅力

春が近づくと雪解けを残念に思う一方、新緑の季節が訪れる事に心躍る。
高い山々に雪解けが始まる頃、森が多い茂低山帯の沢が遡行者を受け入れ始める季節となります。
沢登りはもっとも原始的で、自然の深い部分を楽しめる登山スタイル。
人の踏跡無きその原生の森では、未知への冒険が色濃く残されています。日本特有のアルパインクライミングの楽しみが、そこには確かにあります!

沢登りは日本特有の登山方法です。
標高がさほど高く無い場所から山が急峻になる島国特有の地形でなければ成り立たちません。
ヨーロッパアルプスを始めとした大陸内部の山々では、山の急峻な部分は高い標高に位置します。遡行対象となりそうな谷は、その多くが氷河に覆い尽くされ、沢登りはできません。
赤道からさほど離れていないエリアで、そこそこの標高の山が多く存在している島国。
そんな限られた条件下でしか沢登りを楽しめない。日本はそんな限られた条件に恵まれた土地です。
(実は台湾でも沢登りが行われていますが、元々は日本人が持ち込んだ山行方法だとされています。)

.
個人的には沢登りが全ての山行の中で一番好きです。
沢特有の美しい景観や生命感溢れる森の雰囲気、透き通った美しい水。その美しさは、実際に足を踏み入れてみないと伝わらないかもしれません。
そして何より、その原生のままの自然が切り開いた水の道には、常に冒険が残されている点にこそ魅力があります!
水が集まる沢では、一度雨が降れば人の踏み跡を洗い流します。
道無き道を自ら切り開き進む感覚は、現在ある山行スタイルの中でもっとも"アルパインクライミング"の原点となる山行スタイルなのではないでしょうか?
登山者としての冒険心が掻き立てられます!
沢登りと一言に言っても様々なものがあります。
全身水に使って沢を遡る泳ぎ系の沢から、急峻な滝を攀じ登る登攀系の沢、滑床を永遠と進む歩き系の沢まで様々です。
初心者から楽しめるルートを多く持つ奥多摩や丹沢の沢の多くは、大凡膝丈程度の水深の沢が多く、全身ずぶ濡れになる回数は少なく済みます。
あまり大きな滝はありませんが、それでも連続する小滝を登攀し続ける、登攀系の沢が多い特徴があります。
さほど濡れずに済むので、4月後半から11月前半までと長い期間楽しめるのも魅力のエリアです。
春の新緑の季節は特に最高で、まだ薄い木々の若葉をすり抜けた太陽の光が、黄緑色の木漏れ日となって沢床を多い茂る苔をキラキラと輝かせます。
夏には泊まりがけで沢に入る楽しみがあります。夜には焚火を囲い、蛍の漂う中で飲み交わす酒とバカ話。満天の星空の下、沢のせせらぎの中で眠る夜。これが楽しくないわけがありません!
沢の時期がまもなく終わる秋。紅葉で真っ赤に染まる森の木々を楽しみながら、沢の時期は静かに終わりを告げます。
沢登りを楽しむためには、総合的な登山技術が問われます。
高いレベルのナビゲーションスキルやルートファインディングスキル、クライミングに必要なロープワークスキルや支点設置能力も問われます。
はじめは経験豊かな人に連れて行ってもらい、少しずつその技術を身に着けていきましょう。
沢登りを続けていくと、登山者として必要な技術の多くが身につきます。
沢が山ヤを育てるんです。
そんな魅力たっぷりの沢登りを、Kuri Adventures ではじめてみませんか?
僕個人としてもっとも好きな山行が沢登りです。
その魅力を一人でも多くの方に知って頂きたいと考えています。
皆さまのご参加をお待ちしています^^








Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
最重要登山技術 " 懸垂下降 "

登山中の転滑落事故の多くは下りで発生しています。
急峻で危険な下りを安全に通過する最良の方法は、懸垂下降を行うことです。
しかしクライミング中にもっとも多く死亡事故が起きるのもまた懸垂下降であるように、手順や操作を誤ると大変危険です。
これから懸垂下降を学ぶ方や、すでに技術をお持ちの方の復習用に活用頂ければと思い、動画と写真で説明しています。ご活用下さい^^

山の中を歩いている時に突如として現れる、危険な下り。
登山中の転滑落事故の多くが下りで起きていることからも、その難しさが伺い知れます。
そのような危険な下りをもっとも安全に通過する方法として、やはり懸垂下降が最良の策でしょう。
技術を持っていれば、実に簡単に、且つ安全に危険箇所を通過することができます。
一方で、クライミング中の死亡事故としてもっとも多いのもまた、懸垂下降中であったりします。
懸垂下降は本来安全を確保するための技術ですが、手順や操作に誤りがあると、高さがある場所なだけに大きなダメージを負うリスクがあることも忘れてはいけません。
正確な知識を知り、十分な練習を積んだ上で 、技術を確実なものにした上で行いましょう。
ここでは一連のやり方を説明していますが、懸垂下降は十分な経験を持つ方の指導の元、しっかりと学習する機会を経て下さい。
独学で学ぶには少し危険が大きいと思います。
ここに記す情報は、懸垂下降を学ぶ前の予習、学んだ後の復習にご活用頂ければ幸いです。

120cm のスリングの中央に縫い目が来るようにし、縫い目の真横にオーバハンド・ノットで結び目を作ります。
片側を少しずらして弛みを作り、その弛みを維持したまま先ほどの結び目の真横にピッタリくっつく様に、もう一つオーバーハンド・ノットを結びます。
先端にはスリップノット、又はクローブヒッチを作り、安全管付きカラビナをセットします。
これをセルフビレイコードとして使います。

カラビナとは反対側の末端を、ハーネスのタイインループにガースヒッチで結びます。

懸垂支点にスリングを巻き、セルフビレイをとります。

支点となる木に、ロープの中央部で折り返します。

ロープの末端は、必ず1m以上余して結び目を作っておきます。これを行うことで、万が一ロープが下まで届いていなくても、スッポ抜けによる墜落を防ぐことができます。
末端を結んだらロープを下に投げ下ろします。

スリングの途中に作った、結び目と結び目の間の穴にビレイデバイスをセットします。

ビレイデバイスを支点側にずらし、テンションをセルフビレイからビレイデバイスに移します。
バックアップをビレイデバイス側にスライドさせ、手を離してもビレイデバイスが動かない状態にします。
この状態になると、ロープに体重をかけたままセルフビレイを解除することができます。
セルフビレイを解除し、支点にしていたスリングを回収して懸垂を開始します。

プルージックを握って、バックアップを緩めると懸垂が始まります。

バックアップがあることで、途中で手を離してもすぐに止まります。
安全性、作業性の面からも、必ずバックアップシステムを構築するようにしましょう。
次の動画で一連の流れをお伝えしています。
しっかりと繰り返し学習し、何度も練習して確実な技術を身に付けて下さい。
しっかりと技術を身につけていれば、これほどいざという時に役立つ技術は無いと思えるほど、大きく安全に貢献してくれる重要技術です。
大きなダメージを負うリスクがあるのも事実ですが、是非身に付けて欲しい技術。
山に入る者として、きちんと学習しておきましょう。
いざという時、きっとあなたをピンチから救ってくれるはずです!
Kuri Adventures では、気楽に参加できる登山教室を行っています。登山教室で講習を受け、安全登山にお役立て下さい♪
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームな講習会ですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.2.27-28 はじめてのアイスクライミング体験

一泊二日で、アイスクライミング体験企画を行いました!
暖冬により短い氷のシーズンでしたが、それでもなんとか企画日までは氷が残ってくれました^^;
アイスクライミングには確かに多くの危険が伴いますが、それ以上にとても楽しい冬のアクティビティでもあります。
まずは安全な人口ゲレンデでアイスクライミングを始めてみませんか?

クライミングをやっていると、毎年冬が楽しみになります。
凍てつく冬の寒さはあらゆる物の活動を止めます。それは山間に流れる沢の水すら凍りつかせるのです。
夏には轟音とともに流れ落ちていた大量の水も、この限られた時期だけは無音の氷爆へと姿を替えます。
そう、まるで時が止まったかのように。
アイスクライミングは冬に限定された特別なアクティビティです。
山の沢の奥地にまで足を踏み入れなくてはならない上、ロッククライミングより少しリスクも高くなります。
この為、本来であれば十分な雪山登山経験とクライミング技術を身に付けた一部のエキスパートのみに許された世界でした。
しかし近年では、人工的に氷壁を作る"人口アイスゲレンデ"が増えてきています。
アプローチが優しく、アクセスが良く、安全にアイスクライミングを楽しむ事ができます。
アイスクライミングの間口は、グッと低くなりました!!
この企画は、一泊二日でみっちりと基礎をお伝えする内容。
正対、カウンターでの基礎ムーブと、アックスの振り方、アイゼンの蹴りこみ方などを何度も反復して身に付けます。
またアイススクリューのセット方法やV字スレッドの作り方など、支点構築に関するうんちくもお伝えしました。
夜は近隣のキャンプ場にてテント泊。
焚火を囲いながら語らう時間は、とても幻想的で楽しい時間となりました♪












今シーズンはもう氷の時期が終わります。
暖冬による短い冬でしたが、来シーズンはかなり冷え込むとの予想も??
次のシーズンは、12月中旬〜3月中旬くらいまで、みっちり氷漬けなシーズンにしたいものです。
ご興味をお持ち頂きました皆さま、是非来シーズンはご参加下さい!
本当に楽しい時間を、思いっきり楽しむことができますよ♪
ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました!!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.2.18 山が好き & JMIA 日本登山インストラクターズ協会 合同企画 "安全登山講習会"

Facebook 最大の登山系コミュニティグループ"山が好き"と、JMIA 日本登山インストラクターズ協会の合同企画として、無料の安全登山講習会を行いました。
今回がはじめての試みでしたが、28名もの方にご参加頂けました。
登山の安全に繋がる啓蒙活動としての社会貢献活動を続けることで、きっと山の事故は減ると信じています。
ご協力頂きました皆さま、本当にありがとうございます!

18,000人(記事投稿現在)もの加盟者を誇る、Facebook最大の登山系コミュニティ"山が好き"と、僕の所属するJMIA 日本登山インストラクターズ協会とのコラボ企画として、無料の安全登山講習を行いました。
事の発端は、2016年1月27日にお招き頂いた"山が好き"の新年会での事。
この新年会もまた、超巨大コミュニティグループならではの100人越え企画!すごいっ!!
そんな新年会の席で、ちょっとだけセルフレスキュー講習を行いました。
その時、山が好きの管理者様より、もっと多くのメンバーに安全登山に関わる事柄を伝えて頂けないかとのご相談を頂戴します。
登山技術を学んだ経験が無い方に、学習を始めるきっかけとなればとご提案頂き、今回の無料講習会を行う事となりました。
第一回目の安全登山講習会には、総勢28名もの方にご来場頂きました。
前半に当協会理事長の岩崎による"安心登山の10箇条"をお話頂き、続いて僕の方で"歩行技術と呼吸法"のレクチャーを行いました。
ご参加頂きました皆さまには、大変ご好評頂けたようでなによりです♪
この様な安全登山に関わる啓蒙活動は、高い社会貢献性があると感じております。
今後も出来る限り継続し、皆さまの山の安全に貢献できれば幸いです。

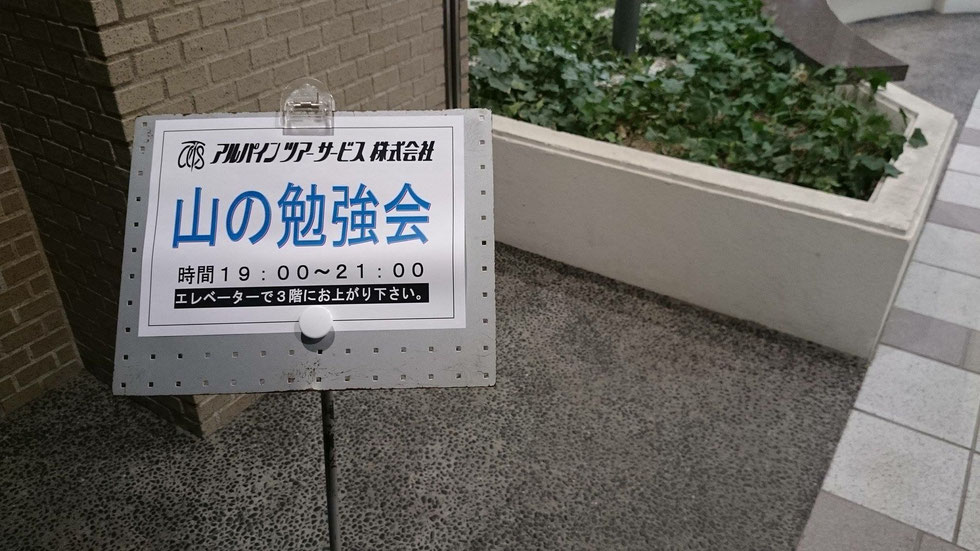





協賛頂き、会場をお貸し頂きました、アルパインツアーサービス様。
本当にありがとうございました!
海外登山を楽しんでみたい方は、是非アルパインツアーサービスを利用して下さい。
比較的低価格で安心の登山ツアーをご提供してくれますよ^_^
アルパインツアーサービス株式会社:http://www.alpine-tour.com
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪山登山におすすめのインナーグローブ"Black Diamond デジタルライナー"

答えが無い雪山のグローブ選択。しかし僕は、今年1つの答えに辿り着いた気がします。
お客様が使っているのを見て、ピンときました!これ、最強じゃね?
ゴアテックス社のウィンドストッパーを使用し、そこそこの防水性と圧倒的な透湿性を持つグローブですので、従来のインナーグローブ程濡れに注意する必要がありません。
また指先に液晶タッチパネル対応素材が付いているので、グローブをしたままスマートフォンが操作できます。もう一度言います。これ、最強じゃね?

雪山登山は装備に悩みます。特にグローブは、答えがない装備としてみんなが様々な方法を試行錯誤しています。
しかし僕は今年、1つの答えにたどり着いた気がしています。
雪山で使うグローブは、インナーグローブ・ミドルグローブ・オーバーグローブの3層重ねで使用するのが一般的。
薄手の化繊インナーをベースに、伝統的な手法では厚手のウールとペラペラの防水オーバーグローブが現在でも使われています。また最近では、化繊やダウンの中綿が入った保温層と防水層がベルクロなどで一体化されたアルパイングローブが主流となりつつあります。
欠点となるのは、操作性の悪さ。
インナーより上の層のグローブを装着したまま細かい操作を行うのは困難で、ロープワークやアイゼンの装着など、細かい作業を行うには訓練が必要です。また、小さなバックルを外したり、カメラの操作をしたりなど、本当の意味で細かい操作を行うのは不可能です。
細かい操作を行わざるをえない時でも、素肌を外気にふれさせるのは危険です。
そのためにインナーグローブが必要です。

.
しかしインナーグローブには弱点があります。
インナーグローブは防水ではないので、雪に直接触れてしまうと手袋が濡れてしまいます。こうなると、熱伝導率が高まって凍傷のリスクが跳ね上がります。
これまで、インナーグローブでは絶対に雪に触れないようにする事が鉄則でした。また万が一濡らしてしまった時の為に、インナーグローブの替えを持つことも常識となっています。
でもふと思ったんです。
なんでインナーグローブが防水じゃダメなんだ???
そもそも保温はミドルグローブの仕事。インナーグローブの保温性なんてたかが知れています。
そんな時、当店をご利用頂いているお客様が使っているグローブを見て「これだっ!」と気が付きました!!
そのグローブは、Black Diamond社のデジタルライナー。ゴアテックス社のウィンドストッパーと言う素材を使ったグローブです。
ウィンドストッパーは完全防水ではありませんが、そこそこの防水性ととても高い透湿性、撥水性、防風性を併せ持った素材です。
つまり、雪を触った程度ではまずグローブが濡れてしまうことがありません。
細かい操作をするために上の層のグローブを外しても、高い防風性により短時間なら手も冷えにくい優れた特性を持っています。
もちろんこのグローブで積極的に雪に触れる事は推奨しませんが、一時的にアイゼンの脱着やロープ操作で雪に触れる程度は問題無いでしょう。
そして、このグローブにはもう一つ大きな特徴があります。
それは親指と人差指のところにつけられた、液晶タッチパネル対応素材!
これにより、インナーグローブを外すこと無くスマートフォンが操作できます!!
現在ではスマートフォンをカメラ代わりに使い、GPS機器として使う方がとても多くなっています。
しかしこれまでインナーグローブではスマートフォンが操作できず、わざわざインナーグローブを一瞬だけ外し、スマートフォンの操作を済ませたら慌ててグローブを装着する方を多く見ています。
中には人差し指、親指がハーフフィンガーになっているインナーグローブを使用されている方までいらっしゃいます。
しかしこれらは当然、かなり高い凍傷リスクがある行為。危険です。
液晶タッチパネル対応素材が指先につけられ、そこそこの防水性と高い防風性を持ち、操作性抜群の薄いグローブ。
これはまさに最強のインナーグローブかもしれません!!
残念なのはお値段。
なんとインナーグローブに6,000円...。ちきしょう、足元見やがって.........(T_T)
このインナーグローブに、同じくBlack Diamond社のアルパイングローブ"ソロイスト"の3本指のを組み合わせて使っています。
−29℃対応の圧倒的保温力のアウターに、防風・防水・スマホ対応のインナーグローブ。
この組み合わせはまさに最強かも知れません。めちゃめちゃオススメですよー♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山のロープワーク " プルージック "

フリクションノットの基本形、プルージックの紹介です。
どちらの方向にも効く結び方なので、トラバースを含む中間登攀にも使えます。
フリクションノットはメインロープの太さによって効きが変わります。しかしプルージックなら、少し結び方を変えるだけで効かせる強さも変えることができます。
中間登攀、懸垂下降のバックアップ、レイジングシステムなど、かなり幅広い用途で使います。しっかりと覚えておきましょう。

プルージックはフリクションノットの基本形です。
どちらの方向にも効くので、フィックスロープをトラバースする様な場合に適しています。また結び方を少し変えるだけで、強く締まった状態から簡単に緩めることもできます。
特に登攀などに使う場合を除いては、使い分けとして、ロープ1本に巻きつける場合はクレイムハイスト。ロープ2本に巻きつけるにはプルージックが適していると思います。
効き自体はクレイムハイストなどに一歩劣りますが、とても扱いやすいフリクションノットだと思います。
フリクションノットは、中間登攀、懸垂下降時のバックアップ、ロープの登り返し、レイジングシステム、ツェルトやタープの設営など、登山の様々なシーンで活用されます。是非しっかりと覚えておきましょう。
フリクションノットは細引きで作ったロープスリングを使います。
フリクションノット用に作ったロープスリングを、ここでは"フリクションノットコード"と呼んでいます。
原則として、7mm × 150cm のアクセサリーコードをダブルフィッシャーマンズノットで輪にしたものを使います。
ただし 8mm ロープなど、細経のロープに対しては 6mm のアクセサリーコードを使用したほうが良い場合もあります。
ロープと細引きの相性がありますので、使用前に必ず効きを確かめましょう。
また使用する細引きのメーカーによっても、使いやすさに差があります。
高いものではないので、いくつか試し、使いやすいものを探しましょう!

1本のロープに結ぶ場合、フリクションノットコードの結び目の反対側あたりをロープに添えます。

結び目側の末端を輪の中に通していきます。

3回巻きつけ、形を整えます。

プルージックの完成です。
巻きつけ部を持てば簡単にスライドでき、結び目側の末端にテンションをかければしっかり止まります。
結び目側が末端に来る結び方は、ロープ一本を対象に結ぶ時に有効です。
二重のロープや太いロープに使用すると、フリクションノットコードがロープに食い込みすぎて使いにくい場合があります。

そのような場合には、結び目を巻きつけ側の中心に来るようにします。

ロープの締め付けが強くなりすぎても、結び目部分を少し押してあげれば簡単に緩ませることができます。
但し細いロープには効きが弱くなることもあります。
二重のロープ、又は太いロープを対象に使用しましょう。
懸垂下降のバックアップには特に使いやすくておすすめです。
ヨーロッパの登山シーンでは、クレイムハイストがもっとも使われるフリクションノットだそうですが、日本ではこのプルージックを使われることの方が多いと思います。ただし絶対的な効きはクレイムハイストより劣るので、トラバースを含まない中間登攀にはクレイムハイストの方が優れているでしょう。
それ以外の多くのシーンでは、ロープを1本で使うのか、2重で使うのかで使用を分けると便利だと思います。
是非覚えておきましょう!
Kuri Adventures では、気楽に参加できる登山教室を行っています。登山教室で講習を受け、安全登山にお役立て下さい♪
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームな講習会ですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
2016.2.6 クライミング教室 "初めてのクライミング講習"

スポーツクライミングは、登山中の安全確保技術や岩場での安全な登攀技術を身につけるのにうってつけです!
登山(マウンテニアリング)とは、トレッキング技術とクライミング技術を合わせたもの。
本格的な登山に挑戦するにも、当然クライミングは必須の技術です。
初めてのクライミング講習では、まったくの未経験者が最初に学ぶべきトップロープクライミングの技術をお伝えしています。

先日、"初めてのクライミング講習"を行い、クライミング未経験の皆さまにトップロープクライミングの技術指導を行いました。
クライミングは、登る人(クライマー)が途中で落ちても止められるように、ロープで安全確保をする人(ビレイヤー)が必要です。
クライミングでのビレイは、登山の安全確保の基礎となる技術でもあります。
クライミング技術を習得する事は、スポーツクライミングを楽しむ上でももちろんですが、登山での安全確保を行ったり、アルパインクライミングの世界に足を踏み入れる上でも必要となる技術です。
トップロープクライミングは、そんなクライミング技術のもっとも基本となる手法。まずはここから覚えましょう!
Kuri Adventures では、ハーネスの装着方法やロープの結び方などから始め、クライミングのビレイの動きを、もうこれでもかっってくらい練習してもらっています。
さらにクライミング講習にご参加頂いたお客様のために、平日の夜にご参加頂く無料のクライミング練習会も♪
合わせて確実に覚えられるプログラムになっています!






スポーツクライミングは決して敷居の高い遊びではありません。
しっかりとルールを学べば、安全に誰でも楽しむことができる素晴らしいスポーツです。
またスポーツクライミングを行うことで、安全確保のシステムを知り、高いレベルの確保技術を身につける事も出来ます。
当然岩を登る能力も高まりますので、岩場での安全度は格段に増します。
より多くの方に、クライミングの愉しみと安全に関するポイントをお伝えできればと考えています。
皆さまのご参加、お待ちしております^^
今回ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました。
引き続き無料の練習会にもご参加下さい。
たくさん練習して、お伝えしたことを忘れないうちにしっかりと身につけましょう^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.2.4 ワークショップ "山岳ナビゲーション基礎"

皆さんに覚えてもらいたい、登山技術の基礎の基礎!それがナビゲーション技術です。
登山技術の基礎の基礎とは言いますが、でもこれってけっこう覚えるのが大変…。
本を読んだり、座学講習を受けるだけではなかなか身につきません。
そこで Kuri Adventures では、夜の公園でオリエンテーリングを行いながらの講習を実施しています!
実際に歩きながらコンパスを使うことで、しっかりと覚えて頂きます♪

山岳遭難事故の約50%は、道迷いを原因として引き起こされています。
でもしっかりとしたナビゲーションができれば、道を間違える事はあっても、道に迷うことは起こりません。
読図能力やコンパスの操作は、登山技術の基礎の基礎。本来は全員ができてしかるべき技術ですが、その一方で登山技術全体の中でも特に難しい技術の1つでもあるんです。
実際にしっかりとした山岳ナビゲーションスキルを持つ人は一部であったりするので、結果として道迷いによる遭難が跡を絶ちません。
でも言い換えれば、確実なナビゲーションが行えれば、山のリスクは半分にまで減ります。
やはり全ての登山者が身につけるべき、必須技術であることは間違えないでしょう。


.
一昔前と違い、今はみんなのポケットに高性能なコンピューターが収められている時代。
スマートフォンのGPSを使えば、山岳ナビゲーションでもっとも難しい"現在地特定"が簡単にできます。
スマートフォンのGPSを使って現在地を特定し、地図とコンパスで進行方向をコンパスに示させ、コンパスの示す方向に向かって進む。
まずはこの様な方法でナビゲーションを行えるようになって頂き、その後少しずつ他の現在地特定に関する技術と知識を身につけてもらうと良いかと思います。
尚、山の中ではスマートフォンを必ず機内モードにしましょう。地形図アプリの地図データは、電波が届くところにいる間に事前キャッシュにのこして起きましょう。気温が低いとバッテリー電圧が下がってすぐに使えなくなります。内ポケットに入れ、現在地特定以外には使わないようにしましょう。
ナビゲーションの道具は、登山の生命線です。スマートフォンの故障やバッテリー管理には十分に注意し、十分な容量を持つポータブルバッテリーも携行しましょう。
また地図とコンパスもバックアップを持つことを強く推奨します。スマートフォンの故障なんかより、地図とコンパスの紛失リスクの方がずっと高いものです。
Kuri Adventures では、平日の夜、お仕事帰りの時間帯でご参加頂ける、登山のワークショップを開催しています。2時間で登山技術を学べる講習となっています。山岳ナビゲーション基礎講習では、実際に地図とコンパスを使いながら、オリエンテーリングを通じて実践的に学んで頂く内容となっています。
定期開催しておりますので、もし地図とコンパスの使い方が分からない方がいらっしゃいましたら是非受講下さい。
山の安全はきっと高まります。ご参加お待ちしております^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪上でバチ効きするペグ "Easton Gold 24"

雪山登山のテント設営って、ちょっと面倒だと感じませんか?
ペグをアンカーにして雪に埋める方法が一般的だとは思いますが、その為にはいちいち雪を掘らなくてはならない。
厳冬の寒風に晒されているテントの設営・撤収は、何とも言いがたい辛さがあります。
その時間を大幅に短縮するには、簡単にテントをペグ固定できる道具が有効です!
あるんですよ!軽くて、長い、良く効くヤツが♪

Kuri Adventures では、テント泊での登山を強く推奨しています。
テントや食料を担ぎ上げ、何にも頼ること無く自分の力で山の中での生活を楽しむ。それこそが本来あるべき登山の姿だと思います。
山でテントに泊まると、自然の中により深く入り込む感覚を得られます。
特に冬のテント泊は、愛用の道具を駆使して生物が行きられない厳寒の環境をしっかりと生き延びると言うだけで、1つのアクティビティとして楽しいものです。
全ての音をすっと消し去る、深々とした雪の中でのテント泊は、それはもう幻想的で素晴らしいものです。

.
冬のテント泊を行うには、幾つか面倒な点があります。
その一つがテント設営。
夏であればペグを地面に打つだけでしっかりと固定できますが、冬場はなんせ相手が雪。付属のペグをさしても無抵抗に抜けてしまいます。
そこで通常はペグを横向きにし、雪深く埋めることでアンカーとします。つまりペグ1ヶ所固定する為に、1つ穴を掘らなければなりません。
これはかなり面倒…。
でもね、あるんですよ!
雪でもペグダウンできるペグがあるんです♪
" Easton Gold 24 " は、中空シャフトのアルミペグ。その長さは実に 24inch = 62cm もあります!!
ただ手でペグを押しこむだけで挿せ、しかもバッチリテントを固定できるんです。
これなら夏より簡単にテントの設営・撤収ができるので、積雪環境下でのテント設営がメチャメチャ楽になります♪
長いペグだと重量も心配なところですが、この Easton Gold 24 は、実測で約30g。
通常のペグが15g程度なので、これだけの長さがありながらも思ったほど重量増になりません。実物を持つと、笑っちゃうくらい軽いですw
僕の場合、このペグを4本持って行きます。
カーボン素材のトレッキングポールを使っているので、トレッキングポールを分解して下段・中断シャフトをペグが割りに雪に挿して使っています。ペグと合わせて8ヶ所。テント底部と張り綱4本をしっかりと固定できる事になります。
あとの細かいところはピッケルやらショベルやらスノーバーやらを挿しておきます。
そう!これをすると、なんと1ヶ所も穴を掘らずにテントが設営できちゃうんです!
これはもう、超スピーディー!!
冬のテント泊の手間が大きく低減するナイスアイテムですよ♪
なかなか便利な道具なので、ちょっと紹介させて頂きました^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.1.30 赤城山 初めての雪山登山体験ツアー

厳冬期の赤城山へ、お客様をお連れしてぐるっと一周のんびりスノーハイキングを愉しみました^^
今年は雪が少なく、もう1月の末だと言うのにまだ大沼は完全凍結していない状態…。
まるで初冬期の様相です。でもその分、登山を行う気候としてはとても穏やかで、気持ち良い登山を楽しむことが出来ました^^
ご参加頂きました皆さま、ありがとうございます♪

雪山登山初級者向けの企画として行った、赤城山スノーハイクのレポートです。
この日は厳冬期の雪山とは思えない程に穏やかな気候で、山頂部でも−5℃程度。風速も3m程度ととても過ごしやすい一日でした。
天候は生憎の曇り空でしたが、雲が高い位置と低い位置に分かれて広がっており、丁度赤城山山頂部は雲がない状態に♪
雲の切れ間から時折太陽の光が注ぎ、木漏れ日のように山々を照らす光のシャワーはとても幻想的。
足元に広がる雲海と輝く樹氷のコラボレートがなんとも言いがたい美しさとなりました^^
雪山登山と言うと、ハードなものをイメージされる方も多いかもしれませんが、ちょっとずつステップアップして行く分にはさほど大きな困難はありません。無雪期に登山経験を重ねた方なら、冬の低山ハイキングは問題なく楽しめると思います^^
その一方で、最近は雪山登山経験をあまり持たないまま高い山に足を運んでしまう方も多いようです。
もちろん危険の有無は標高の高さだけに左右されるものではないので一概には全部が危ないとは言いがたい部分もありますが、それでも雪山登山1年生がいきなり冬の赤岳に挑戦しようとする風潮とかはちょっと如何なものかなと感じています。
まず1~2シーズン程度は冬の低山ハイキングを中心に雪の上を歩く経験を十分に積んでもらい、その後標高2,000m前後の山を経験。3~4シーズン目で北八ヶ岳や西穂丸山などの比較的安全な森林限界越えの山を経験し、初めてちょっと難易度の高めの山に挑戦してみるくらいの感覚が良いのではないかと思います。
その間に、雪上歩行技術やアイゼン・ピッケルワーク、初動停止・滑落停止技術、雪崩対策、ロープワークなどの登山技術をしっかりと教育を受ける機会を設け、実践の場で何度も自己訓練を繰り返すくらいの準備が必要です。
はじめる敷居は決して高いものではありませんが、標高の高い岩稜の難しさはかなりのものだと思って頂いたほうが良いでしょう。
低い、比較的穏やかな山でもこんなに素晴らしい美しさがあるんです。
まずはこの素晴らしさをたくさん体験してみては如何でしょうか?
そこには、本当にすばらしい体験があります。
背伸びせず、急がず、細く長く山歩きを愉しみましょう♪
赤城山登山にご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました!
是非また一緒に山に行きましょう。
皆さまのご参加、心よりお待ち申し上げております ^^




















Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪山登山でまったく曇らないゴーグル "RUSH XED"

雪山登山で欠かすことの出来ない、重要な道具の一つであるゴーグル。強風や吹雪の中でも、ゴーグルが視界を確保してくれ、安全な登山の継続を保ってくれます。
また顔の大きい面積を覆ってくれるので、保温や頬骨、鼻の凍傷予防にも役立ちます。
そんなゴーグルにも大きな欠点があります。それはサングラスに比べてとても曇りやすい点。僅かなミスや気象条件で簡単に曇ります。
しかし、ついに発見しましたよ!まったく曇らないゴーグルが存在します!!

雪山登山で欠かすことの出来ない道具の一つに、ゴーグルがあります。
積雪期は山の表面のデコボコが雪で覆われ、フラットな斜面になります。風は抵抗を受けること無く山肌を駆け上がり、登山者に猛烈な烈風を浴びせます。この風が厄介者で、雪を飛ばして視界を奪ってきます。
吹雪の中はもちろんですが、晴れた日でも風が強ければ、降り積もった雪が吹き飛ばされて地吹雪となる場合もあります。
樹林帯以外の山域や稜線上では、常にこの様なリスクがあることを知っておかなければなりません。
視界を維持するためにはゴーグルが必要です。
隙間の多いサングラスと違い、顔に密着するゴーグルをすれば吹雪の中でも視界を確保する事ができます。あたりまえの話しですが、視界を確保することは山の安全上とても重要な事です。ゴーグルは雪山登山を行う上でとても重要な道具の一つと言えます。
しかしゴーグルには大きな欠点があることも覚えておかなくてはなりません。
サングラスの様に周囲が開放されていないと言うことは、雪や風から目を守れると言う利点の一方で、空気が対流しないと言う欠点もあります。
内部と外部の温度差が大きくなることで、ゴーグル内に結露が発生します。つまりは曇ります。

.
しかし世の中にはまったくと言っていいほど曇らない、超ハイテクゴーグルも存在します。
世界最高齢エベレスト登頂記録樹立を果たした三浦雄一郎大先輩も愛用している、SWANS 製の電熱線入りゴーグル"RUSH XED"。
定価35,000円のクッソお高いゴーグルですが、その性能はもう最強!
日本のトップゴーグルメーカーが、予算度外視で技術の粋を集めて本気で開発しただけあり、その高性能っぷりは常識を覆します。
車のリヤウインドウなどに使われているような電熱線ヒーターを搭載したレンズを使用し、ゴーグルとポータブルバッテリーをUSBケーブルで繋いで使用します。
レンズを温める事で結露を防いでいます。
実際にフィールドでテストをしてみると、その凄さに改めて驚かされます。
バラクラバをしたまま着用したまま登ってもまるで曇らないので、試しにおでこのあたりにゴーグルを装着したまま30分以上歩いてみました。
これは雪山登山でやってはいけないことの代表的な例で、まず間違えなく、あっという間にゴーグルが曇ってしまいます。
しかしこの状態で汗ばむほど歩いても、一切の曇はありませんでした。
これはもう、とんでもない事です!!!
今度は電源を抜いて試してみます。
電源を抜いてしまうと、それはもうただのダブルレンズのゴーグル。
一応、世界最高水準レベルの曇り度目処理を施したレンズではあるそうですが、額からの発汗には勝てず、僅か5分程度で視界ゼロの状態に曇ってしまいました…。
しかしここからがすごい!!
再度電源を入れて顔に装着して歩いていると、5分程度で視界が開け始めます。
そのままハイペースに登り続けても、20分もしない内に完全に曇りが取れてしまいます!!!ありえんwww
まぁ現実的には山の中で僅かな時間でも視界を奪われるべきではないので、通常は使用時間中電源を入れたままにすべきとは思います ^^;
登山における視界は、安全上とても重要です。
たしかにチトお高い商品ではありましたが、その価格以上の価値が十分にあると感じています。
正直、これまで購入した登山用品の中でも、トップクラスの満足度の道具となりました♪
雪山登山中のゴーグルの曇りでお困りの方は試してみては如何ですか?
その問題、イッパツで解決しますよ−!お試しあれ^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.1.28 クライミング練習会

クライミング講習にご参加頂いたお客様の練習の場として、無料参加頂けるクライミング練習会を行いました♪
ビレイ技術の維持と上達、基本的な登り方をお伝えしつつ楽しんで頂きました^^
平日の夜、2周間に1回のペースで定期開催していこうかと考えています。
お客様同士のコミュニケーションの場にもなって頂けたようで、とても良かった。
ご興味ある方は是非ご参加下さい!!

Kuri Adventures のクライミング講習にご参加頂いたお客様の、技術の維持と上達を目的とした、クライミング練習会を開催しました!
お伝えしたビレイ技術がきちんと行えているか、クリップの向きや方法に間違えは無いか、チェックを入れつつクライミングを楽しんでもらいます。講習会だけでは伝えきれないビレイ技術を、細かくアフターサービスさせて頂きます^^
お客様同士のコミュニケーションの場にもなって頂けたようで、とても素晴らしい時間となりました。
こうして山仲間の輪を広げることは、単独行で山に入る事を減らすきっかけにもなるのではないかと思うんです。
それもまた、山の安全に繋がる活動に一環になる。
そう信じて、この練習会を定期開催したいと思います。
ご興味ある方は是非ご参加下さい^^
お待ちしております!!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.1.27 Facebook最大の登山コミュニティ"山が好き" 新年会

Facebookの登山系コミュニティ最大規模のグループ"山が好き"の新年会に出席させて頂きました!
さすがは最大規模コミュニティの新年会だけあり、その人数は100名越え!!
渋谷のクラブを貸しきっての、圧巻な飲み会が実施されました♪
ご紹介により壇上に立つ機会を設けて頂き、安全登山に関わるお話を少しだけさせて頂きました。とても素晴らしい会に招いて頂き、感謝感謝です♪

Facebookの登山系コミュニティとして最大規模のグループ"山が好き"の新年会に招いて頂きました^^
さすがは18000人に達する超巨大グループだけあり、その新年会もなんと100名越え!!
渋谷のクラブを貸しきって、圧倒的な規模の飲み会が行われました。その人数は圧巻ですw

.
今回は壇上に立つ機会を頂き、少しだけ安全登山に関わるお話をさせて頂きました。今後も機会があれば、この様な場を通じて安全登山啓発活動を行っていければと思います。
山の危険とその回避方法を知ってもらうことで、登山中の事故は大きく減らせると信じています。
登山は最高の遊びです!自然地に身を置くことは、人間の中に眠る野生の部分を刺激し、生きる実感を感じられます。
登山を行うことで、人生は確実に豊かになります!!
そんな素晴らしい登山の趣味を持った方達に、より安全な登山を楽しんで頂きたい!
それを伝えることは、この業界の職業人としての責務であると感じます。
自分の仕事を通じて、社会に貢献できることはとてもありがたい事です。
今後も活動を続け、山の安全に貢献してきたいものです。
応援頂ければ幸いです^^
この様な機会を頂きました、山が好き管理人の森山様に、この場を借りて感謝申し上げます。
ありがとうございました!!

.
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
2016.1.26 山岳ロープワーク講習

実際の登山で活用する機会の多い、安全確保技術をお伝えしています。
ロープを使って安全確保を行うことで、滑落や転落の事故をとても少なくする事が出来ます。
一般登山においても、時に危険箇所が現れます。そんな時、最低限の装備だけで危険箇所を通過するための技術をお伝え致しました。
定期開催しますので、ご興味ある方は是非ご参加下さい^^

登山の大きな危険の一つに、滑落や転落があります。
これらの事故は死亡や大怪我などの大きな事故に繋がりやすい危険なトラブルですが、しっかりとした確保技術を身に付ければその殆どを未然に防ぐことができます。
山岳ロープワーク講習では、実際の登山で活用できる、最低限の装備で行える危険箇所を通過する方法をお伝えしています。

.
この日は、秋川エリアの山の麓で行いました。
数日前に降った雪が日陰で残り、寒波の影響でカチコチに凍りついた様な状況。実際、どこの山でも起こりえる現象で、うっかり足を滑らすともう止めることが難しい様な、そんな雪質。
この様な状況って、いつでも起こりえます。
鎖場の鎖は氷の中に閉じ込められ、沢筋をトラバースする登山道が雪崩で崩落して、しかもカチカチのつるつるになった氷の斜面。
そんな状況を安全に通過するためには、ロープによる確保が必要です。
ロープを繋がない状態では命がけの区間も、ロープによる確保を行った瞬間、それは大して危険な場所ではなくなるのです。
山岳ロープワーク講習では、最低限必要な技術と知識に的を絞り、何度も練習を重ねることでしっかりと体得してもらえる講習内容にしています。
・タイトロープによるコンティニュアスビレイ
・スタカットビレイによる安全確保
・フリクションノットによる中間登攀
・急峻な場所を安全に下る事ができる、懸垂下降技術
これらの技術をしっかりと覚え、それに必要な装備をいつも備えることで、山の安全は確実に高まります!
多くの登山者がこの技術を身に付ければ、山での事故は激減します。

.

.

.

ご参加頂きました皆さまには、大変高い評価を頂きました♪
これからも登山技術の普及に励み、山の安全に貢献していきたいと思います。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
わかんのカスタマイズキット

わかんがスノーシューみたいに簡単に取り付けられたらなぁ。
なんて思ってたら、ありましたよ!そーゆーカスタムキットが!!
オクトスから販売されている、アルミわかん用ラチェットベルトキット。
一本締めと違い、簡単に取り付けられて緩むこともありません。もちろん、アイゼンを付けたままの装着も可能です。
これはとても便利な商品を見つけちゃいましたよー ^^

雪山登山でのラッセルに必須な"わかん"。
元々は生活の為の道具として作られていた輪かんじきを、登山用にアルミ素材で改良された道具が"わかん"です。
デッキが無いので、浮力はスノーシューやスキーには遠く及びません。実際に足の沈み込みも、ツボ足よりかはマシな程度。でもわかんを使うとラッセルが明らかに楽になります♪
踏み込んだ足が左右にブレず、安定して前の足に荷重移動して乗り込むことが出来ます。積雪50㎝程度もあれば十分使え、胸まで埋まるような豪雪でも問題なく使えます。(この様な状況だと、スノーシューは使いにくくなります。)
日本の人気登山山域には多くの場合トレースがありますので、わかんやスノーシューを使わない事も多くあります。アルパインクライミングでは使用機会も多くなりますが、登攀中は当然使うことはありません。こうなると、"軽い"というのもまた大切な機能です。
雪原歩きにスノーシューが流行っていますが、日本の山にはやっぱりわかんが使いやすいと思うのです。




そんな便利なわかんですが、個人的にはちょっと気に入らない部分もありました。
と言うのも、取り付けが一本締めのものしか無く、ちょっと面倒なんです。
スノーシューのようにビンディング式であったり、アイゼンの様にワンタッチで取り付けられれば便利なのに、これだけ便利な世の中にイマドキ一本締め??何時代よ!?
なんて思っていたら、出ましたよ!便利なのが♪
オクトスと言うインターネットを中心に展開する登山用品販売店のオリジナル商品で、スノーシューなどと同じようにラチェット式のベルトで固定するタイプのわかんです。
ビンディングに比べれば取り付けにやや手間がありますが、その分重量が軽く、コンパクトに持ち運べます。
わかんの良い所をスポイルする事無く、しかも取り付けやすくなっています。
この商品の優れているところが、土台となるベルトに固定ベルトが縫い付けられているところ。
この縫い付けにより、左右に足がずれてしまう事がありません。圧倒的に歩きやすくなります♪
そうは言っても、すでにわかん持ってるしなぁ。
なんて思った方!僕もそう思いましたよ。
でもなんともありがたいことに、各社のアルミわかん用にカスタムキットも出ているんです!!
さっそくポチってしまいましたよ♪
使用感も良く、とても使いやすいアルミわかんに生まれ変わりました。
ご興味ある方は、試してみては如何でしょう^^
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
雪山登山における、ゴーグルとサングラスの使い分け

雪山登山の必須アイテムであるゴーグルやサングラス。
それぞれどの様に使い分けるか、意識したことはありますか?
これを意識しないと、次第にどちらか一方でも良いかな・・・。なんて気がしてきちゃうのですが、やっぱりどっちもあった方が良いと思います。
それぞれの特徴と使用シーンをしっかりと知っておきましょう。
正しい知識を知った上で両方持っていると、きっと雪山登山の安全が高まりますよ^^

雪山登山において、ゴーグルやサングラスは絶対に必要な大切な道具です。
「結局のところ、どっちを持っていけば良いの?」とご質問を受けることがありますが、できればやはり両方持っておいたほうが良いでしょう。
っと言うのも、実はそれぞれ使用シーンが異なるんですよね^^;
雪山登山の多くの時間は、サングラスを装着することとなります。
太陽光の紫外線の多くを照り返す雪山では、雪がない時期に比べて倍近い紫外線に晒されます。
紫外線の影響を受けるのは皮膚だけでなく、実は目も紫外線によって大きなダメージを負います。これを雪盲と言います。
雪盲になると、目が開けていられないくらい目の痛みを伴います。
登山中の危険はもちろん、帰りの運転などにも大きな支障が出ます。
当然目の健康上においても良くないので、晴れた日の雪山登山では必ずサングラスが必要です。
でも、ゴーグルじゃダメなの?ってご意見もあると思います。
確かにゴーグルも紫外線カットできるし、面積が広い分顔の日焼け止め効果も期待できる。ゴーグルだけでも良い気がします。
しかし、ゴーグルには大きな欠点があります。
ゴーグルは密閉度が高いので、サングラスに比べてとても曇りやすいんです。風が強い条件がでの使用では、あっという間に曇ってしまいます。
ゴーグルは、基本的に森林限界を超えた場所で、風が強い時に使うものだとお考え下さい。
ただ限定的に、アイスクライミングで使用するのはありだと思います。
顔の多くの部分を覆うことが出来るゴーグルは、アックスを降った時に飛んで来る氷から顔や目を守ってくれます。
サングラスでも良いのですが、ゴーグルならより良いでしょう。
この様に、森林限界を超える登山においては、ゴーグルとサングラスの両方が必要です。
森林限界以下しか歩かない場合ではサングラスだけでも良いかもしれませんが、急な気象変化を考えるとできれば両方持っていたほうが安心でしょう。
尚、外したゴーグルやサングラスを額に置いておくのはやめましょう。
ヘルメットの様に湿気を通さないものの上なら構いませんが、帽子の上などでは発汗量の多い額の湿気で、あっという間に曇ってしまいます。
その曇はすぐに凍結し、下山するまで曇りが取れなくなる事も・・・。
外したゴーグルやサングラスは、バックパックなどの中に入れておくのが懸命でしょう。
この事を、動画でも説明していますので、ご興味ある方は是非見てみて下さい^^
皆さまの安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
超軽量ハーネス Black Diamond クーロワール

ハーネスと言うと、スポーツクライミングのカラフルなしっかりとしたハーネスを思い浮かべる方も多いでしょう。
しかしあのハーネスって、登山で使うとバックパックと干渉してイマイチ使いにくかったりしませんか?
登山に使うには、パットが省略された登山専用のものを用意したほうが快適です。
今回は個人的に愛用している、登山用ハーネスを紹介します。

雪山登山や沢登り、岩稜のバリエーションルートなど、滑落の危険を伴う場合がある山行ではロープによる確保を行いたいものです。
しかし登山では多くの荷物を運ばなくてはならないため、少しでも荷物をコンパクトにまとめたいもの。
そんな中、スポーツクライミングに使うクライミングハーネスをバックパックに詰めようとするとかなり嵩張り困るものです。
また背中側にもついたしっかりとしたギヤラックや、衝撃を吸収するための分厚いパッドがバックパックと干渉し、ウェストベルトが使いにくかったりします。

.
そこでおすすめなのが、シットハーネスとかアルパインハーネスと呼ばれる、登山用に開発されているハーネスです。
このタイプのハーネスには、衝撃吸収用のパッドがありません。
墜落することがあたりまえのスポーツクライミングと違い、そもそも墜落や滑落を起こさないことを前提としている登山では、墜落時の快適性はあまり重要ではありません。
もちろん大きな墜落をすれば腰に痛みを伴う場合もあるかもしれませんが、安全性はしっかりと確保されています。
パットが無い分薄く、バックパックとの干渉がほとんど起こりません。
またサイズがとても小さく、軽量に収まるので、収納・運搬にも適しています。
個人的には、ブラックダイヤモンド社のクーロワールを愛用しています。薄く、軽く、すぐに乾く、とても使いやすいハーネスです。
小さく軽いと言うことは、登山者にとってとても大切なこと。
運搬が楽であれば、ロープを使うかどうか分からない山行にもいつも持って行きやすいですよね!
それこそが、安全に繋がる大切なポイントだとも思います。
この様なハーネスや補助ロープの携行、ロープワーク技術を身につけることがもっともっと普及すれば、山の安全は高まると思うんですよね。
このブログを読んで興味を持たれた方は、ちょっとずつロープワークを学んでみませんか?
ある日、あなたと大切な仲間を助ける日が来るかもしれませんよ?
その時、きっと小さなハーネスと頼もしいロープが役立ちます。
来ないと良い"いざ"と言う時の為、今から始めてみては如何でしょう。
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
おすすめの細引き紐 " シンギングロック アクセサリーコード "

テントの張り綱に、フリクションノットコード、沢でのお助け紐など、様々な用途で使う細引き。そんな細引きのメーカーって気にしたことありますか?
低価格な商品なのでなんとなく適当に買っているかも知れませんが、実はメーカーによってその使用感がかなり異なるようです。
今回たまたま登山用品店で発見したシンギングロック社のアクセサリーコードは、実に靭やかで扱いやすい印象です!

チェコ共和国のシンギングロック社。
近年このシンギングロック社の製品が、世界各国のレスキューシーンで採用され注目を集めています。
チェコ人のクライマーとベルギー人のセールスマンによって設立されたシンギングロック社は、主にテキスタイル(繊維)製品を中心に扱うメーカーです。その技術が素晴らしく、同じナイロンとは思えないほど靭やかな製品を作り出すと評判です。
近年では日本でも取り扱われ始めています。
先日、フリクションノットコード用の6mmの細引きと、補助ロープとして使う7mmの細引きを購入しに登山用品店に足を運びました。
そこで偶然であったのが、シンギングロック社のアクセサリーコードでした。
噂に違わぬ靭やかな触り心地は、いかにも扱いやすそう。
補助ロープはこれまで7mmを愛用してきましたが、このしなやかさなら8mmでも十分扱いやすいと感じ、今回は8mmを購入してみました。
自宅でテストをしてみた感じでは、これまで使用してきたどの細引きよりも個人的には好きです。
好みはあると思いますが、靭やかで柔らかい使用感が好きな方には特におすすめですよ!
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山のロープワーク " クレイムハイスト "

プルージックと並ぶ、フリクションノットの代表格。
巻きつけた部分を握ればテンションを解くことができ、末端部分にテンションをかければすぐにロックするとても便利な結びです。
一方向にしか効きませんが、その分とても強く効いてくれます。
例えばロープ1本に対して巻きつける場合、プルージックなどよりもずっと安心して使うことが出来ます。
ただしトラバースを伴う様な登攀に使用する場合には、少し使いにくいと思います。特性を理解した上で活用しましょう。

クレイムハイストは、プルージックと並ぶフリクションノットの代表格の1つです。
プルージックの様にどちらの方向にもロックがかかる訳では無く、結びの方向を間違えると危険です。しかしその一方で、フリクションノットとしての効きはプルージックよりずっと強く、しかもうまく巻きつければアッセンダーの様に手で繰り出さなくても進むことが出来ます。
特性を理解し、使い分けることで安全性や利便性はさらに高まるでしょう。
使う道具はプルージックと同じ。細引きで作ったロープスリングを使います。
フリクションノット用に作ったロープスリングを、ここでは"フリクションノットコード"と呼んでいます。
原則として、7mm × 150cm のアクセサリーコードをダブルフィッシャーマンズノットで輪にしたものを使います。
ただし 8mm ロープなど、細経のロープに対しては 6mm のアクセサリーコードを使用したほうが良い場合もあります。
ロープと細引きの相性がありますので、使用前に必ず効きを確かめましょう。
また使用する細引きのメーカーによっても、使いやすさに差があります。
高いものではないので、いくつか試し、使いやすいものを探しましょう!

フリクションノットコードの、結び目の反対側あたりをロープに添えます。

ロープを添えた部分を指で固定し、3回キレイに巻きつけます。

指で抑えた部分にできている輪に、巻きつけた末端を通します。

下方向に末端を引っ張りながら、写真の様にキレイに形を整えれば完成です。

巻きつけた部分を持てば、かんたんにロックを解除できます。

末端部分に、下方向に対してテンションがかかるとクレイムハイストがロックします。
この末端部分に安全管付きカラビナを付け、ハーネスやその他対象物と繋いで使用します。

末端を上方向に引き上げ、全体を緩めると抵抗なく巻きつけ部分を引き上げることができます。
途中で下方向に荷重が移れば、すぐにロープとフリクションノットコードがロックします。
ちょうどアッセンダーと同じような働きとなります。
ロープが屈折したりして抵抗があると、クレイムハイストが締まって動きが悪くなることがあります。
動きが悪くなった場合、再度少し緩めて使用してください。
アッセンダーの様に使う場合、アッセンダーと同じく両端が固定されたフィックスロープに使用する事が前提となります。
基本的に下方向にしか効きませんので、トラバースなど、どちらに荷重がかかるかわからないような場合にはプルージックの方が適しているでしょう。適材適所、使い分けに注意して下さい。
ヨーロッパの登山シーンでは、もっとも使われるフリクションノットがクレイムハイストだそうです。
慣れればプルージックよりかんたんに結べ、解除もスピーディー。
とても便利なので、是非覚えてみてください^^
Kuri Adventures では、気楽に参加できる" 登山のワークショップ " を行っています。実際に直接指導させて頂きます。
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームなワークショップですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
登山のロープワーク " スリップノット "

セルフビレイコードに使うスリングにカラビナをセットしたり、タイトロープの枝にカラビナをセットする時などに便利なスリップノットを紹介します。
この結び方を覚えることで、枝や足を輪にひっかけにくくなります。
この事は、登山の安全にとってとても重要な事です。
また簡単に結べて、強いテンションがかかった後でも簡単に解く事が出来ます。
この様な使い方をする場合、クローブヒッチなどよりも使いやすいでしょう。

スリングをハーネスに結んで作るセルフビレイコード。
一時的なセルフビレイに使ったり、懸垂下降時にバックアップを設ける際などにも、デバイスを離した位置にセットしたりなどいろいろ便利です。クライミングはもちろん、少し難易度の高い登山をするなら欠かせない装備でしょう。
しかしスリングにただカラビナを取り付けただけでは危険です。
カラビナの中でスリングが自由に動くため、片側だけがびろーんと伸びがち…。
こうなると、膝を引っ掛けたり、枝を引っ掛けたり…。
そうならないように、カラビナとスリングはしっかりと固定しましょう!
一般的にはクローブヒッチで固定する場合が多いようですが、それだとスリングとスリングの間に隙間ができてしまいます。
スリップノットなら、そのような隙間ができません。
またキーロックゲートのカラビナでなくても外しやすかったり、強いテンションがかかった後でも簡単に解けたりと、多くの利点があります。
セルフビレイコード以外にも、タイトローピングの枝や、スリングで作る簡易ハーネスにカラビナを取り付ける場合。スリングとカラビナで作る、いわゆる"アルパインヌンチャク"にも便利です!
是非覚えておきましょう。

ロープやスリングの途中に輪を作ります。

その輪に、ロープを折り返すように入れます。

折り返し部分を持ちながら、輪の方のロープを引っ張ります。

結び目を締めあげて完成です。

結んでできた輪の部分にカラビナを入れ、さらに締め上げます。
カラビナがやや固定された状態にします。
セルフビレイコードやタイトロープの枝に足を引っ掛けたりするととても危険です。
せっかく安全の為に使うなら、是非そのシステムにスリップノットも取り入れてみてください。
皆さまの安全登山にお役立て頂ければ幸いです^^
Kuri Adventures では、気楽に参加できる" 登山のワークショップ " を行っています。実際に直接指導させて頂きます。
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームなワークショップですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
雪山登山技術 " ピッケルでセルフビレイをとる方法 "

急峻な雪の斜面を登る場合、万が一の滑落に備えてスタカットビレイに切り替えます。
支点設置の難しい雪上において、もっとも簡単な支点構築方法はピッケルを使った支点構築方法です。素早く簡単に支点を作ることができ、しかもそれなりに信用できる支点になってくれます。
雪上のどこでもセルフビレイがとれるのは安心ですね^^
雪山登山の安全に大きく関わる技術ですので覚えておきましょう!

雪山登山中に危険を感じる様な急峻な斜面が現れた場合、スタカットビレイで慎重に登るべきです。
雪上でのスタカットビレイは、ボディビレイが基本となります。肩絡みや腰絡みなど、支点に直接衝撃を与えないビレイスタイルが安全です。
しかし一定以上の墜落衝撃があれば、自分自身がバランスを崩して滑落に巻き込まれてしまう可能性があります。
それを避けるために、セルフビレイが必ず必要です。
強固な支点からとったセルフビレイがあって、初めてスタカットビレイは確実性の高い安全なビレイ方法となります。

.
雪上で支点をとるのにもっとも適した方法は、ピッケルをT字に埋めることです。
アッズ(ヘッドのショベル部分)で斜面に対して横に穴を掘ります。
なるべく直線的に、深さ50㎝以上掘りましょう。
続いて横穴の丁度真ん中あたりから、斜面下方向に対して掘ります。
ピッケルの中央部に長いスリングをガースヒッチで結び、横穴にピッケルを入れます。スリングは横穴から斜面下方向に掘った溝に入るようにします。
斜面の上側から下側に向け雪を落とし、ピッケルを穴に埋めます。しっかりと上から圧雪し、雪を固めましょう。
スリングの先端には安全管付きカラビナをセットします。
メインロープを安全管付きカラビナにクローブヒッチで結び、セルフビレイとします。
この時、自分が立つ位置(又は座る位置)についた時のロープの流れが、ピッケルより低い位置にあるようにします。
この支点は、ピッケルの斜め下方向に引かれた時に初めて効く支点です。上方向に力が働けば簡単に支点は崩壊していしまいます。
必ずピッケルに下方向の力が働くように、溝の深さや角度、ロープの流れなどには十分注意しましょう。
スタンディングアックスビレイの時には他にアンカーが必要です。ショベルなどをデッドマンとして使い、アンカーとしましょう。

.
セカンドクライマーをビレイし、そのまま次のピッチまでリードしてもらいましょう。
この時、フォールライン(もし滑落した時に滑って行くと予想される方向)にビレイヤーが入らないように登っていくことが大切です。
ロープいっぱい付近になったら声掛け、セルフをとってもらいます。
パートナーの準備ができたら埋めたピッケルを開始し、登攀を開始します。
この様に交互に確保をとりながら登る方法を"スタカットビレイ"と言います。
とても安全性が高い登り方となります。
雪山で少しでも危険だと感じる場合は、面倒がらずにスタカットビレイに切り替えることが大切です。
この時にしっかりとしたアンカー設置ができるかどうかが、パーティー全体の生命線となります。
安全の為にも、しっかりと練習しておきましょう!
Kuri Adventures では、気楽に参加できる" 登山のワークショップ " を行っています。実際に直接指導させて頂きます。
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームなワークショップですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
テムレスのロゴを消す方法

透湿性を持つゴム手袋の"テムレス"。
絶対的な防水性と作業性に加え、透湿機能により蒸れないテムレスは、登山においてとても使いやすい手袋です。特に防寒テムレスは、クライマーを中心に広く愛用されています。
低価格で高性能なテムレスにも、唯一弱点が…。それは超が付くほどダサいロゴ…。
しかしこのロゴ、どうやら消す方法があるようです!

作業用ゴム手袋として開発された、透湿性能を持つゴム手袋の"テムレス"。
これまでのゴム手袋で感じていた不快な蒸れが起こらない、とても優れたゴム手袋です。
特に冷凍庫内作業用に開発された防寒テムレスは、今登山者の間で密かなブームになっているのはご存知でしょうか?
ゴム手袋特有の圧倒的な防水性と作業性。雪山にはぴったりの特性です♪
絶対的な保温力にはやや欠けますが、−15℃程度までは問題なく使えます。
アイスクライミングやアルパインクライミングの際には、素晴らしい威力を発揮します!
またテント設営用に使ったり、オーバーグローブ紛失時対策のバックアップとして活用される方います。
一般的な雪山登山にも十分使える性能を持ちながら、それを躊躇される方も多いようです。
その最大の理由が、あまりにダサいロゴ…。
でもこのロゴ、どうやら消せるらしいんです!
このダサいろごが消せるなら、テムレスはより使いやすい手袋になるのではないでしょうか!??

あまりに主張が強すぎる、防寒テムレスのロゴを消します。

ティッシュやコットンにマニキュア用除光液を染み込ませます。

表面を撫でるように、ロゴの部分を擦ります。

あっという間に、ロゴを完全に消すことができました!
このロゴが消せるなら、テムレスのダサさもだいぶ軽減できそうですね^^
気になっていた方は、是非早速試してみてください♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
クライミングロープ " 絡まらないロープのまとめ方 "

沢登りや雪山登山、岩稜登山など、ちょっと難しい登山ではロープを出すことも多くなります。しかしクライミングと違い、ずっとロープを出しているわけでは無く、その多くは"歩き"となります。
ロープを使う段階になったら素早く必要最低限だけ出し、それ以外はバックパックにまとめておきたいもの。
そんな登山での使用に特化した、便利なロープのまとめ方をご紹介します!

沢登りや雪山登山、岩稜登山など、ちょっと難易度の高い登山を行うようになるとロープが必ず必要になります。
クライミングのようにロープを出しっぱなしにする場合には、振り分けでロープをまとめる方法がやはり便利ですが、ロープを出すのに時間と場所がかかります。
登山でロープを使う場合、素早く必要最低限だけ出し、不要な分はバックパックにしまったままにできると便利です。
ロープの片側末端を自分のハーネスに結び、もう一方の末端にはカラビナをセット。バックパックのショルダーハーネスなどにかけておきます。
必要なときはそのカラビナを外し、引っ張るだけで絡まること無くスムーズにロープを出すことが出来ます。
この様に、ロープを出す手間を少しでも少なくすること。
このことこそ、安全登山に繋がると感じています。

大きめのスタッフバッグを用意します。使いやすいので、冬用寝袋のものを推奨します。
まず最初にロープの片側の末端にはエイトノットを作ります。
このエイトノット側を自分のハーネスに結ぶと覚えておきます。
登山開始時には、このエイトノット側の末端を自分のハーネスに結びましょう。

エイトノットとスタッフバッグの縁とエイトノット部分を持ち、反対の手でエイトノット側からスタッフバッグの中へロープを入れていきます。

奥から順に、上へ積み重なるように少しずつ、どんどんロープを入れていきます。

反対側の末端まで来たら、目印としてオーバーハンド・ノットで結んでおきます。
登山前にはオーバーハンド・ノット側の末端にカラビナを結び、バックパックのショルダーハーネスに引っ掛けておきます。

スタッフバッグの内側のドローコード(一番入口側のドローコード)を絞ります。
実際に使用する時には、スムーズにロープが出てくるよう緩めます。

外側に来る2段目のドローコードを絞り、末端を先ほどのドローコードとこのドローコードの間に収めます。
まとめたスタッフバッグはバックパックの一番上に収納します。
登山前にはバックパックのドローコードから末端を出し、エイトノット側を自分のハーネスへ、オーバーハンド・ノット側にはカラビナを付けてショルダーハーネスに繋いでおきます。
登山中にロープが必要になったら、ショルダーハーネスからカラビナを外すだけでスムースにロープが引っ張り出せます。
ロープの使用が終わったら、出した分のロープだけたすき掛けにしてまとめます。
バックパックの中身を出すときにも、ロープが邪魔になることが無くなりますし、絡むこと無く素早くロープが出せるようになるので、登山の進行がとてもスムーズでストレスの無いものになるでしょう。
またロープを手間なく出せると言うことは、登山中の安全にも直結します。
"この程度のところで大げさな"とか、"いちいち面倒くさい"とか思わずに、安全を再優先する。それはとても大切なことです。
ちょっとした事でもしっかりと確保をとる事で、登山はより一層安全なものになります。
たかがロープのまとめ方ですが、この様な細かいことの積み重ねが安全登山に繋がります。
きっと便利だと感じてもらえますので、是非覚えてみてください^^
Kuri Adventures では、気楽に参加できる" 登山のワークショップ " を行っています。実際に直接指導させて頂きます。
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームなワークショップですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山技術基礎 " ほどけない靴紐の結び方 "

登山中に靴紐が解ける事が多かったりしませんか?
しかも、なんか解けやすい日と、ハードに歩いても解けない日があると思いませんか?
実は結ぶ時にちょっと注意するだけで、ずっと解けにくくなるんです。
そんな注意ポイントを、動画とブログで説明しています。
さらに!
より解けにくくなる、応用形の靴紐の結び方を伝授します!!

登山中に靴紐が解けた経験。きっと誰にでもあると思います。
靴紐の解けは転倒に繋がる可能性があり、場所によっては非常に危険です。何より何度も足を止めるのはとても面倒です。
ところで、なんか靴紐がほどけやすい時と、ハードに歩いても解けない時があったりしませんか?
これ、実はきちんと結べている時とそうでない時の差なんです。
無意識で結ぶのではなく、あることにちょっと意識するだけで、靴紐はずっと解けにくくなります。

靴紐を結ぶ時、ブックノットの形になるようにします。
左右対称の形になっていないと、ちょっと引っ張るだけで簡単に解けてしまいます。(詳しくは動画を御覧下さい。)
右側の紐を上に結び始めたら、蝶々結びを仕上げる時の2回めの結びは左側を上に結び始めて下さい。
実はたったこれだけの差で、実に解けにくくなります。
解けやすいかそうでないかの差は、実はこの結ぶ順にあります。
さらに、もう1つ工夫すると、まったく解けない結び方になります!
結び方は簡単♪ それぞれの結びを2回ずつ巻くだけで、たいへん解けにくくなります。
詳しくは写真の流れを追って説明します。

まず踵をとんとんと叩き、かかとを靴に密着させます。

足の甲から靴紐を締めあげていきます。
足首を締める時がポイント!
踵が浮いてしまわないよう、足首の紐を締め込みながら踵を密着させます。
ここをしっかりと密着して動かないようにすることで、明らかに安定感が上がります。
しっかりと意識しましょう!

続いて足首を締めます。
登りは緩め、下りはキツ目にしましょう。
登りは足首の屈折が大きくなりますので、足首の可動がし易いほうが楽です。
一方下りは足首にかかる負荷が多くなりますので、キツ目に締め上げます。

一番上のフックは、上から下に引っ掛けましょう。
こうすることで交差部分の真上に結び目が来ることになり、より一層靴紐が解けにくくなります。

靴紐を結ぶ時、通常1回転させる部分を2回転に増やします。

ブックノットの形になるように注意しながら、さらに2回転させながら結びます。

残った末端の長さを整え、末端を全てまとめて結んでおきます。
この結び方をすることでまず解けることは無くなります。
たかが靴紐ですが、うっかり踏んでしまうと大きな事故に繋がりかねません。
こうした基礎の基礎からしっかりと注意しておくことで、山の安全は高まっていきます。
是非この結び方を覚え、登山の安全を足元から固めてみてください^^
皆さまの安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪
Kuri Adventures では、気楽に参加できる" 登山のワークショップ " を行っています。実際に直接指導させて頂きます。
初めての方でも十分楽しんで頂ける、アットホームなワークショップですので、是非お気軽にご参加下さい♪
Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪
登山のセルフレスキューに必要な道具 "ペツル クレバスレスキューキット"

ペツルのクレバスレスキューキットは、クレバスに落ちた仲間を救う為に用意されたセットですが、実は登山のセルフレスキューにおいて欠かせない道具でもあります。
先日紹介したレスキューキットでも問題なくレスキューを行えますが、このセットを使うことでより簡単に、より効率良く作業が行えるようになります。
マルチピッチクライミングやバリエーションルート、雪山登山で必ず持ちたい装備です。
装備の準備に合わせ、レスキュー技術と知識も身につけておきましょう。

携行していない人も多いようですが、クライミングに出かける時や、雪山登山で稜線上を歩く時、痩せ細った岩稜を歩く時、春から夏の雪渓上を歩く時には必ずレスキューキットを持ちたいものです。
ロープを繋ぎ合ったパートナーがオーバーハングで墜落した時や、雪庇を踏み抜いた時、シュルンドに墜落した時、あなたは中にぶら下がったパートナーを救い出せますか?

パートナーが墜落した場合、パートナーが自力で登ってくるか、又はレイジングシステムでパートナーを引き上げる必要があります。
クライミングに使う最低限の装備だけでも出来ないことはありませんが、極めて効率が悪く、困難を伴います。この様なシーンに、レスキューキットがあると大変助かります。
また自分が墜落して登り返す時も、レスキューキットを持っているととても効率良く登り返すことが出来ます。
場合によっては、プーリーを使わないとまったく持ち上がらないこともあります。
まだレスキューキットを持っていない方は、是非装備に加えたいものです。

ペツルのクレバスレスキューキットは、これらのセルフレスキューの際に、より簡単で効率の良いレスキューを実現するキットです。
例えば上の図にある様な
1/3レイジングシステムを構築する場合、通常はプルージックでロープの逆戻りを防止した上でプーリーを使って構築します。この場合、プルージックコードの遊び分だけロープが戻ってしまいます。
この部分にセルフジャミング機能を持ったマイクロトラクション(クレバスレスキューキットの1つ)を使えば、一切の戻りが無いレイジングシステムを作ることが出来ます。
またコンパクトなアッセンダーである"タイブロック"や高効率プーリーの"パートナー"、オーバルカラビナが2つに、120㎝のダイニーマスリングが1つと、必要なものが全てセットになっています。バラバラにも購入できますが、セットで購入するとけっこう安くなるようです。
もちろん、道具を揃えただけではダメで、しっかりと使い方も熟知しなくてはなりません。
まずは道具を揃え、実際に練習を重ねて技術を身につけましょう。
使用するシーンはあまり無いかも知れませんが、万が一の時に困らないよう、レスキューキットは必ず用意しましょう。


Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓
登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。
良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!
~ 無料相談受付中 ~
登山の無料相談を行っています。
ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪










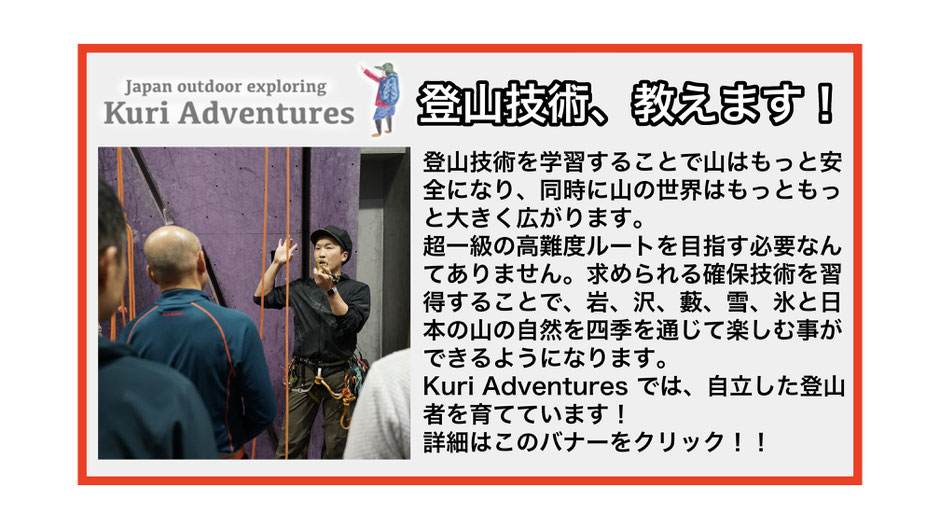
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d51a47d.201df8f0.1d51a47e.d1ee1f70/?me_id=1191175&item_id=10030925&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuyoshi%2Fcabinet%2Fari%2F01%2Fari-0309200.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












































































